介護職の「ボーナス(賞与)」は、正社員の約7割に支給されており、平均額は年間50万円台と言われています。しかし、施設形態や雇用形態によっては「賞与なし」の職場も存在し、その差は最大で数十万円以上。
本記事では、最新の統計データと現場の実態をもとに、介護職員のボーナス相場から支給条件、アップの方法まで徹底解説します。これから介護職を目指す方、転職を検討している方、そして現役職員の方にも役立つ「ボーナス完全ガイド」です。
介護職員のボーナス(賞与)の平均額と相場

介護職全体の年間平均賞与額【最新データ】
介護職員の年間平均賞与額は、おおよそ40万円〜65万円前後となっています。これは全産業平均(約90万円)に比べると低めですが、介護業界全体の給与体系や人件費構造を考えると妥当な水準といえます。
全国規模の調査結果では、正規職員の平均支給額は年間2回合計で50.8万円(厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 ※1)というデータがあり、パート職員の場合は支給額が10万円未満にとどまるケースも少なくありません。
こうした数値を把握することで、転職や待遇交渉時に適正かどうかの判断材料になります。
年齢別のボーナス平均額|40代でピークを迎える理由
介護職員のボーナスは年齢が上がるにつれて増加し、40代でピークを迎える傾向があります。理由は、40代は管理職やリーダー職への登用が多く、評価基準で加点されやすいためです。
例えば、介護労働安定センターの調査(※2)では、20代前半の平均賞与は約40万円台、30代後半で50万円台に上昇し、40代で60万円台に達します。50代以降は役職定年や勤務時間短縮の影響でやや減少します。
実際に特養でユニットリーダーとして勤務する40代職員は、基本給の高さと役職手当の加算により賞与額が同世代の一般職員よりも年間で10万円以上高くなっています。
このように、年齢と経験、役職が複合的に影響し、40代が最も高額になりやすいのです。
勤続年数別のボーナス平均額|長期勤続のメリット
勤続年数が長いほどボーナス額が高くなるのは、介護業界でも共通です。長期勤続は評価基準の一部に組み込まれており、昇給や役職登用にも直結します。
例えば、勤続1年未満では賞与支給額が年間10万円未満のケースが多いですが、5年以上になると50万円以上、10年以上では60万円を超える事業所もあります。
実際に老健施設で10年以上勤務する介護福祉士は、勤続年数による昇給と役職手当の効果で年間賞与額が平均より15万円以上高くなることもあります。
このため、安易な転職よりも長期勤務で昇給・加算を重ねる戦略が、賞与額アップの近道となります。
職種別の平均額|介護福祉士・ケアマネ・管理職の違い
職種によってボーナス額は大きく異なります。介護福祉士やケアマネジャー、管理職は資格や職務責任の大きさに応じて高額になる傾向があります。
介護労働安定センターの調査(※2)では、介護福祉士の平均賞与額は約58万円、ケアマネジャーは約65万円、施設長クラスでは100万円を超える事例もあります。
例えば、特養の施設長は人事評価の最終責任者であり、施設運営の成果が直接賞与に反映されるため、高水準になります。
このように、資格取得や職種選択は賞与額に直結するため、キャリア設計の重要な判断材料になります。
資格別の平均額|介護福祉士、初任者研修、無資格比較
保有資格によって賞与額は顕著に差が出ます。介護福祉士は資格手当や評価加点の対象となるため、賞与額が高くなるのが一般的です。
介護労働安定センターの調査(※2)によれば、介護福祉士の年間賞与額は約58万円、初任者研修修了者は約41万円、無資格では37万円前後にとどまります。
たとえば、初任者研修から介護福祉士にステップアップした職員が、賞与額で年間5万円以上増加した事例もあります。
資格は一度取得すれば長期的に収入に影響するため、取得のメリットは大きいと言えます。
施設形態別の平均額|特養・老健・介護医療院・グループホーム
施設形態によっても賞与額は異なります。一般的に、特別養護老人ホームや介護老人保健施設は公的補助が安定しており、賞与水準が高めです。
介護労働安定センターの調査(※2)では、特養の平均賞与額は約78万円、老健は約70万円、介護医療院は約73万円、グループホームは約41万円程度です。
例えば、特養は入所者数が多く稼働率が安定しているため、固定的な収益を背景に賞与が安定しやすい傾向があります。
就職・転職時には施設形態による差を確認することで、長期的な収入見込みを立てやすくなります。
※ 介護職員の平均月収について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/2025saishin-kaigosyoku-heikingessyuu/
雇用形態別|正社員・契約社員・パートの支給状況
雇用形態による賞与の有無と金額差は大きく、正社員は約7割の施設で賞与あり、契約社員は約5割、パートは約4割にとどまります。
正社員の年間平均額は54万円台ですが、パートは10万円未満が多く、勤務日数や時間に応じて計算されます。
例えば、週5日フルタイム勤務のパート職員が年間15万円の賞与を受け取った例もありますが、支給の有無は事業所ごとの規定次第です。
賞与を重視する場合は、正社員または契約社員での雇用が有利です。
※1【参考資料】厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種
※2【参考資料】公益社団法人 介護労働安定センター 令和4年度 介護労働実態調査結果について 事業所調査「事業所における介護労働実態調査 結果報告書」資料編 P.126-127
ボーナスの支給時期・回数・査定基準

ボーナスはいつ支給される?(夏・冬・期末)
介護職員のボーナスは、夏(6〜7月)と冬(12月)の年2回が一般的です。加えて、業績連動型の期末賞与を支給する事業所もあります。
これは法人の決算時期や資金繰りに合わせて決定されるため、全ての施設が同じ時期とは限りません。
例えば、ある社会福祉法人では6月と12月に基本給の2か月分を支給し、黒字の場合は3月に期末賞与を追加しています。
この支給スケジュールを把握しておくことで、年間の資金計画や貯蓄計画が立てやすくなります。
査定基準は基本給+評価|勤怠・勤務態度・貢献度
ボーナスの算定は「基本給×支給月数+評価点」が基本です。評価には出勤率、勤務態度、業務成果、資格、役職などが反映されます。
評価基準が明確な事業所では、職員が納得感を持ちやすく、モチベーション維持にもつながります。
たとえば、ある老健施設での評価項目には「遅刻・欠勤日数」「研修参加状況」などが含まれており、基準を満たせば満額支給となります。
自分の勤務先の評価基準を確認することで、賞与額を意識的に高める行動が可能になります。
※ 介護職員の基本給が低い理由について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-kihonkyu-nccu/
1年目の介護職員はもらえる?
1年目でも支給対象になるケースは多いですが、満額支給とは限りません。採用時期や就業規則により、在籍期間が一定以上でないと支給されない場合があります。
例えば、6月採用の職員は12月の冬季賞与のみ支給、または在籍半年未満は寸志程度(数万円)になるケースが一般的です。
新卒で特養に入職した職員が、初年度は夏1万円・冬25万円だった事例もあります。
採用前に「初年度賞与の条件」を必ず確認しておくことが重要です。
休職や退職月の場合の取り扱い
休職期間や退職月は賞与の減額や不支給になる場合があります。これは勤務実績や在籍日数に応じた按分計算が行われるためです。
例えば、病気休職で3か月間勤務していない場合、勤務割合に応じて支給額が半分になることがあります。
実際に、規定で「支給対象は査定期間中の出勤率が8割以上」と定める事業所もあります。
休職や退職を予定している場合は、賞与への影響を事前にシミュレーションしておくと安心です。
法律上の支払い義務はあるのか?
ボーナスは法律上の支払い義務がなく、就業規則や労働契約に明記されていない限り、必ず支給されるものではありません。
そのため、業績悪化や経営方針によっては支給が減額・カットされる可能性もあります。
たとえば、賞与支給の明記がある契約社員は減額する場合も事前説明が必要ですが、明記がなければ支給そのもの見送ることも可能です。
安心して働くためには、採用前に就業規則や契約書で「賞与の有無と条件」を確認することが不可欠です。
※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/
賞与なしの介護職場は本当にある?

賞与制度がない施設の特徴
介護業界には、実際に賞与制度そのものが存在しない施設もあります。特に小規模な事業所や営利目的の新規参入施設では、固定給のみで賞与がないケースがあります。
その背景には、利益率の低さや運営初期の資金繰りを優先している事情があります。
例えば、開設から間もないグループホームでは、運営安定までの数年間は賞与制度を設けず、昇給や手当で還元する方針をとることもあります。
賞与の有無は就業規則や求人票で事前に確認し、制度がなければ年収ベースで納得できるかを判断することが重要です。
賞与カットや減額の理由
賞与が制度上存在しても、業績不振や収支悪化で減額・カットされる場合があります。介護報酬改定による減収や、利用者減少、感染症流行時の稼働率低下が主な要因です。
例えば、コロナ禍では一時的に賞与を半減した施設が全国的に見られました。これは、固定費負担を軽減し、事業継続を優先するための措置です。
ただし、事前説明や労使協議なしに一方的に減額することはトラブルの元になります。
勤務先の経営状況や業績連動型の賞与かどうかを普段から把握しておくことが安心につながります。
パート介護職員のボーナス支給率と条件
パート勤務の介護職員にも賞与が支給される事例はありますが、その割合は全体の約4割程度にとどまります。
支給条件は「週の勤務日数」「年間労働時間」「勤続期間」などがあり、正社員と同じ基準ではありません。
例えば、週5日フルタイム勤務のパート職員は年間10〜15万円支給されるケースがある一方、週3日勤務では寸志程度にとどまります。
パートであっても賞与を重視するなら、事前に支給条件と実績額を確認することが大切です。
介護職員等処遇改善加算とボーナスの関係
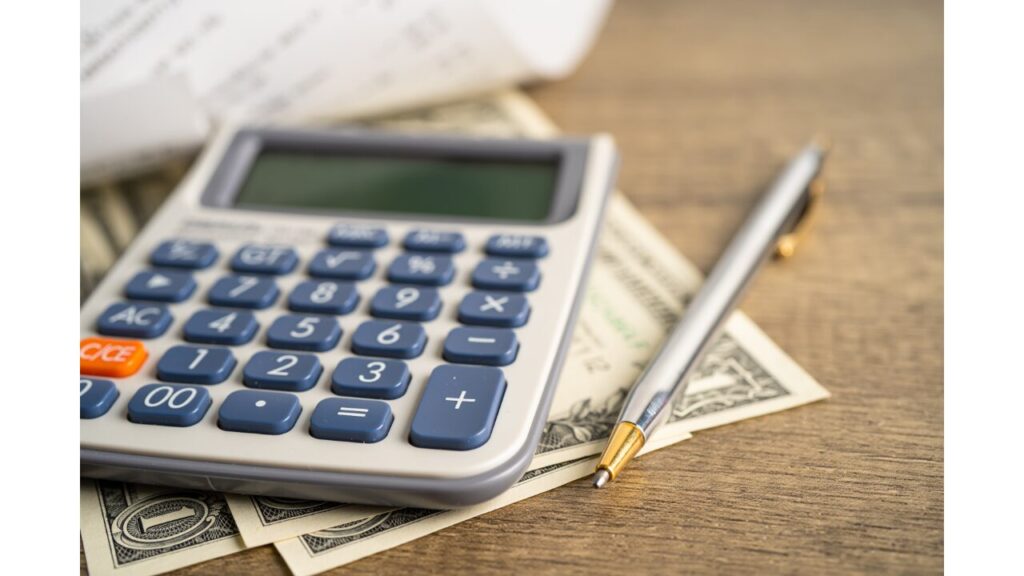
処遇改善加算とは?
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善を目的に介護報酬に上乗せされる制度です。国が定めた要件を満たす事業所に対して支給され、職員の基本給や賞与に充てられます。
加算には複数の区分があり、高い区分ほど加算率が高くなります。
例えば、特養で加算を取得している施設では、年間数百万円単位で介護職員の処遇改善に充てられています。
制度を理解することで、自分の賞与額の裏付けや改善余地を把握できます。
賞与への配分方法と金額アップの事例
処遇改善加算は、職員間で公平に分配される必要がありますが、配分方法は施設ごとに異なります。
一部の施設では、加算の一定割合を年2回の賞与に上乗せし、残りを月額給与に反映する運用をしています。
例えば、年間加算額が1人あたり30万円の施設では、そのうち15万円を賞与に加算し、残りを月々の手当に分けています。
この配分方法次第で、同じ加算額でも年間賞与が数万円単位で変わるため、施設の運用方針を知ることが重要です。
加算を活用している施設の選び方
処遇改善加算をしっかり活用している施設は、求人票やホームページで加算取得状況を明示しています。
加算を活用していない、または低い区分しか取得していない施設は、賞与や給与面での改善が限定的になりがちです。
例えば、加算を継続取得している法人は、賞与額が業界平均より5〜10万円高い傾向があります。
転職や就職活動では、加算の取得状況とその配分方針を必ず確認することが、長期的な収入アップにつながります。
介護職のボーナスをアップさせる方法【実践編】

介護関連資格を取得する(介護福祉士・ケアマネ)
資格を取得すると評価基準が上がり、ボーナス額にも直接反映されます。介護福祉士やケアマネジャーは資格手当がつき、昇進の可能性も高まります。
資格取得によって職務の幅が広がり、責任ある業務を任されることで評価点が上昇します。
例えば、初任者研修から介護福祉士にステップアップした職員が、翌年の賞与で年間7万円増加した事例があります。
将来の収入安定を考えるなら、資格取得は最も費用対効果の高い自己投資です。
リーダー・主任・管理者など役職に就く
役職に就くと基本給が上がり、賞与計算のベース額も増加します。加えて役職手当や管理職評価が賞与に反映されるため、年間で数十万円単位の差になることもあります。
役職登用は勤務態度、リーダーシップ、資格、勤続年数など総合的な評価によって決まります。
例えば、特養のユニットリーダーに昇格した職員が、年間賞与額を約15万円増やした事例があります。
昇進のチャンスがある職場では、積極的に研修や資格取得に取り組みましょう。
経営者や上司に賞与額アップを相談する
自分の業務成果や資格取得、勤続年数を根拠にして賞与額の改善を相談することも有効です。
交渉は勤務評価が高いタイミングや人事考課の前に行うのが効果的です。
例えば、業務改善提案でコスト削減に貢献した職員が、その功績を評価され賞与額を5万円増額されたケースがあります。
自己アピールとタイミング次第で、賞与額は自らの行動で引き上げられます。
ボーナスの高い職場に転職する
賞与額は施設の運営母体や財務状況に大きく依存します。高賞与が期待できる職場に転職することは、短期間で収入を大きく伸ばす方法です。
特に大規模法人、公立施設、医療法人附属の老健などは、安定した財源で賞与額も高めです。
例えば、民間有料老人ホームから特養へ転職した職員が、年間賞与額を約20万円増やした事例があります。
求人選びの際は「過去3年間の賞与実績」を必ず確認しましょう。
※ おすすめの転職サイトはこちら>>>医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】
転職時にボーナス条件を見極めるポイント

求人票の「賞与欄」の正しい読み方
求人票には「賞与あり(年2回 計〇か月分)」と記載されることが多いですが、この数字はあくまで過去実績や規定額であり、確約ではありません。
実績値か固定額かを見極めることで、入職後のギャップを防げます。
例えば、「計4か月分」と記載があっても、業績連動型であれば実際は3か月分に減額されることがあります。
必ず「前年実績かどうか」を確認することが重要です。
固定賞与と業績連動賞与の違い
固定賞与は業績に関係なく規定額が支給されるため安定していますが、業績連動賞与は景気や稼働率によって変動します。
安定重視なら固定賞与型、成果重視なら業績連動型を選ぶと良いでしょう。
例えば、公立系特養は固定賞与型が多く、民間の有料老人ホームは業績連動型が多い傾向です。
自分のライフプランに合わせた賞与形態を選ぶことで、将来の収入計画が立てやすくなります。
面接でボーナスの実績を確認する方法
面接時には「昨年度の賞与支給実績」「平均支給額」「支給回数」を具体的に質問します。
施設によっては賞与額が職種や役職で大きく異なるため、同職種での実績を確認することが大切です。
例えば、「介護福祉士で入職3年目の平均賞与額はいくらですか?」と具体的に聞けば、現実的な数字が得られます。
明確な回答が得られない場合は、条件面で慎重な判断が必要です。
高賞与が期待できる施設形態・運営母体
高賞与を期待するなら、財務基盤の強い運営母体や公的施設を選びましょう。
特養、老健、自治体直営施設、医療法人附属施設などは、年間4か月分以上の賞与を支給する例が多くあります。
例えば、医療法人附属老健は賞与4.5か月分+期末賞与を支給するケースがあり、年間100万円以上になることもあります。
施設形態と運営母体を見極めることは、転職成功の大きなカギとなります。
介護職の年収をトータルで考える重要性

賞与だけでなく月給・手当・福利厚生を含めた年収比較
年収は「賞与+月給+各種手当+福利厚生」の総合額で判断することが大切です。賞与額だけに注目すると、本来の収入水準を正確に把握できません。
なぜなら、夜勤手当や処遇改善手当、住宅手当などが充実していれば、賞与が平均より少なくても総収入は高くなる場合があるからです。
例えば、A施設は年間賞与が45万円と少なめでも、夜勤手当や資格手当を含めた年収は380万円。一方、B施設は賞与55万円でも手当が少なく年収350万円というケースがあります。
収入比較は「総支給額」で行うことが、転職や職場選びの失敗を防ぐポイントです。


ボーナスが少なくても年収が高いケース
ボーナスが少なくても、基本給や諸手当が高い場合は年収が上がります。特に固定残業代や夜勤手当、資格手当が厚い職場ではこの傾向が顕著です。
たとえば、賞与が年間40万円でも、夜勤月8回+資格手当+処遇改善手当で月収が30万円を超えると、年収は400万円を超えることがあります。
また、福利厚生として家賃補助や食事補助がある場合、実質的な可処分所得が増えるため生活水準は下がりません。
賞与の金額だけで職場を評価せず、総合的な待遇で判断することが重要です。
年収アップに直結する転職戦略
年収を上げるには、賞与の高い施設に転職するだけでなく、手当や基本給の水準も高い職場を選ぶ必要があります。
そのためには「求人票の総支給額」「過去3年の賞与実績」「夜勤回数」「加算取得状況」を必ず確認しましょう。
例えば、年間賞与80万円+手当充実の老健に転職したことで、年収が80万円以上増えた事例があります。
転職活動では「高賞与+高手当」の両立を目指すことが、最も効率的な収入アップの方法です。
よくある質問(FAQ)

Q1. 介護職1年目でもボーナスはもらえる?
もらえる場合が多いですが、在籍期間によって満額支給ではないことがあります。採用時期が夏の支給月より後の場合は冬季のみ、または寸志程度の支給になることが一般的です。
例えば、4月入職なら夏・冬ともに支給対象になることが多いですが、10月入職では冬賞与が半額、夏は翌年度からという規定の例もあります。
入職前に「初年度賞与の支給条件」を必ず確認しましょう。
Q2. パートやアルバイトでも賞与は出る?
出る場合もありますが、全体の4割程度にとどまります。支給額は勤務日数や時間に応じて計算され、正社員よりも少額です。
週5日フルタイム勤務のパートでは年間10〜15万円支給された例もありますが、週2〜3日の勤務では寸志程度となることが多いです。
求人票や契約書で支給条件と過去の実績額を確認することが重要です。
Q3. 賞与支給月に退職してももらえる?
在籍要件を満たしていれば支給される場合がありますが、多くの施設では「支給日に在籍していること」が条件です。
例えば、6月末に退職予定で賞与支給日が7月10日なら、受け取れないケースがほとんどです。
退職時期を調整できるなら、支給日以降に設定する方が有利です。
Q4. 賞与なしの職場は避けるべき?
一概に避けるべきとは言えませんが、年収や手当の総額で納得できるかが判断基準になります。
賞与がない代わりに月給や手当が高く、年収水準が高い職場もあります。
ただし、賞与制度がない職場は昇給も限定的な傾向があるため、長期的な収入安定性は慎重に検討すべきです。
Q5. ボーナスアップのために何から始めればいい?
最も効果的なのは「資格取得」です。介護福祉士やケアマネジャーは資格手当や評価加点の対象となり、賞与額が上がりやすくなります。
次に、夜勤回数を増やす、役職を目指す、処遇改善加算の高い施設へ転職するなどの方法があります。
小さなステップでも積み重ねることで、1〜2年後には年間賞与額が大きく変わります。
まとめ|介護職のボーナス事情を理解し、賢くキャリアを築こう

平均相場を知り、キャリアプランに反映
介護職の年間賞与は平均50万円台ですが、年齢・勤続年数・職種・施設形態によって差があります。自分の立ち位置と目指す収入額を把握することは、キャリア形成の出発点です。
相場を知れば、現在の待遇が適正か、将来的にどの程度の賞与を見込めるのかを判断できます。
例えば、40代で管理職に就けば賞与が年間100万円を超える事例もあります。
正しいデータをもとに、5年後・10年後のキャリアと収入プランを設計しましょう。
処遇改善加算や資格取得でアップ可能
賞与額を増やすには、処遇改善加算を活用している施設で働くことと、介護福祉士やケアマネジャーなどの資格取得が効果的です。
処遇改善加算を取得している施設は、賞与額が平均より5〜10万円高い傾向があります。資格取得は評価加点や役職登用にもつながります。
例えば、初任者研修修了者が介護福祉士にステップアップし、翌年の賞与額が7万円増加した事例があります。
長期的な収入安定を目指すなら、この2つの取り組みは外せません。
求人選びでは年収トータルで判断
賞与額だけでなく、月給・手当・福利厚生を含めた総年収で職場を評価することが重要です。
ボーナスが少なくても、手当や基本給が高ければ年収は十分に確保できます。
例えば、賞与45万円でも夜勤手当や処遇改善手当が手厚く、年収380万円を超えるケースがあります。
求人票の賞与欄だけに惑わされず、総収入とライフスタイルに合った職場を選ぶことが、介護職として賢くキャリアを築く秘訣です。

コメント