介護士として働く上で、「休みは取りやすいのか?」「土日や連休はあるのか?」という疑問は、多くの現役介護職員やこれから介護業界を目指す方に共通する関心事です。
本記事では、介護職の年間休日数・有給取得率・連休の取りやすさについて、法律の基準や業界平均、施設形態・雇用形態ごとの違いまで徹底解説します。さらに、休みやすい職場を見極める方法や、希望休・連休を確保するための実践的な方法も紹介します。
「介護士の休日事情のリアル」を知ることで、転職や職場選び、働き方の改善に役立ててください。
介護士の休みの実態とは?

介護士の年間休日数の平均と全国平均との比較
介護士の年間休日数は、厚生労働省の調査によると平均111日程度(※1)で、全国の全業種平均(約116日)(※2)よりやや少ない傾向があります。
これは、介護現場のシフト制勤務や人員配置の制約が影響しており、カレンダー通りの休みが難しい職場も多いためです。特に入所型施設では、24時間体制の勤務が求められるため、年間休日数が業界平均よりも少なくなりがちです。
例えば、ある特別養護老人ホームでは年間休日が108日と設定されており、職員は月9日程度の休みをシフトで回しています。一方、他法人の特別養護老人ホームでは、年間休日120日以上を確保しているケースもあります。
年間休日数は職場選びの重要な基準のひとつであり、求人票で必ず確認しておくべきポイントです。
※1【参考資料】 厚生労働省 平成30年就労条件総合調査
※2【参考資料】 厚生労働省 令和6年就労条件総合調査
月間休日数の目安
介護士の月間休日数は、シフトや勤務形態によって異なりますが、一般的には8〜10日程度が目安です。
この数字は労働基準法で定められた週1日以上の休日を満たす水準ですが、実際には夜勤明けが休日としてカウントされる職場もあり、体感的な休養感が薄れるケースもあります。
例えば、夜勤明けと翌日の公休を合わせて「2連休」として扱う施設もあり、表面的には休日日数が多く見えても実質的な休養が不足する場合があります。
月間休日の実態を理解し、自分の生活リズムや体力に合った働き方を選ぶことが長期的なキャリア維持に繋がります。
土日休みは可能か?
介護士は土日休みが取りにくい職種といわれますが、勤務先によっては可能です。
入所型施設では24時間365日利用者が生活しているため、土日勤務はほぼ避けられませんが、通所型施設や企業内介護サービスでは土日休みの職場もあります。
例えば、デイサービスでは多くの事業所が日曜定休、土曜は交代勤務または半日営業という形態を取っています。訪問介護でも土日休みの事業所は少なくありません。
土日休みを重視する場合は、面接時や求人票で「土日休み可」「完全週休二日制(土日)」などの記載を確認しましょう。
連休の取りやすさと現場の課題
介護士が3日以上の連休を取るのは難しいとされますが、全く不可能ではありません。
連休取得を阻む要因は、人手不足やシフトの調整困難さであり、特に繁忙期や人員が限られる小規模施設では取りにくい傾向があります。
しかし、職員数に余裕がある施設や有給の計画取得制度を導入している法人では、旅行や帰省のための連休を確保できる事例も増えています。
連休の取りやすさは職場文化と人員体制に大きく左右されるため、入職前に「過去1年での連休取得実績」を確認すると安心です。
介護職の有給休暇事情を徹底解説

そもそも有給休暇とは?(労働基準法の基礎)
有給休暇とは、労働基準法で定められた給与が支払われる休日のことです。
法律では、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日以上の有給休暇を付与する義務があります。
例えば、週5日勤務の正社員であれば、初年度に10日、勤続年数に応じて最大20日まで増加します。
介護士ももちろん対象であり、雇用形態に関わらず適用される制度です。
有給休暇の付与条件と取得義務
介護士が有給休暇を取得するには、雇入れから6ヶ月以上の勤務と8割以上の出勤率が必要です。
また、2019年4月の法改正により、年間5日以上の有給取得が義務化され、事業主が取得日を指定することも可能になりました。
例えば、ある介護施設では、年度の初めに職員と面談し、有給取得計画を立てて計画的に消化しています。
この制度を理解していれば、計画的な休暇取得や連休確保がしやすくなります。
介護士の有給休暇取得率と他業界との比較
介護士の有給休暇取得率は、介護労働安定センターの「介護労働実態調査」(※3)によると約53.7%で、全産業平均(約65.3%)より低い傾向があります。
理由として、人員不足やシフト制による調整の難しさが挙げられます。特に入所型施設では代替人員の確保が困難なため、休暇申請がしづらい環境になりがちです。
ただし、運営法人によっては、比較的取得率が高く70%を超えるケースもあり、企業努力によって差が出ています。
有給取得率の高さは、働きやすさや職員定着率にも直結する重要な指標です。
※3【参考資料】介護労働安定センター 令和5年度介護労働実態調査
有給休暇を取りにくい理由と改善事例
介護士が有給を取りにくい背景には、人手不足・シフト制・業務引き継ぎの困難さがあります。
しかし、近年では有給取得促進のため、法人全体で取得推進キャンペーンを実施する施設や、シフト作成時に有給消化日を事前に組み込む制度を導入する事例も増えています。
例えば、ある社会福祉法人では「年間有給取得目標日数」を全職員に配布し、達成状況を可視化した結果、取得率が20%改善しました。
環境改善が進む職場ほど、有給休暇は取りやすくなります。
円滑に有給を取得するためのポイント
介護士が有給をスムーズに取得するためには、早めの申請・同僚との協力・業務の事前調整が鍵です。
特に繁忙期やイベント時期を避けた申請や、引き継ぎ資料の作成は、休暇承認を得やすくする有効な手段です。
例えば、夜勤明けと組み合わせて有給を取得すれば、実質的に3連休以上を確保することも可能です。
計画性と職場内の信頼関係が、有給取得の実現度を大きく左右します。
法律で定められた休日数と休憩時間

週1日以上の「法定休日」のルール
介護士も含め、全ての労働者には週1日以上、または4週間で4日以上の休日を与えることが労働基準法で義務付けられています。
この規定は、長時間労働による健康被害を防ぐために設けられており、シフト制の介護現場でも守らなければなりません。
例えば、週5日勤務の介護士であれば、少なくとも週1日の完全な休みが必要で、これを守らない場合は労働基準法違反となります。
法定休日は職場選びや労働条件の確認時に、必ずチェックすべき重要項目です。
夜勤明けは法定休日にならない理由
夜勤明けの日は、法律上の休日としてはカウントされません。
その理由は、夜勤明けは前日の勤務時間に含まれるため、労働時間が終わった日=休日ではないからです。
例えば、16時間夜勤(17時〜翌9時)の勤務後に丸一日休みがあったとしても、それは「勤務終了後の休養時間」に過ぎず、法定休日とは別枠で確保する必要があります。
夜勤明けを休日として扱う職場は、実質的に休日数が少なくなるため、求人票の休日数を確認する際に注意が必要です。
労働時間に応じた休憩時間の基準
労働基準法では、労働時間に応じて以下の休憩時間を与えることが定められています。
・6時間を超える勤務…45分以上
・8時間を超える勤務…60分以上
これは介護職員にも当然適用され、日勤・夜勤いずれの場合も休憩時間を確保する必要があります。
例えば、日勤で8時間勤務の場合、最低でも60分の休憩が必要であり、分割して取ることも可能です。
十分な休憩は体力回復だけでなく、利用者への安全なケア提供にも直結します。
休憩時間中の記録や見守り業務は違法?
休憩時間は業務から完全に解放されていることが条件であり、記録作業や見守り業務を行っている場合は休憩とは認められません。
介護現場では、休憩中もナースコール対応や巡回を求められることがありますが、これは実質的な労働となり、法律違反の可能性があります。
例えば、休憩室にいても「呼ばれたら対応する」という状態は、休憩ではなく待機業務と見なされます。
適切な休憩を取れる職場環境は、働きやすさの大きな指標となります。
施設形態別|介護士の休日事情

入居型施設(特養・老健など)の勤務体制と休日
入居型施設では365日24時間体制で介護サービスを提供しているため、土日や祝日も勤務が必要です。
シフト制が基本で、年間休日数は110日前後が多く、夜勤を含む交替勤務となります。
例えば、特別養護老人ホームでは、日勤・早番・遅番・夜勤を組み合わせて勤務し、休日は平日になることがほとんどです。
安定した休日が欲しい場合は、年間休日数やシフトパターンを事前に確認することが重要です。
通所型施設(デイサービス等)の休日と特徴
通所型施設では、日曜定休や祝日休みのところが多く、年間休日数が多めになる傾向があります。
運営時間が日中のみのため、夜勤がなく、土日休みが可能な職場も珍しくありません。
例えば、デイサービスであれば、日曜日と他の曜日を組み合わせた完全週休二日制を導入している事業所もあります。
家庭やプライベートの予定に合わせやすいことが、通所型の大きなメリットです。
訪問介護の休日とスケジュールの柔軟性
訪問介護は、利用者の生活スタイルに合わせた柔軟なシフトが特徴で、比較的休みを調整しやすい業態です。
土日休みの事業所も存在し、パート勤務や曜日固定勤務も可能な場合があります。
例えば、週3日勤務のパート訪問介護員であれば、子育てや副業と両立しながら働くことが可能です。
柔軟な働き方を求める場合は、訪問介護事業所の勤務形態が選択肢となります。
雇用形態別|介護士の休日と働き方

正社員の休日とシフトの特徴
正社員介護士は、シフト制で月8〜10日の休日が一般的です。
責任ある立場や固定シフトの組み合わせにより、希望通りの休みが取りづらい場合がありますが、福利厚生や有給休暇の付与日数は安定しています。
例えば、特養勤務の正社員では、年間休日110日程度で夜勤や早遅番を含む変則勤務が多く、平日休みが中心です。
安定した雇用と収入を重視するなら、休日の数とシフトの柔軟性のバランスを事前に確認しておく必要があります。
契約社員の休日・連休の取りやすさ
契約社員は、契約条件で休日が比較的固定されやすい傾向があります。
契約時に勤務日数や曜日を明確にできるため、ライフスタイルに合わせた休日設定が可能です。
例えば、契約社員として週4勤務で契約し、残り3日は固定休とする事例もあります。
フルタイム勤務でも、正社員より業務責任が軽い分、連休や希望休を通しやすい環境が整いやすいです。
派遣社員の休日の自由度
派遣介護士は、勤務日・休日を比較的自由に選べることが特徴です。
派遣先や契約条件によりますが、「週3勤務・土日休み」などの働き方も可能で、家庭や副業との両立に向いています。
例えば、短期派遣であれば、自分の都合に合わせて1週間単位でシフトを調整できるケースもあります。
休みを優先した働き方を希望する場合、派遣は選択肢の一つです。
パート・アルバイトの休日の柔軟性
パート・アルバイト介護士は、勤務日数や曜日を自由に設定しやすいため、休みの柔軟性が高い働き方です。
特に家庭の都合や学業と両立する場合、午前のみや週2〜3日勤務など細かいシフト調整が可能です。
例えば、子育て中のパート介護士が、平日のみ・短時間勤務で働くケースも一般的です。
自由度を重視する場合には最も柔軟な働き方ですが、収入や福利厚生面は正社員に比べて制限があります。
介護士が休みを取りやすい職場の条件

年間休日数が多い施設の特徴
年間休日が多い施設は、シフトに余裕を持たせ、職員の働きやすさを重視している傾向があります。
年間休日115日以上を設定する法人は、職員の定着率も高く、有給取得率が業界平均より高い場合が多いです。
例えば、デイサービスや企業内介護施設など、土日休み+祝日休の形態は、年間休日が120日を超えることもあります。
求人票や就業規則で年間休日数を必ずチェックすることが大切です。
人員配置に余裕があるか
休みを取りやすい職場は、職員数が十分に確保されていることが大前提です。
人員不足の職場では、希望休や連休の取得が難しく、休みを取ると他の職員の負担が増える悪循環が起こります。
例えば、厚労省基準を上回る人員配置を行っている法人では、代替勤務がスムーズに行え、有給消化率も高くなります。
面接時に職員数や人員配置基準を確認することで、休暇取得のしやすさを見極められます。
※ 人手不足の原因と背景について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-gensyou-haikei/
希望休制度や計画的有給取得制度の有無
希望休制度や計画的有給取得制度は、休暇の計画的取得を可能にし、連休も作りやすくする仕組みです。
この制度がある職場では、旅行や家族行事など、先々の予定を立てやすくなります。
例えば、年初に年間の希望休を提出し、シフト作成時に反映する施設では、連休取得率が高くなります。
制度の有無は求人票や面接で必ず確認しておきたいポイントです。
休暇中の業務サポート体制が整っているか
休暇を取りやすい職場は、不在時の業務をカバーする体制が整っているのが特徴です。
代替スタッフやヘルプ要員が配置されていれば、休暇中も安心して休むことができます。
例えば、他部署からの応援体制や派遣スタッフの活用によって、長期休暇取得が可能になった事例もあります。
こうした体制がある職場は、休みやすさだけでなく、働きやすさ全体が向上します。
希望休・連休を確保するための実践方法
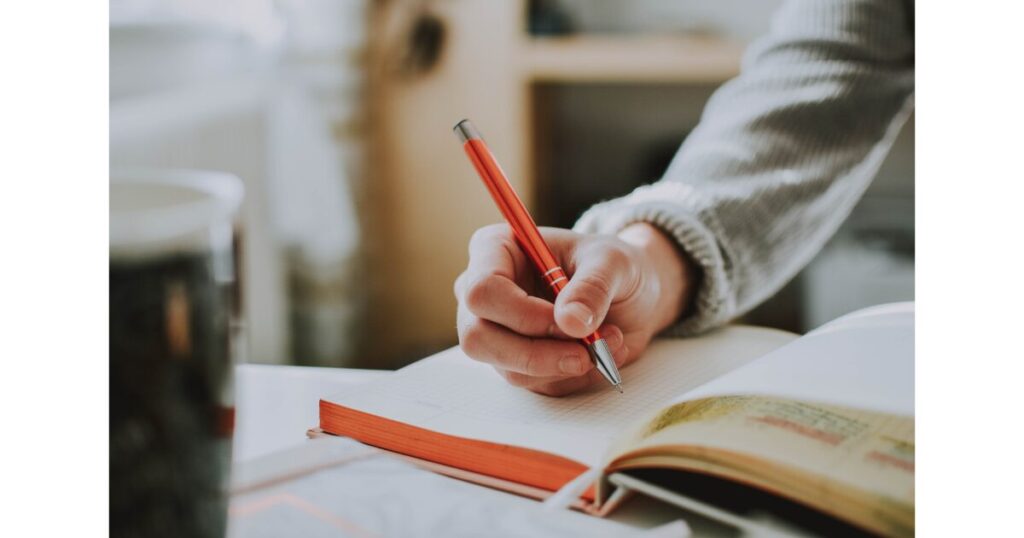
希望休を事前に申請するタイミング
希望休は早めに申請するほど通りやすくなります。
介護現場はシフト制のため、締切直前の申請では他職員との調整が難しくなるからです。
例えば、シフト作成が毎月20日頃に行われる職場であれば、その2週間前までに希望日を提出することで、反映される可能性が高まります。
先を見越した申請は、連休取得や家族行事の参加を確実にします。
夜勤明けを活用して連休を作る方法
夜勤明けは翌日の公休と組み合わせることで実質連休になります。
法律上は休日ではありませんが、体感的な休養時間は大幅に確保できます。
例えば、金曜夜勤明け+土曜公休+日曜公休で、実質的に3連休を作ることが可能です。
計画的に夜勤明けと公休を組み合わせることで、旅行や帰省の時間を捻出できます。
※ 夜勤手当の相場について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-yakinteate-souba/
同僚とのシフト調整テクニック
連休や希望休を取りたい場合、同僚との協力関係が重要です。
日頃から情報共有や業務サポートを行っていると、代わりに勤務してもらいやすくなります。
例えば、「来月この日を代わってもらえれば、翌月はこちらが代わります」という形での持ちつ持たれつの調整は、現場でよく使われる方法です。
信頼関係を築くことが、希望休実現の近道です。
派遣やパートとして柔軟に働く選択肢
希望通りの休みが取れない場合、雇用形態の見直しも選択肢です。
派遣やパート勤務であれば、出勤日や時間を自分で選べるケースが多く、家庭やプライベートの予定に合わせられます。
例えば、週3日・曜日固定の派遣契約なら、残りの4日間を完全にプライベートに充てられます。
自由度を優先した働き方にシフトすることで、休みを確実に確保できます。
※ 派遣のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-staff-hakenjijou/
休めないときの対処法と転職の視点

有給が取れない場合の改善提案の出し方
有給が取りにくい場合は、建設的な改善提案を行うことが大切です。
感情的な訴えではなく、業務負担や人員配置の課題を具体的に示すことで、上司や管理者の理解を得やすくなります。
例えば、「この時期は利用者数が少ないため、この期間に有給を集中取得すれば業務影響が少ない」という提案は受け入れられやすいです。
データと理由を添えることで、職場全体の有給取得率向上にも繋がります。
職場環境改善のための正式な相談手順
休暇取得の改善は、正式な相談ルートを通すことが効果的です。
まず直属の上司に相談し、それでも改善が見られない場合は労働組合や法人本部、人事部に申し出ます。
例えば、相談内容を記録として残すことで、法人側も対応の必要性を認識しやすくなります。
段階的な相談は、円満な解決と職場改善のきっかけになります。
休みやすい職場への転職チェックポイント
どうしても休暇が確保できない場合は、休みやすい職場への転職を検討します。
求人票の年間休日数や有給取得率、土日休みの有無はもちろん、面接での質問や現場見学での確認が重要です。
例えば、「職員の有給取得率」「過去1年間の連休取得実績」などを直接質問することで、働きやすさを数値で判断できます。
転職活動時の情報収集は、将来の働きやすさを大きく左右します。
※ おすすめの転職サイトはこちら>>>転職先をお探しの介護士さんに!【レバウェル介護】
Q&A|介護士の休日に関するよくある疑問

Q1. 介護士の平均年間休日は何日?
介護士の平均年間休日は約111日で、全業種平均(約116日)よりやや少ない傾向があります。
シフト制勤務や夜勤明けの扱いによって、実感としての休みはさらに少なく感じられることもあります。
例えば、特養では年間休日108日〜110日程度のケースが多い一方、運営法人によっては120日を超えることもあります。
年間休日数は求人選びの大きな判断材料になるため、必ず確認しましょう。
Q2. 介護職は旅行に行ける?
介護職でも計画的に休みを取れば旅行は可能です。
人員体制や希望休制度が整った職場では、3日以上の連休を確保できることもあります。
例えば、夜勤明け+公休+有給を組み合わせれば、4日間の旅行も実現可能です。
勤務先の休暇制度を活用すれば、プライベートの充実も十分可能です。
Q3. 夏休みや冬期休暇はある?
介護職にも夏季休暇や年末年始休暇がある場合がありますが、施設の種類によって異なります。
入所型施設では、休暇期間中もシフト勤務となり、交代で取得するのが一般的です。
例えば、特養ではお盆や年末年始に3日程度の特別休暇を設定している場合もあります。
求人票や就業規則で休暇制度を確認し、自分の予定に合わせやすいか見極めましょう。
Q4. 他業種と比べて休みは少ない?
介護職は全業種平均よりやや休みが少ないのが現状です。
その理由は、24時間365日体制の施設が多く、土日祝日も稼働しているためです。
例えば、一般企業では完全週休二日制(土日)で年間休日120日以上が標準ですが、介護職では110日前後が一般的です。
ただし、通所型や訪問介護では他業種並みの休日を確保できる職場もあります。
まとめ|介護士も「しっかり休む」ことが働き続ける力になる

働きやすい環境を選ぶ重要性
介護士が長く働くためには、休日制度や有給取得のしやすさが整った環境が欠かせません。
休みが取れない職場は、心身の負担が蓄積し、離職率の上昇にもつながります。
例えば、有給取得率が高く、年間休日が多い職場ほど職員定着率も高い傾向があります。
職場選びの段階で「休みやすさ」を重視することが、キャリアの安定につながります。
年間休日・有給・連休を職場選びの基準に
介護職の求人を見る際は、年間休日数・有給取得率・連休取得実績を必ず確認しましょう。
これらの情報は、働きやすさやプライベートとの両立可能性を判断する重要な指標です。
例えば、年間休日120日+計画的有給制度を持つ職場は、プライベート時間を確保しやすく、モチベーション維持にもつながります。
条件を数値で比較し、自分に合った環境を選ぶことが大切です。
休みやすい職場で長く活躍するための心構え
休みやすい職場で働くには、自分自身も職場にとって信頼できる存在であることが重要です。
日頃から業務に誠実に取り組み、同僚との協力体制を築くことで、希望休や連休も通りやすくなります。
例えば、普段から代勤務を引き受けている人は、希望休申請時にも快く応じてもらえることが多いです。
お互いに助け合える関係を築くことが、働きやすい環境を長く維持する秘訣です。
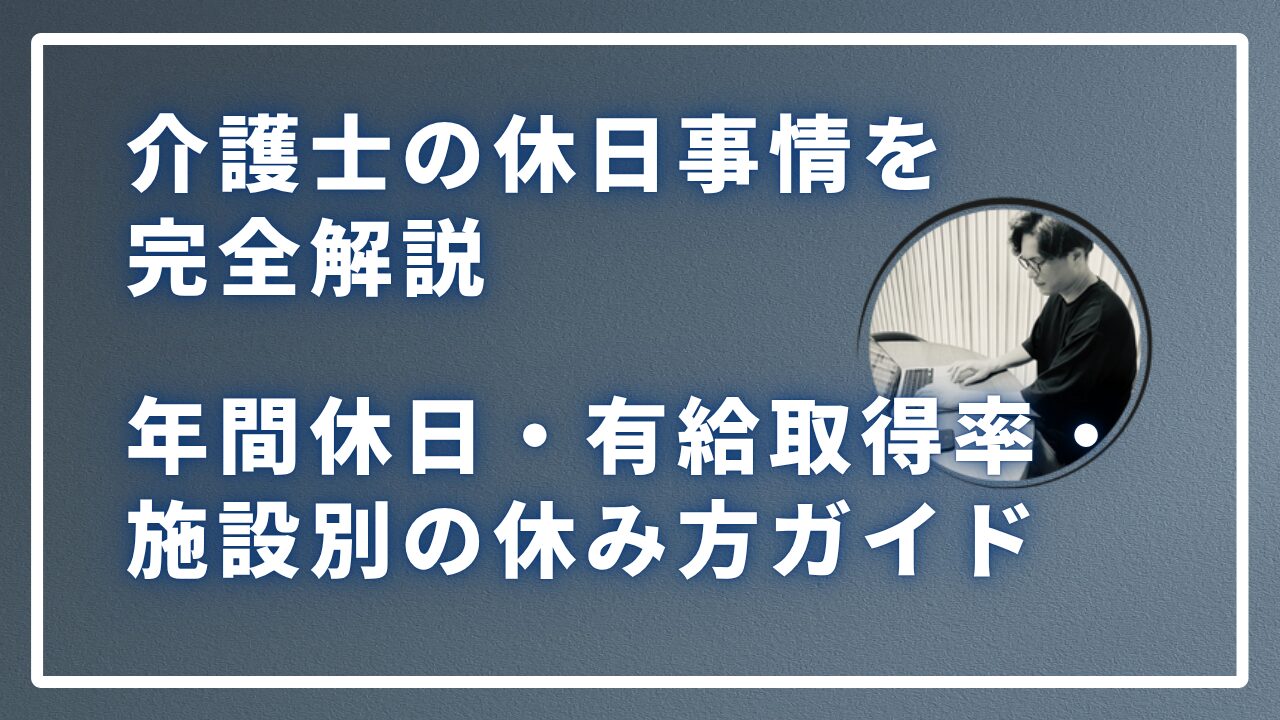
コメント