ユニット型介護施設では設えを整えることが重要とされています。
本記事では、その人らしい暮らしを実現するためのハード(環境)×ソフト(暮らしのサポート)×システム(運営)を網羅し、現場で即使えるチェックリスト・配置テンプレ・低予算アイデアまで一気通貫で解説します。
空間デザインのコツ、家具・家電の選び方、従来型との比較、照明や色調に至まで、参考にしていただけると幸いです。
ユニットケアの基本と「設え」の考え方

ユニットケアとは?
ユニットケアは、少人数単位で「暮らしの継続」を再現し、自律・選択・関係性・役割の再獲得を促すケアの方式です。設え(しつらえ)を整えることは、この理念を“日常の行為”に落とし込む最短ルートになります。
プライバシーが守られ、選べる居どころがあり、自分のペースで過ごせる環境は、生活リズムの安定や不安軽減、コミュニケーションの質向上を呼び込みます。逆に、空間が“病院的”で画一的だと、ケアの個別化は形骸化しやすくなります。
たとえば、写真や愛用品を置ける「自分の居場所」を居室とリビング双方に設け、朝は窓辺の椅子、午後はダイニングの定位置、夕方は和室でひと息…と時間帯で居どころを使い分けられる設えにすると、自然と会話の機会や役割行動(配膳・片付け等)が増えてきます。
ユニットケアの核心は“暮らしの選択肢”を空間で支えること。設えはケアの抽象を具体に変えるツールであり、まずは「暮らしの継続」を体感できる小さな改善から着手するのが近道です。
ユニットケアの3要素(ハード・ソフト・システム)
ユニットケアの成果は、ハード(環境)×ソフト(暮らしのサポート)×システム(運営)の三位一体で最大化します。どれか一つでも欠けると、良い設えも“飾り”に終わってしまいます。
理由は明快で、環境は行動を誘発し、支援は行動を持続させ、運営は行動を標準化してチームの再現性を高めるからです。家具・照明・音・温熱が整い、食や活動の支援が回り、さらにルール・記録・評価が回る時、ユニットは“家庭らしい日常”を安定供給できます。
ハードは回遊導線と匂い・音の演出、ソフトは選べる量・時間・役割づくり、システムは配膳手順・見守り配置・記録様式。これらを噛み合わせると、滞在時間の延伸・会話増・食事量の安定が起きます。
結論として、ユニットケアを強くする鍵はこれら三要素の組み合わせ。設えの変更は、支援の運びと運営の型まで同時に設計してはじめて力を発揮します。
ユニットケアの魅力~「その人らしい暮らし」を大切に~
ユニットケアの魅力は、その人らしい生活リズムと居場所が保障され、関係性が自然に育つことに尽きます。
人は自分で選べると落ち着き、馴染んだ物や匂いは記憶と感情を呼び戻します。静と動の居どころが複線化されていれば、気分や体調に合わせて移動でき、他者との距離も調整しやすくなります。
たとえば、窓辺の読書コーナーや季節の設えを整えるだけで、自発的な移動・会話が増えます。結果、BPSDの緩和や日中覚醒の安定などの波及も起きやすくなります。
だからこそ、ユニットケアは「人」を見て「場」を整えます。設えは“その人らしさ”を守る最小単位であり、日々の微調整が刺激を与え、新たな価値を生み出します。
従来型との違いと位置づけ
ユニット型は、プライバシーの確保、個別ケア、コミュニティの形成が特徴で、従来型と目指す景色が異なります。従来型は集団ケアの効率性が強みだが、個別性と選択の自由は制限されやすくなります。
ユニット型は少人数で関係密度が上がり、観察・声かけ・役割づくりが細やかになる一方、運営の標準化と教育が不可欠になります。
例として、食堂を“通過点”から“居場所”へ転換し、見守り視線を通しつつ居心地を高めると、ナースコールの偏在や転倒リスクが下がることがあります。
結論として、両者は優劣でなく設計思想が異なります。ユニットケアは個別性の獲得に強みを持ち、設えの質がケアの質を牽引する点を理解することが重要です。
ユニット運営の課題について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unit-care-transfer/
設えの原則(ハード編:環境づくり)

ゾーニング設計:パブリック/セミパブリック/プライベート
ユニットの設えは、パブリック・セミパブリック・プライベートの三層ゾーニングで考えると迷いが消えます。
心理的安全と行動の予測可能性が高まり、移動・参加・休息の切り替えがスムーズになるからです。境界は“固く仕切る”より“あいまいに示す”ほうが、家庭らしい流動性を保てます。
たとえば、玄関〜廊下はパブリック、リビング・食堂はセミパブリック、居室はプライベートとし、腰高家具・ラグ・照度差・素材差で境界を“やわらかく”演出します。結果、迷走の減少・滞在の偏りの改善が起きやすくなります。
要は、居どころの“段階”を設計することが個別ケアの土台となります。視覚・触覚・音環境を使って、多様な居心地を用意しよう。
ユニット玄関と導線
玄関は“帰って来られる場所”に仕立てます。シンボルとサインで“戻りやすさ”を高め、回遊できる導線は渋滞と不安を減らすことができます。
最初の視覚情報が安心感の土台になるため、色・素材・照明・匂いを“家庭的”に統一し、サインは文字だけでなく形・アイコン・写真を用いることで感覚情報が脳内で結び付きます。
例として、季節のリースと家族写真の掲示、ユニット名のサイン、食の香りが漏れる位置関係を意識すると、方向づけと帰巣行動が起きやすくなります。
まとめると、玄関は迷いを減らすコンパスです。シンボルマーク+回遊性で設計すると良いでしょう。
居室の基本:広さ・形状・設備
居室は安心して休む・整える・招くの三機能を満たします。理由は、休息・身支度・交流が住まいの核だからです。
照明・収納・コール機器・コンセントは“使う順”に配置し、持ち込み家具は馴染みのものを最優先に選びましょう。
例として、ベッド片側に介助スペースを確保し、ナースコールは寝姿勢でも手が届く高さに。クローゼットは見える収納(扉を半透明・オープン棚)にして選択を助け、スタンドライトで就寝前は色温度を落とす。
写真・趣味の品を視線の止まる位置へ。結論、居室は“その人の思い出”を置けるプライベート空間にしましょう。
リビング・和室・食堂の設え
共有空間は団らん・活動・静養の三態を併存させ、「食」を中心に回遊導線を組みましょう。
食は参加・会話・役割を最も引き出す生活行為です。席は固定化し過ぎず“安心の定位置+試せる席”の二層を用意すると良いでしょう。
例として、カフェ型(小テーブル分散)/島型(中テーブル+周回動線)/円卓型(中心に食)の三案を使い分け、照度差でエリアを示します。和室は低座・低照度・柔素材で落ち着きを演出し、静養の逃げ場にすることもできます。
結論、リビングは滞在を伸ばす場所。見守り視線が通り、居心地の選択肢が多いほど、関わりは増えていきます。
浴室・特殊浴槽の快適性と尊厳
浴室は短い導線・十分な温熱・高いプライバシー保護で整えます。
湯前後の体温変化や羞恥心は転倒・拒否の引き金となります。ヒートショック回避の温熱管理、滑り対策、身体を隠しながら介助できる視線遮蔽が不可欠です。
例として、前室を暖めてから誘導し、床は水切れの良いノンスリップ、タオルポンチョやのれん型パーティションで露出を最小化しましょう。特殊浴槽は声かけ→手順の見える化→終わりの合図を徹底します。
結論、入浴は身体ケアと尊厳の最高難度の交点。設えと手順の両輪で「気持ちよさ」を設計しましょう。
光・音・温度・匂いの環境調整
五感環境は“効く微調整”を積み上げます。
眩しさや残響は疲労を生み、寒暑・匂いは不快と焦燥を増幅します。照度の層(ベース+タスク+アクセント)、吸音・遮音、温湿度の安定、匂いの発生源管理が基本です。
例として、日中はベース200–300lx、作業300–500lx目安、夕方は色温度を落として緊張を和らげます。吸音パネルやカーテンで残響を抑え、空調は24±2℃・湿度40–60%程度の安定を狙う。匂いは芳香で覆うのではなく、排泄物動線の短縮・換気・素材の清掃性で元から断つことが重要です。
結局、環境は“音・光・熱・匂い”の目に見えない設え。数値の目安を持って運用点検まで回すと、ユニットケアの安定感が一段上がります。
※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/
設えの原則(ソフト編:暮らしのサポート)

普段と変わらない暮らしを叶える「食」のしつらえ
ユニットの“日常感”は食の場づくりで最も早く回復できます。匂い・音・手触りを伴うしつらえは、食欲と会話、役割参加を自然に引き出すことができます。
食は五感への刺激が強く、出来立ての香りや食器の触感、調理音が「家の台所」を想起させます。さらに個量個菜(量・味付け・形態の選択肢化)は、自律の手応えを与え、完食率と満足感を底上げすることができます。
具体的には、ユニット内調理の“演出”(温め直しでも良いので香りが立つ工程を見せる)、音の演出(味噌汁をよそう音、食器の触れ合う音を適度に残す)、小鍋・ミニお櫃の卓上供給で“自分で選ぶ・よそう”を可能にします。席は安心の定位置+気分転換席を用意し、小鉢トレーの色分けで選択を助けます。
結論として、食のしつらえは最小投資で最大の生活感を生み出せます。香りと音を設計し、個量個菜で“選べる”を仕込めば、ユニットの空気は一気に家庭に近づけることができます。
「自分の居場所」を設けるパーソナライゼーション
入居者に“私の居場所”を二つ以上(居室+共有部)用意すると、落ち着きと関わりが安定します。
居場所は所有感・記憶の手がかり・役割の起点となり、行動の予測可能性を高めるからです。居室だけに依存すると孤立や滞在偏りが起きやすく、共有部のパーソナル化が日中の覚醒と交流を助けます。
実例は、リビングの“マイチェア+膝掛け+名札”、窓辺の写真フレーム・小鉢による季節のしつらえ、キッチン脇の配膳・拭き上げ・水やりなどの役割コーナーなど。居室はメモリーボックス(趣味の品・家族写真)や愛用品の定位置化で「私の部屋」感を強めることができます。
結論、居室と共有部の二拠点パーソナル化が行動の自律を後押しします。まずは“物と役割がいつもそこにある”状態をつくりましょう。
認知症フレンドリー・デザインの要点
認知症のある方には、情報量を適切に絞った“わかりやすい”設えが有効です。
過剰な刺激や複雑な手がかりは誤認・不安・迷いを増やします。低刺激色(ベージュ系)を基調に、強調色で目的地や持ち手を示し、素材や柄は実物に近いものを選ぶと認知負荷が下がります。収納は見える化して「何がどこにあるか」を即時理解できるようにしましょう。
例として、トイレ扉の取っ手を強調色で縁取り、便座と床の明度差を確保します。大柄の幾何学模様や鏡面の強い反射は避け、半透明扉やピクトサインで場所の機能を示す。衣類は前面オープン棚・透過ケースで“見て選べる”にすると良いでしょう。
結論、色・コントラスト・見える収納・単純な導線が迷いを減らします。まずは「強調すべき一点」を決め、そこだけを意図的に目立たせる設計から始めましょう。
設えの原則(システム編:運営・仕組み)

標準化と例外管理:ぶれない軸を作る
ユニットの設えは“標準化の軸+例外の許容”で回すと品質が安定します。
環境・手順・記録がばらつくと、良い設えも再現性を失い、一方で個別性に必要な例外を締め付け過ぎると、暮らしの自由が損なわれます。
実務では、家具・照明・色の基準書、持ち込み規程、メンテナンス周期表を整備し、例外は“理由・期間・代替策”をセットで承認・記録します。たとえば「居室に私物の棚を追加」なら、耐震固定・動線影響のチェックリストを添付し、定期見直しの期日を入れましょう。
結論、軸は文書化、例外は透明化が鉄則。PDCAで更新し続けることで、設えの質が“チームの共通財産”になります。
安全・感染対策・BCPと設え
設えは安全・感染対策・BCP(事業継続)と一体で設計してこそ機能します。
平時の心地よさだけを追うと、有事に脆弱になります。動線分離・手指衛生導線・停電や猛暑時の代替手段を織り込み、緊急時にも“選べる暮らし”を可能な範囲で守ることが重要です。
具体的には、リネン・ゴミ動線を生活動線から分離、手指衛生ポイントを入口・ダイニング・トイレ前に配置、非常用照明・蓄電・換気手段を想定位置に設置します。可搬式の間仕切りで隔離ゾーンを即時に切り出せるようにし、掲示物は平時/緊急時の二層仕様にして切替を迅速化します。
結論、“快適+適応力”の設えがユニットの生命線です。机上演習で盲点を洗い出し、改善を反映させる運用が不可欠です。
予算設計と調達のコツ
設え改善は段階投資と調達戦略でムリなく進めることができます。
一度に大規模更新を狙うと頓挫しやすい。効果が高くコストの軽い施策から着手し、可視化された成果を財源化(減った事故・満足度向上などの実績)して次段階につなげましょう。
たとえば、0円:配置換え・掲示刷新・照明角度調整 → 〜5万円:ラグ・間接照明・収納の差し替え → 〜30万円:造作収納・可動間仕切り・手すり更新の“階段投資”を採用します。リース・レンタル・共同調達も併用し、代替品リストで欠品・高騰に備えることもできます。
結論、小さく始めて早く成果を見せ、段階的に積み上げるのが最短ルートです。調達は“複数見積+代替案+納期”でリスクを抑えましょう。
家具・インテリアの選び方&配置のコツ

机の選び方
食事や作業のしやすさは、天板形状と脚まわりで大きく向上します。角に丸みがあり、脚の抜けが良いテーブルを選ぶことが、立ち座りや介助のスムーズさにつながります。
理由は、エッジの角当たりや脚の干渉が減ることで、痛み・打撲・つまずきのリスクを下げ、清掃性も上がるためです。天板は拭き取りやすい素材(耐アルコール・耐水)で、脚間の有効幅と足元の余裕が確保できるものが望ましいです。
例として、角R加工(目安R10mm以上)・エッジ面取り、T字・4本脚でも外寄せ脚で膝前方余裕300mm程度/天板高680〜720mm目安のテーブルは、車椅子・歩行器の出入りがしやすくなります。天板はメラミン・高圧ラミネート等にすると、日々の拭き上げが短時間で済みます。
結論として、「角R」「脚の抜け」「拭ける天板」の三点を押さえますと、安全性と運用効率の両立が図れます。
チェック:角R/天板高/脚間有効幅/表面の拭き取り性/脚端のガタ・保護キャップ
椅子の選び方
座面高さ・肘掛・張地の清掃性が、立ち上がりの安定と滞在の快適さを左右します。
理由は、座面高が低すぎると立ち上がりに力が要り、高すぎると足底接地が不安定になるためです。肘掛は立ち上がり補助となり、張地は清掃の手間と衛生に直結します。
例として、座面高43〜46cm/座面奥行38〜42cm/肘掛高(座面上)20〜25cm程度を目安に、前脚が外に張り出し過ぎない安定フレームを選定します。張地は耐アルコール・防汚・取り外しカバーが実用的です。必要に応じてキャスター付き前脚+ストッパーで移乗を補助します。
結論として、「立ち上がりやすさ×拭ける材」を優先しますと、転倒予防と清掃時間の短縮に効果的です。
チェック:座面高・奥行/肘掛位置/前縁の丸み/張地の耐薬品性/脚端滑り止め
リビングの設え
リビングは過ごし方の“選択肢”を用意する空間にします。ゾーンを分け、照度を“層”で設計することで、会話・静養・作業の切り替えが自然に生まれます。
理由は、視環境のメリハリが活動の質を決めるからです。ゾーンラグで居どころを明確化し、ベース照明+タスク照明により手元の見やすさと寛ぎの両立を図ります。ダークブラウンのシーリングライトは天井面を引き締め、ウールラグは足裏感覚と保温性を高めます。
例として、カフェ型(小テーブル分散)/島型(中テーブル+周回導線)/円卓型を時間帯で使い分け、ラグの下にノンスリップシートを敷きます。タスクライトは読書席・手作業席に可動式を配置し、眩しさ対策として直接光が目に入らない向きを徹底します。
結論として、「ゾーン化×照明レイヤー×安全な下地」で滞在を伸ばし、見守りのしやすさを両立させます。
チェック:ラグのめくれ防止/通路幅の確保/タスクライトの眩しさ/座席の“定位置+気分転換席”
居室の家具・家電
居室は安全・使い勝手・“私物性”のバランスが重要です。
理由は、居室の物選びが自律行動と休息の質を左右するからです。家電は省スペース・簡単操作・自動停止の機能を優先し、家具は低重心・転倒防止・コードの取り回しを重視します。
例として、テレビは24〜32型でリモコン大ボタン、冷蔵庫は一人用45〜90L・開閉が軽いもの、加湿器は空焚き防止・手入れ簡易の製品を選びます。収納は**ローチェスト(天板≦90cm)で視線を遮らず、タンスは耐震固定を行います。差し色としてピンクの多目的スチールラックを使い、ハンカチ・眼鏡・常用薬の“見える定位置”をつくります。
結論として、「見える・手に届く・しまえる」を基準に、私物で“私の部屋”感を醸成します。
チェック:耐震固定/配線の躓き対策/リモコンの視認性/家電の自動停止機能/非常時の動線
ベッド配置とコール機器
ベッドは介助側スペースと本人の可動域を両立する配置が最も安全です。
理由は、介助の余白がないと無理姿勢・転倒が増え、コール機器が遠いと呼出の遅延・誤操作につながるためです。
例として、介助側に800mm程度のスペースを確保し、ベッドサイドの主動線は塞がないようにします。ナースコールとヘルパーコールは寝位で手が届く位置に固定し、コードはクリップ留めで引っ掛かりを防ぎます。照明スイッチ・コール・眼鏡置きはワンアクションで触れる“3点セット”にまとめます。
結論として、「介助余白×コール到達性」を最優先に、夜間も迷わない配置にします。
チェック:介助側800mm確保/コールの位置・作動確認/配線固定/夜間フットライト/ベッド高さ調整
車椅子・歩行補助具に配慮したレイアウト
レイアウトは回遊できることが最優先です。行き止まりを減らし、つかまりポイントを連続させます。
理由は、方向転換や停止が多いほど疲労とリスクが増えるためで、回遊性は迷いと渋滞を減らす効果があります。
例として、車椅子の回転直径は目安1500mm、通路幅は900〜1200mm程度を確保します。段差は6mm以下を目標にエッジを面取り・スロープで処理し、手すりは床上750〜850mmを連続配置します。ラグやマットは端部の段差・めくれを必ず点検します。
結論として、「回遊スペース×段差処理×連続手がかり」で安全な移動を実現します。
チェック:回転スペース/主通路幅/段差と敷物の端部/手すりの連続性/家具の張り出し
0円~30万円でできるビフォーアフター改善

0円改善:配置換え/掲示刷新/照明角度調整/動線の片付け
まずは費用ゼロの再配置と整頓で体感的な改善を実現します。これは、導線の渋滞・眩しさ・情報過多といった“日常の小さな不快”を断つことが、滞在時間や会話量の増加につながるためです。
具体的には、通路幅の確保(目安900mm以上)、席の役割分け(食事/作業/静養)、テレビや時計の視認性向上、照明の向き変更で眩光カット、掲示の断捨離とカテゴリ分け、配線の固定を行います。リビングは「定位置+気分転換席」の二層運用にすると滞留が偏りません。
ビフォーアフターでは、転倒リスク箇所のゼロ化、ナースコール多発席の改善、“10分日次リセット”の運用化を指標にします。
結論として、置き方と見せ方の更新だけで、ユニットの空気は確実に変わります。
~5万円改善:ラグ・間接照明・小型収納・チェア差し替え
次に少額投資で“居どころの質”を底上げします。五感への配慮と片付けやすさがそろうと、日中覚醒と会話が安定するためです。
例として、ゾーンラグ+ノンスリップで区画を示し、スタンドライト/フロアライトでベース+タスクの二層照明を作ります。小型ワゴンやローチェストで“出しっぱなし”を防ぎ、立ち上がりやすい椅子へ一部差し替えると移乗が安全になります。
評価は、リビング滞在時間・食後の残留率・片付け所要時間などを簡易KPIで見える化します。
結論として、ラグ×照明×小収納×椅子の四点セットが、費用対効果の高い黄金パターンです。
~30万円改善:造作収納/可動間仕切り/手すり・建具更新
最後に中規模の“構造に近い”改善で再現性を高めます。収納と境界の設計が整うと、混雑・騒音・視線ストレスが減り、ケア手順が安定するためです。
具体的には、造作収納で動線上の仮置きをゼロ化、キャスター付き可動間仕切りで静養/感染対策の即時切出し、手すり連続化と引戸(建具)更新で移動負担を軽減します。
実施手順は、①現状導線の可視化→②スケッチ3案→③仮配置で試行→④段階施工→⑤KPI測定(コール件数・転倒ヒヤリ・移動所要)の順が安全です。
結論として、“収納”と“境界”への投資が日々の運用コストを下げ、設えの標準化を後押しします。
個室と持ち込みの実務ガイド

個室の広さ・形状・設備の違いを理解する
個室は「休む・整える・招く」の三機能が滞りなく回る広さと形状を押さえることが重要です。
広さ・形状・設備の差を把握して設えを合わせないと、導線の渋滞や転倒・物の散乱が生じやすくなるからです。
たとえば、長方形はベッド+収納の直線配置で介助側の余白を確保しやすく、L字型は視線を遮り過ぎない低収納を使えば落ち着きと見守りを両立できます。扉は引戸が理想、開き戸なら開閉干渉域を避けて家具を置きます。窓・コンセント・コール位置は平面図に記し、使う順に並べ替えます。
結論として、部屋の“クセ”を先に読み、導線>家具>装飾の順に最適化することが成功の近道です。
持ち込み家具・家電の選び方(テレビ/冷蔵庫/加湿器/収納)
持ち込みは「安全・簡単操作・維持管理のしやすさ」を軸に選定します。
理由は、機器トラブルや清掃の手間が増えると、生活の質と職員の運用に負担がかかるためです。
具体例:テレビは24〜32型・大きめボタンのリモコン・転倒防止固定。冷蔵庫は45〜90L・ドアが軽い・霜取り簡易。加湿器は空焚き防止・上部給水・手入れ容易。収納はローチェスト(天板≦90cm)で視線を遮らず、耐震金具と滑り止めを併用します。延長コードは熱に強いPSE適合+配線固定が前提です。
結論として、“使う人基準”と“運用基準”の両立を満たすスペックを最優先にいたします。
グリップできる家具/配色は落ち着き重視/“使い慣れ”を優先
家具は“つかまれる”こと、配色は落ち着きを保つこと、そして使い慣れを尊重することが要です。
理由は、立ち上がりや方向転換の一瞬に支えが要り、色刺激の過多は不安を増やし、馴染みのある物は行動の予測可能性を高めるためです。
例として、角に丸み・しっかりした肘掛の椅子、手を掛けても動かないローボードを選び、ベージュや木質系を基調にアクセントは小物で最小限にします。写真・時計・愛用品は“定位置化”して即時認識を助けます。
結論として、グリップ性×落ち着き色×馴染みの三点で、安心と自発性を底上げいたします。
日用品リスト:季節品・補助具・防災小物
日用品は「毎日使う・時々使う・いざという時」に分けて揃えます。
理由は、頻度で置き場所と在庫量を決めると、探し物・紛失・不潔化を防げるためです。
具体例:毎日=眼鏡・補聴器・歯ブラシ・整容セット・常用薬・ティッシュ。時々=季節衣類・ひざ掛け・帽子・日焼け止め・爪切り。防災=小型ライト・携帯コールの予備・モバイル電源・笛・メモカード(既往・連絡先)。保管は透明ボックス+ラベルで“見える化”し、点検日を明記します。
結論として、頻度別の置き方と見える化で、生活が滞らない仕組みをつくります。
レイアウト設計の実践ポイント
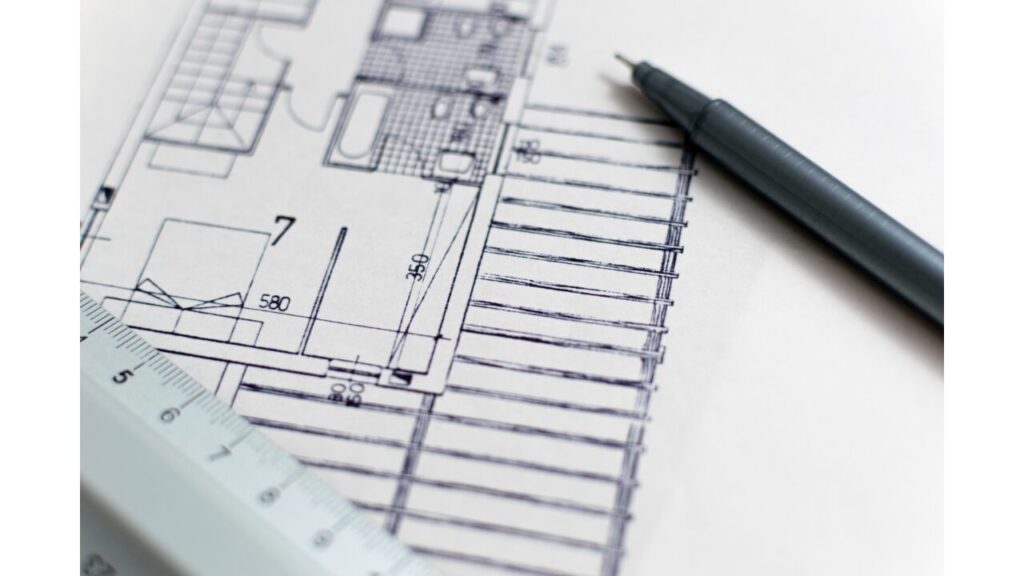
入居前の採寸・家具配置プランニング
入居前に採寸と配置案の下書きを必ず作成いたします。
理由は、現物合わせで始めると、介助余白の不足やコンセントの届かない“やり直し”が頻発するためです。
手順は、間口・奥行・窓・扉・コンセント・コール位置を実測し、等倍縮尺の紙模型で家具を並べ替えます。A案(安全重視)/B案(居心地重視)/C案(折衷)の3パターンを作り、当人・家族の好みで決めます。
結論として、図上で試して現場で微調整が、最短コストで最適解に至る王道です。
コール機器とコンセント位置の先読み
コールと電源は“使う瞬間の手元にあること”を保証します。
理由は、コールの遅延や配線の躓きが、重大事故や不満に直結するためです。
具体例:ベッドサイドのコールは寝位で届く位置に固定、トイレ内にも増設を検討。電源はベッド・TV・冷蔵庫・加湿器・照明のルートを計画し、配線はモールで固定、タップはスイッチ付・耐トラッキングを使用します。
結論として、“手が届く・線が邪魔しない”を基準に、先回りで設計いたします。
ベッド向きと介助導線の最適化
ベッドは介助側の余白と本人の視線の落ち着きを両立する向きにいたします。
理由は、介助の無理姿勢を減らし、覚醒時の視覚情報が落ち着きに直結するためです。
実装例:介助側800mm程度のスペース確保、主動線を塞がない向き、窓や時計が見える視線を意識します。夜間フットライトでトイレ動線を示し、ベッド・照明・コール・眼鏡置きを“ワンリーチ”にまとめます。
結論として、介助余白×視線安定×夜間導線が、事故予防と睡眠の質を高めます。
車椅子回遊スペースの確保と“渋滞”回避
個室内外の回遊性を高め、行き止まりを減らします。
理由は、方向転換の多さが疲労とリスクを増やし、介助者の手間も膨らむためです。
目安として、回転直径1500mm程度、主通路900〜1200mmを確保し、ラグ端部・コード・段差を徹底処理します。手すりは床上750〜850mmで連続させ、可動家具は動かないようキャスター固定を用います。ユニット内は“周回できる導線”を1本確保すると渋滞が減ります。
結論として、回遊スペース×段差処理×連続手がかりで、安全かつ楽な移動を実現いたします。
実践テンプレ&書式(ダウンロード想定)

設え見直しシート(現状→課題→対策→費用→効果)
設え改善を「見える化」して合意形成を早めます。なぜなら、現状・課題・対策・費用・効果を一枚で共有できれば、優先順位と意思決定がぶれにくくなるからです。
テンプレ項目例
- 現状:____(例:食堂が混雑し滞在が短い)
- 課題:____(例:席の役割混在/回遊導線なし)
- 対策:____(例:ラグでゾーニング/島型配置へ変更)
- 費用:____(例:ラグ×2=3万円)
- 期待効果・KPI:____(例:食後滞在15→30分、コール件数▲20%)
運用のコツ:写真のビフォーアフターとKPIをセットで貼付。結論として、意思決定者が一目で判断できる“1枚”を標準様式化します。
調達リスト(優先度・予算帯・代替案)
調達は「優先度×予算帯×代替案」で管理します。理由は、欠品や値上がり時でも改善を止めないためです。
テンプレ列例
- 品目/仕様(例:ウールラグ 170×240、ノンスリップ必須)
- 優先度(A/B/C)
- 予算帯(0円/〜5万円/〜30万円)
- 第一候補(型番・見積)/代替案(型番・見積)
- 納期/設置担当/検収日
結論として、複数見積と代替を最初から持つことで、導入スピードを維持します。
家族向け「持ち込みガイド」(サイズ・安全・メンテ)
家族には“歓迎と安全基準”を同時に伝えます。なぜなら、私物の持ち込みは暮らしの質を高める一方、サイズ超過や転倒リスクの管理が必要だからです。
テンプレ構成例
- 持ち込み歓迎品:写真立て/膝掛け/ローチェスト(高さ90cm以下推奨) 等
- サイズ目安:ベッド脇介助幅800mm確保、扉開閉域への設置不可
- 安全基準:耐震固定/滑り止め/コード固定(PSE対応・タップはスイッチ付)
- メンテ・掃除:拭き取り可能素材推奨、加湿器は週1清掃
- 事前連絡欄:品名/サイズ/搬入日/連絡先
結論として、「歓迎ルール+具体基準」で家族と同じ目線をつくります。
レイアウト図サンプル(居室/リビング三案:円卓・島型・カフェ型)
配置案は3パターンをセットで提示します。理由は、比較することで合意形成が早まり、現場が試行しやすくなるためです。
サンプル説明文
- 円卓型:会話が自然に生まれる/中央見守り◎/車椅子回転に配慮
- 島型:中テーブル+周回導線/配膳・下膳が効率的
- カフェ型:小テーブル分散/“定位置+気分転換席”を両立
居室は「A安全重視」「B居心地重視」「C折衷」を作図し、コール・コンセント・介助余白を明記します。結論、“選べる配置”を標準化し、ユニット差を良い差に変えます。
評価KPI(転倒・ナースコール・食事滞在時間・満足度)
KPIで改善効果を定量把握します。理由は、体感だけでは次の投資判断に結びつかないためです。
- 転倒・ヒヤリ:件数/週(▲20%を目標)
- ナースコール:ピーク時集中率(偏在▲30%)
- 食事滞在時間:分/食(+10〜15分)
- 満足度:5段階(家族・本人・職員アンケート)
- 観察指標:日中覚醒時間、参加行動回数
結論、「数値→意思決定→再投資」の循環を定着させます。
よくある質問(FAQ)

低予算でも効果が出る優先順位は?
まずは0円で“置き方・見せ方・動線”を整えることが最も費用対効果が高いです。
理由は、家具の再配置・掲示の整理・照明角度の調整だけでも、滞在時間や会話量、見守りのしやすさが改善し、事故リスクの芽が減るためです。
具体例として、①主通路の確保(目安900mm以上)、②席の役割分け(食事/作業/静養)、③テレビと時計の視認性改善、④配線固定と掲示のカテゴリ分けを当日中に実施します。次に〜5万円でゾーンラグ+タスクライト+小型収納+椅子の差し替えを投入し、KPI(食後滞在・コール偏在・ヒヤリ件数)で効果を見える化します。
結論として、0円→〜5万円→〜30万円の“階段投資”を守ると、失敗なく継続的に質が上がります。
認知症の方が落ち着かない配色・柄は?
高彩度のベタ塗り・強いコントラスト・鏡面反射・複雑柄は避けるべきです。
理由は、視覚刺激が強いほど誤認や不安、視線のさまよいを誘発しやすく、移動や食事の集中が妨げられるためです。
実務では、床・壁・家具をベージュ〜木質系の低刺激色で統一し、取っ手・サイン・目的地のみアクセント色で強調します。白黒ボーダー、大柄の幾何学、ガラスや鏡面の強い反射は避け、半透明扉・ピクトで機能を示します。便座と床、壁の明度差を確保し、段差や境目が“見てわかる”ようにします。
結論として、“静かな面+絞った点”の配色が迷いを減らし、落ち着きを生みます。
家族の“持ち込み希望”と安全基準の折衷は?
歓迎の姿勢を示しつつ、安全基準を“見える化”して合意するのが最適です。
理由は、私物は暮らしの質を高めますが、サイズ超過・転倒・配線火災などのリスク管理が必要だからです。
具体的には、事前申請シートに品名・サイズ・重量・設置場所を記載し、搬入前に耐震固定・滑り止め・コード固定(PSE適合・スイッチ付タップ)のチェックを行います。難しい場合は期間限定の試行(2週間)を設定し、理由・代替案とともに記録します。思い出の家具は低重心・ローチェスト優先、家電は自動停止・お手入れ容易を条件にします。
結論として、「歓迎ルール」+「安全条件」+「試行の窓口」で、家族と同じ方向を向けます。
標準化とユニットごとの自由度、どこで線引き?
安全・衛生・導線は標準化、季節のしつらえや小物は自由化が基本線です。
理由は、事故や感染に直結する領域のばらつきはリスクを増やし、一方で“暮らしらしさ”はユニットの創意で豊かになるためです。
運用は、①基準書(家具・色・照明・掲示・配線)を整備、②例外は理由・期間・代替を明文化、③月次レビューで写真+KPIを共有、④相互ラウンドで良い事例を水平展開します。たとえば、色パレット・家具寸法・コール位置は固定し、季節装飾・テーブル上の小物・香りはユニット裁量とします。
結論として、“標準=安全と再現性の担保”“自由=家庭らしさの創出”と定義し、文書と写真で共有いたします。
まとめ|「入所」ではなく「入居」。暮らしを支える設えへ

3要素(ハード×ソフト×システム)を一体で回す
最終的に成果を決めるのは、環境(ハード)・暮らしの支援(ソフト)・運営(システム)の組み合わせです。
理由は、空間が行動を誘発し、支援が行動を持続させ、運営が再現性を担保するからです。
実装は、例:食の場を回遊導線+個量個菜(ハード・ソフト)+配膳手順と記録様式(システム)で束ねる、という設計です。
結論として、設えの変更は必ず支援と運営の型までセットで設計いたします。
小さく試して、早く学び、段階的に改善する
改善は0円→〜5万円→〜30万円の階段で段階的に進めます。
理由は、スモールスタートで効果と学びを確保し、次の投資判断に根拠を持てるためです。
行動例:本日15分の“動線片付け&照明角度調整”→今週ラグとタスクライト導入→来月造作収納の計画とし、KPI(滞在・コール・ヒヤリ)で検証します。
結論として、“試す→測る→広げる”のループが、無理なく質を底上げいたします。
設えは“ケアの質”を可視化する——今日から一歩を
ユニットケアの設え改善は、ケアの質を可視化しながら「その人らしさ」と安全を同時に高める最短ルートです。
その理由は、ハード(環境)・ソフト(暮らしの支援)・システム(運営)を同期させることで、行動を誘発し、支援を持続させ、運用の再現性を確保できるからです。
例えば、主動線の整理と配線固定、ラグと灯りによる居どころのゾーニング、家族向け持ち込みガイドの共有を今日から実行すれば、食事滞在時間の延伸、ナースコール偏在の低減、ヒヤリ件数の減少といったKPIの改善が期待できます。
結論として、小さく試し(0円施策)、効果を測り、段階的に投資を重ねることで、ユニットケアのQOLと職員の働きやすさは持続的に向上し、「入所」ではなく「入居」の暮らしが根づきます。
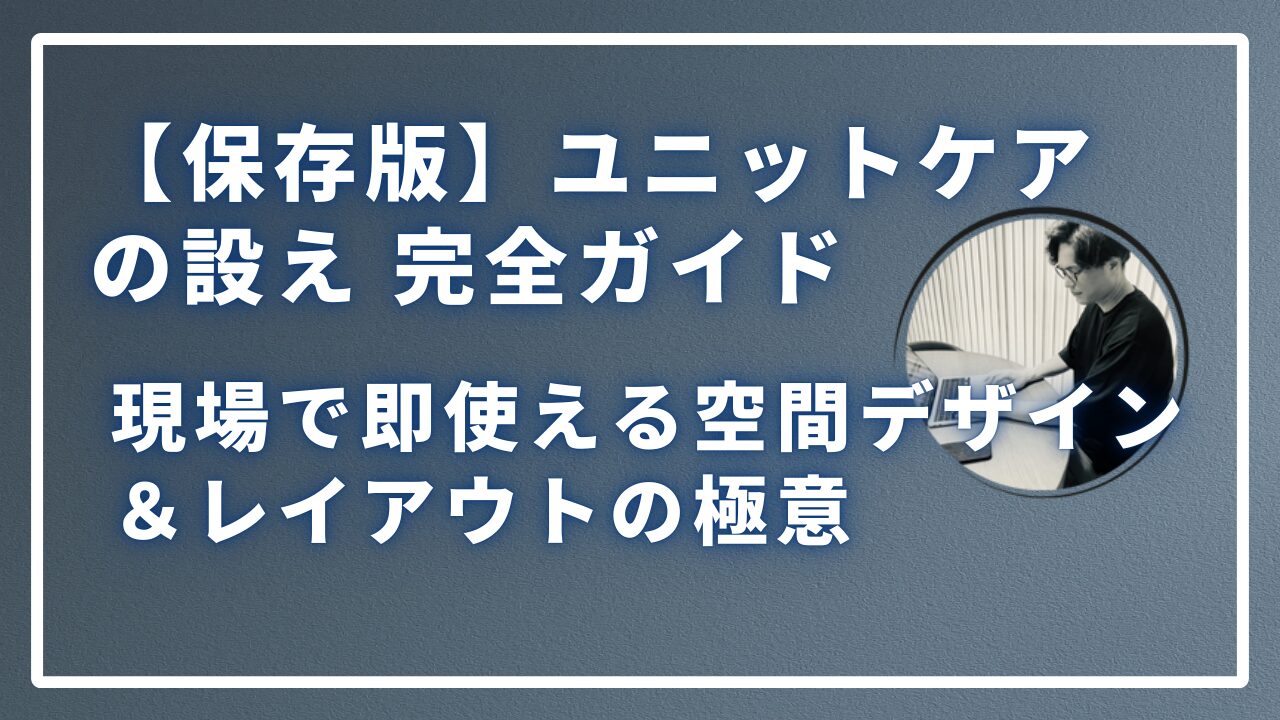
コメント