ユニット型の特別養護老人ホーム(特養)や老健で働く職員の皆さまへ。「ユニット費、何に使う?」「使っても使わなくても指摘される…」というお悩みは、多くの現場で共通です。
本記事では、ユニット費の定義・規定・会計処理・使い道をやさしく整理し、今日から実践できる具体例をまとめました。現場で迷わないための“保存版”としてご活用ください。
ユニット費とは何か?

ユニット費の定義と目的
ユニット費とは、特別養護老人ホームなどにおいて「ユニット型」という少人数のグループを単位にしたケア提供を行う際、各ユニットごとに職員が裁量を持って使える予算のことです。
これは施設の公式な会計科目ではなく、たとえば教養娯楽費の一部として、非公式に定められている場合が多いです。
具体的には、季節の飾りつけや共用トイレの棚、入居者さんへのおやつや飲み物、施設行事の追加プレゼントなど、ユニット内の環境改善や交流促進を目的として活用されます。
特養・老健におけるユニット費の位置づけ
特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)において、ユニット型ケアは「入居者10人以下のユニットで共同生活を送りながら、きめ細かなケアをする方式」として国も積極的に推進しています。
その背景には、プライバシー確保と社会的交流の両立という狙いがあり、ユニット費はその「ユニットらしさ」を高めるためのツールとして位置づけられています。
「ユニット費」という考え方が生まれた背景
ユニット型特養は、従来の多床室に比べてプライベート空間を保ちつつ交流空間も持てる構造です。
こうした環境を職員が自由に工夫できるよう、個別のユニットに小額の裁量予算として「ユニット費」が設けられることが生まれた背景です。
正式に制度化された費用ではありませんが、現場の裁量性を高め、入居者のQOL(生活の質)や職員のモチベーションに寄与する目的で運用されています
ユニット運営の課題について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unit-care-transfer/
ユニット費の規定と金額の目安

各施設での一般的なユニット費規定
ユニット費は法律や介護報酬で定められた公式な項目ではなく、各施設が独自に設定する「裁量予算」です。そのため規定は施設ごとに異なりますが、共通するのは「ユニット全体のために使う」というルールです。
たとえば、会計処理上は教養娯楽費や雑費に含められ、職員が話し合って使い道を決めるケースが一般的です。多くの施設では 年度末に精算または繰越し可能 とし、領収書を残して透明性を確保しています。規定そのものは「使途の自由度は高いが、ユニット全体の利益に限る」という点が共通しています。
ユニット費はいくら?相場感と施設別の事例
金額の相場は全国的に統一されていませんが、いくつかの事例をみると「1ユニットあたり月5,000円程度」を目安にしている施設が多いことがわかります。
この額は職員が自由に運用できる小規模な予算としては現実的で、季節の装飾や飲み物・おやつ購入、行事補助などに十分対応できる範囲です。
この背景には、ユニット型ケアの環境整備やきめ細かなサービス提供にコストがかかっていることがあり、ユニット費もその一部として機能していると考えられます。
※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/
ユニット費の使い道(基本編)

季節の飾りつけやしつらえ
ユニット内の雰囲気を一新するのに、季節の飾りつけはとても有効です。
春には桜の花を折り紙で作って壁一面に飾ったり、夏には七夕の短冊を入居者と一緒に書いて笹に飾ったりすることで、「季節を感じる」「自分も参加している」という実感が生まれます。秋には紅葉や収穫祭のイラスト、冬にはクリスマスツリーや干支の置物など、年間を通して行事と結びつけることができます。
こうした飾りは入居者と一緒に作ることができ、レクリエーションの一環にもなります。また、訪問されるご家族や地域の方にとっても「温かい雰囲気の施設だ」という印象を持っていただけるため、ユニット費を充てる価値が高いといえるでしょう。
ユニットケアの設えについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unitcare-shiturae-design/
共用備品・消耗品(トイレ棚や小物など)
ユニットでは、全員が使う共有スペースに備品を整えることが生活の快適さに直結します。
たとえば、共用トイレに小さな棚を設けてペーパーや消臭グッズを整理するだけで、清潔感が高まり使いやすくなります。食堂や居間では、リモコンや眼鏡を置ける専用トレーを用意すると「探し物が減る」「物が失われにくくなる」という効果も期待できます。
また、手指消毒用の小型ディスペンサー、取りやすい位置に置けるゴミ箱、滑りにくいマットなども少額のユニット費で揃えることが可能です。
こうした工夫は事故防止や職員の作業効率向上にもつながり、入居者だけでなく職員にとっても働きやすい環境を作る一助となります。
入居者全体に提供できる飲み物やおやつ
高齢者は喉の渇きを感じにくく、脱水や低栄養のリスクがあるため、定期的な水分や軽食の提供はとても大切です。ユニット費を活用すれば、普段の食事に加えて「ちょっと楽しみになる時間」を作ることができます。
たとえば、午後の時間にコーヒーや紅茶、ノンカフェインの飲み物を数種類用意して“選べる楽しみ”を演出したり、季節の果物や和菓子を提供したりすることが可能です。週末だけ特別なおやつを出す「お楽しみデー」を設けると、入居者の方にとって1週間の目標や楽しみにつながります。
こうした取り組みは、栄養面のサポートだけでなく、ユニット全体が笑顔になる雰囲気づくりにも役立ちます。
敬老会や行事でのプレゼント追加費用
施設では年間を通じて敬老会や誕生日会、クリスマス会などさまざまな行事が行われます。その際にユニット費を使って小さなプレゼントを準備すると、入居者の満足度がぐっと高まります。
例えば、名前入りのハンカチや手作りのメッセージカード、写真立てなどは、思い出に残る贈り物になります。また、行事の写真をアルバムやカレンダーにまとめて配布するのも喜ばれる工夫です。
こうした「形に残る記念品」は、ご家族にとっても安心感や信頼につながり、施設全体の評価を高める効果も期待できます。
4. ユニット費の使い方(応用編)

ユニットケアを高める工夫(環境改善)
ユニットの雰囲気をさらに良くするために、環境改善にユニット費を使う方法があります。
たとえば、照明をやわらかい光に変えるスタンドライトを購入したり、入居者が安心して座れる椅子や滑りにくいマットを整備したりすることです。
また、アロマディフューザーを取り入れてリラックスできる香りを漂わせる、静かなBGMを流すといった工夫も、心の落ち着きに役立ちます。
こうした小さな環境改善は、特に認知症のある方にとって安心感を与え、不安や不穏を和らげる効果があるとされています。
入居者のQOL向上につながるアイデア例
「その人らしい生活」を支えるために、ユニット費を活用することも有効です。QOL(生活の質)を高めるための工夫は、必ずしも大掛かりでなくても構いません。
例えば、入居者が好きだった歌を流す“音楽の時間”を作る、昔の趣味に関連する道具(将棋盤や手芸用品など)を揃える、季節ごとに少し特別なおやつを提供するなどです。
こうした取り組みは「自分のことを理解してもらえている」という気持ちにつながり、生活に張り合いを生み出します。
他ユニットとの差別化と交流のきっかけづくり
ユニットごとの特色を出すことで、入居者も「自分たちの居場所」に誇りを持てるようになります。
たとえば、毎月1回「ユニット喫茶」を開催し、簡単なケーキと飲み物を準備して他ユニットを招待すると、自然に交流が生まれます。
また、ユニットごとに作品展やカレンダー作りを行い、廊下に展示することで「見に行こう」という楽しみも増えます。
こうした活動は、ユニット間のつながりを強めるだけでなく、入居者やご家族が「ここは温かい雰囲気の施設だ」と実感できるきっかけにもなります。
ユニット費の会計処理と管理

会計処理の基本ルール
ユニット費は施設の会計の中では「雑費」や「教養娯楽費」に近い扱いとなることが多いですが、使い方に一定のルールを設けておくことが大切です。
基本的には「ユニット全体のために使うこと」が前提となり、特定の個人だけが恩恵を受けるような支出は避ける必要があります。領収書を必ず残し、いつ・何に使ったのかを記録することが透明性の第一歩です。
これにより、後から確認があっても説明できる体制を整えることができます。
年度末の繰越しと精算の仕組み
多くの施設では「ユニット費は年度末に精算、または繰越し可能」というルールを設けています。
繰越しが認められる場合は、余った費用を翌年度に回すことができ、まとまった金額を使って大きな買い物(共用家具の購入や大型装飾など)に充てることが可能です。
一方で繰越しができない場合は、年度末に「使い切り」となるため、計画的に使うことが求められます。年末近くになって慌てて消耗品を大量に買うのではなく、年間を通じて少しずつ有効に活用する工夫が必要です。
透明性を高めるための帳簿・記録の工夫
ユニット費の管理で最も重要なのは「透明性」です。ノートやファイルを一冊用意して、いつ・何に・いくら使ったのかを明確に記録することで、誰が見ても納得できる状態を保つことができます。
さらに、月に一度はユニット会議で収支を共有し、職員全員が把握できるようにすると、不必要な誤解や疑念を防ぐことができます。
壁に簡単な掲示を行うと「自分たちのお金がどう使われているのか」が利用者やご家族にも伝わりやすくなり、安心感につながります。
ユニット費を巡る現場の悩みとトラブル
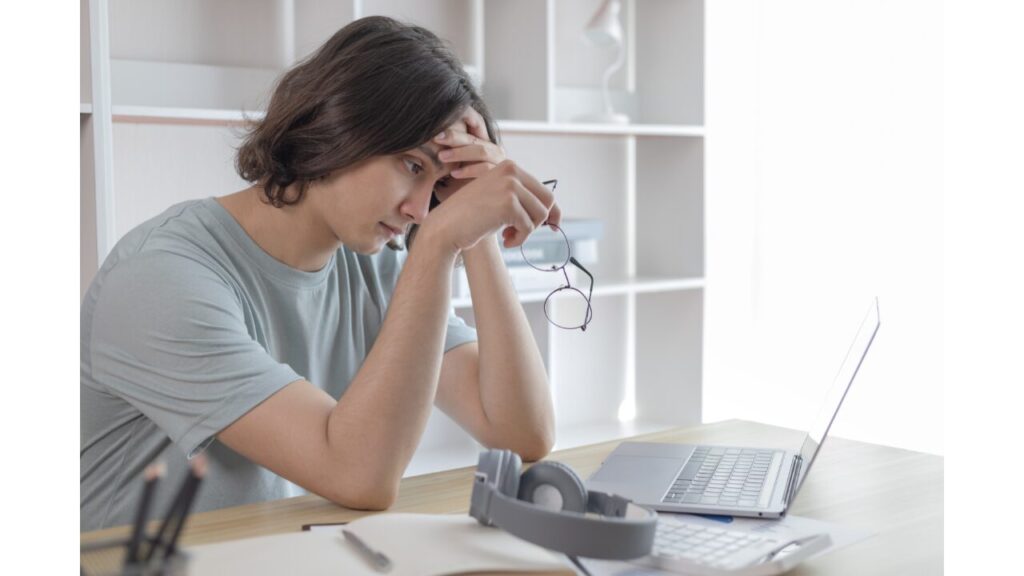
「使って小言を言われる」ケース
ユニット費を積極的に活用したにもかかわらず、「そんなものに使う必要があったの?」と疑問の声が上がることがあります。
たとえば、ユニットの雰囲気を和らげるために観葉植物を購入した場合、一部の職員から「水やりの手間が増える」と不満が出ることがあります。
こうしたケースを防ぐためには、事前に職員同士で話し合い、合意を得てから購入することが重要です。
「使わずに小言を言われる」ケース
逆に、ユニット費をほとんど使わなかった場合も「せっかく予算があるのに何もしていない」と指摘されることがあります。特に年度末に予算が大きく余ってしまうと「工夫が足りないのでは」と見られることもあります。
このような状況を避けるためには、年間を通じた利用計画を立てることが効果的です。春は装飾、夏は飲み物補充、秋は小物購入、冬は行事費補助といった形で、あらかじめバランスよく配分しておくと無理なく使い切ることができます。
自腹対応はNG!ルールを守る重要性
職員の中には「ユニット費を使うのは気が引けるから」と自腹で購入してしまう方もいます。
しかし、これは大きなリスクにつながります。個人負担が続くと不公平感が生まれ、職員間の人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
本来、ユニット費は「ユニット全体のために施設が準備したもの」であり、個人が負担する必要はありません。ルールに沿って正しく使うことで、職員の負担感を減らし、安心して働ける環境を作ることができます。
ユニット費の賢い活用法

職員全体で意見を出し合う「使い道会議」
ユニット費を上手に使うためには、職員一人の判断に任せるのではなく、みんなで話し合う場を作ることが大切です。
月に一度の「使い道会議」を設けると、職員それぞれの視点からアイデアが出され、偏りのない使い方ができます。
たとえば「夏は冷たい飲み物を充実させよう」「秋には壁飾りをみんなで作ろう」など、季節ごとのテーマを決めると計画が立てやすくなります。
こうした会議は、職員間のコミュニケーション強化にもつながり、働きやすい雰囲気を作る効果も期待できます。
小さな工夫で大きな満足につなげる方法
ユニット費は決して大きな金額ではありませんが、工夫次第で入居者に大きな満足をもたらすことができます。
例えば、100円ショップで購入できる小物を使って収納を改善したり、手作りの壁飾りに少し良質な材料を加えて完成度を高めたりする方法です。
少額でも「気持ちが伝わる工夫」をすることで、入居者の方にとっては「大切にされている」という安心感につながります。無理のない範囲で工夫することが、ユニット費を賢く使うコツです。
入居者・家族からのフィードバック活用
ユニット費の使い道は、職員だけで決めるのではなく、入居者やご家族からの意見も取り入れると、より効果的な活用ができます。
例えば「ご飯のおともに漬物があると嬉しい」「お花を飾ってほしい」といった声を聞き、それを反映させるだけで満足度は大きく向上します。
さらに、使い道を説明して感謝の言葉をいただけると、職員のやりがいにもつながります。フィードバックを受けて改善を重ねることが、ユニット費を無駄にせず最大限に活かすポイントです。
【まとめ】ユニット費の正しい理解と活用が職員の悩みを解決する

「ユニット費 何に使う?」の悩みを解消する視点
ユニット費は「何に使うべきか分からない」と悩むこともありますが、基本は「ユニット全体にとって役立つかどうか」で判断すると分かりやすくなります。
入居者全員が少しでも快適に過ごせるような用途であれば、安心して活用できるでしょう。
会計処理と使い道ルールを明確にしてトラブル防止
ユニット費を巡るトラブルの多くは、ルールが不明確なことが原因です。会計処理をきちんと行い、領収書や記録を残しておくことで、不必要な誤解や小言を防ぐことができます。
さらに、年度を通して計画的に使うことで、余らせすぎたり急に使い切ろうと慌てたりする問題も避けられます。
ユニットケアの質を高める費用として前向きに活用する
ユニット費は単なる「小さな予算」ではなく、ユニットケアの質を高めるための大切な資源です。少しの工夫で入居者の笑顔を増やし、ご家族の安心感を高め、職員の働きやすさにもつながります。
「どうせ少額だから」と軽視するのではなく、「このお金をどう使えばユニットがより良くなるか」という前向きな視点を持つことで、ユニット費は大きな力を発揮します。
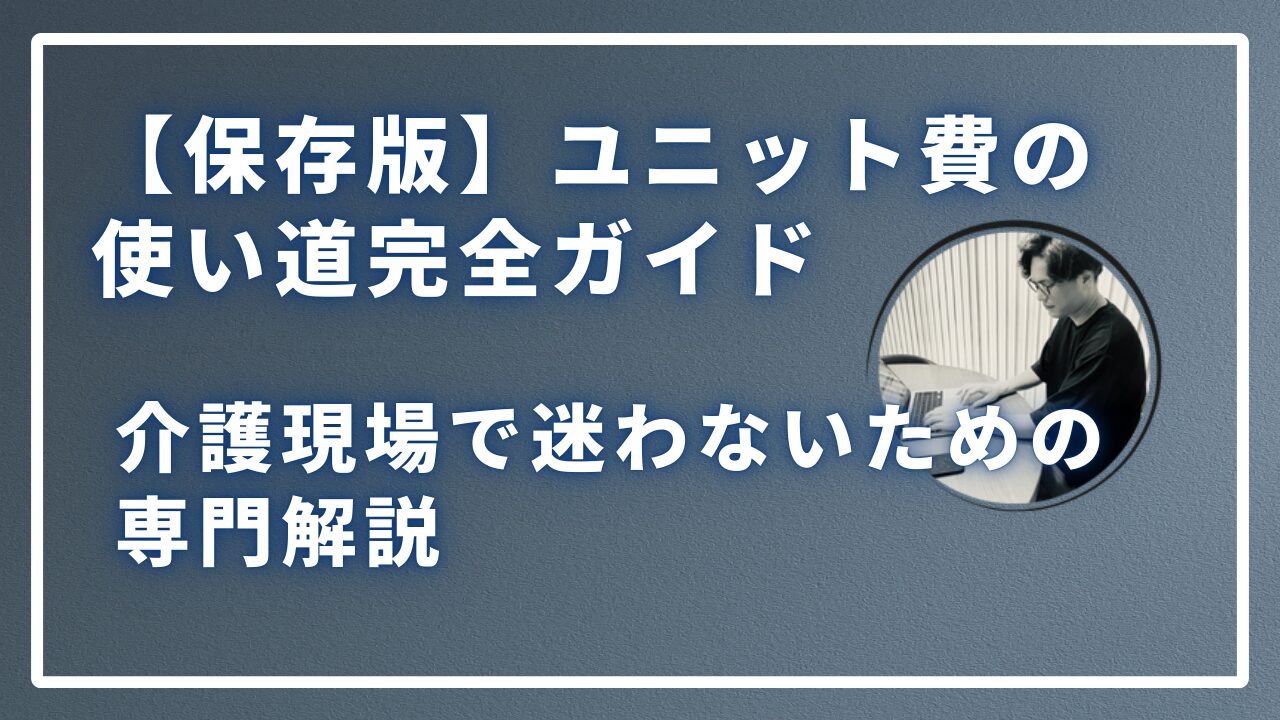
コメント