ユニットケアは「個別性・尊厳・自立支援」を掲げて導入された介護の新しい仕組みです。しかし、現場では人手不足や夜勤の負担、教育体制の遅れなど“理想と現実”のギャップに直面しています。
本記事では、ユニットケアの基本から従来型との違い、メリットと課題、そして現場で実践できる改善アプローチまでを体系的に解説。介護職員や管理者の悩みに答え、個別ケアを効率的に支える実践術を提示します。
ユニットケアとは(定義と理念を“運用可能な言葉”に)

目的:個別性・尊厳・自立支援を小さな単位で実現する
ユニットケアの目的は、入居前の暮らしに近い形で、その人らしい生活を小さなグループで取り戻すことです。10人前後の少人数で顔なじみの関係をつくると、起きる時間や食事のペース、好きな活動などの「日常の選択」が守られ、本人の尊厳や自立が保ちやすくなります。
この考え方を実行するには、「暮らしの単位」と「ケアの単位」を一致させることが大切です。つまり、同じ小さなまとまりの中で生活と介護が回るように設計し、同じ職員が継続して関わる体制にします。そうすると小さな変化(食事量の減り、歩き方の変化、表情の違い)に気づきやすく、早めの対応ができます。
小規模で家庭的な暮らし方は、日々の見守りや衛生面でも有利に働くことがあり、海外の研究では“家庭的で小規模”なモデルが大規模型より感染や重症化を抑えられたという報告もあります(制度は異なるため、同じ効果を断定するものではありません)。
3つの要素:環境(ハード)/生活の支え(ソフト)/運営の仕組み(システム)
ユニットケアは「建物だけ」で決まりません。まず、個室と共同リビングが近く、動きやすくて見守りやすい環境が必要です。次に、起床・食事・入浴などの流れをその人のリズムに合わせて整える生活の支えが要ります。最後に、記録・申し送り・勤務表などをそろえる運営の仕組みが欠かせません。3つがそろってはじめて、少人数の良さが生きます。
たとえば、ユニットの定員は「原則として概ね10人以下、かつ最大15人を超えない」が基本です。これは「互いに関係を築ける小ささ」を保つための目安で、現場では環境・支え・仕組みを同時に見直すと効果が出やすく、どれか1つだけでは成果が出にくいという順番の意識が役に立ちます。
前提:「効率化」は手抜きではなく、個別ケアを助ける土台
「効率化」は時間を生み、入居者と向き合う余裕をつくります。申し送りの書式を統一する、記録に音声入力を取り入れる、巡視ルートを先に決める――こうした小さな工夫で移動と待ち時間が減り、観察や会話に時間を回せます。
家庭的で小規模な暮らし方は、日常の接触が濃く、健康状態の変化に早く気づける利点もあります。コロナ禍の分析では、家庭的な小規模ホームが従来型より感染や死亡の割合が低かったという報告があり、日常運用を整えることが安全にもつながりうることが示唆されました(研究対象は米国)。
従来型との違いを3分で把握

居室と共有スペース:小規模分散か、大規模集中か
ユニット型は個室を基本に、10人前後で使う共同リビングやキッチンが近接しています。生活の場と見守りの場が近いので、移動が少なく、普段の様子を把握しやすいのが特徴です。従来型は多床室や大きな食堂など「大規模に集める設計」が多く、動線が長くなりやすい反面、見守りの目が届きにくい場面が出ます。
一方で、ユニットごとの設備や空間が必要になるため、設計や配置の工夫をしないと“こじんまりしすぎて活動が広がらない”などの弱点も出ます。動線を短くしつつ、自然に人が集まれる場をつくることが大切です(ユニット定員の基本は10人以下)。
ケアの進め方と情報の伝え方:小集団の強みを活かす
ユニット型では、同じ入居者を同じ職員が継続的に支えることが前提になりやすく、生活歴や好み、最近の変化が伝わりやすくなります。記録や申し送りの書式をそろえると、担当が変わってもケアの質が落ちにくく、属人化も防げます。
従来型でも工夫すれば情報共有はできますが、関わる人数が多くなりやすい分、抜け漏れが起きやすいのが実情です。ユニット型は「生活のまとまり=ケアのまとまり」が一致しているため、情報の流れが短く、朝礼や短時間のカンファレンスを固定化すれば、日々の小さな変化に素早く反応できます。
職員の配置と勤務の組み立て:固定配置の良い点・弱い点
ユニット型では、どの職員がどの入居者を主に見るかがはっきりしやすく、観察の質が上がります。一方で、欠員や夜勤の負担が特定のユニットに集中しやすい弱点があります。夜勤明けの負荷をならす勤務表の工夫や、応援に入る手順をあらかじめ決めておくことが欠かせません。
運営では「入居者の処遇を最優先に、同時並行で支障が出ない範囲の応援」をあらかじめ設計し、固定配置の良さを生かしつつ、現実的なバックアップ体制を用意するバランスが重要です。
お金のかかり方:初期費用・運営費・加算の考え方
ユニット型は、個室や小さなリビングなど「小規模の場」を数多く整えるため、建設や改修の初期費用が高くなりがちです。運営でも、ユニットごとの設備や人員でコストが上がる面があります。従来型に比べ、部屋代にあたる「居住費」の自己負担も、個室・多床室など部屋のタイプで差があり、ユニット型個室は高くなるのが一般的です。
また、低所得の方向けの補助では、近年の見直しで居住費の基準費用額が引き上げられました。具体的な負担限度額は段階区分ごとに示されます。費用の考え方を正しく理解し、家族説明では「なぜ差が出るのか」を丁寧に伝えることが大切です。
ユニットケアの設えについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unitcare-shiturae-design/
理想:ユニットケアがもたらす価値

入居者の価値:毎日の“選べる小さな自由”が増え、心身の波が整う
ユニットケアのいちばんの価値は、入居者が「今日を自分で選べた」と感じる瞬間が増えることです。起床や食事の“時刻そのもの”ではなく、本人の体調に合わせて少し前後できる“幅”を持たせることで、無理のないスタートが切れます。結果として、食事量や水分摂取が保ちやすく、昼夜のリズムも整い、日中の居眠りや夜間の不安が和らぎやすくなります。
この効果は、建物の違いではなく“運び方と関わり方”の違いから生まれます。たとえば、朝の声かけを「起きましょう」から「もう5分横になりますか? それとも洗顔だけ先にしますか?」に変える、食事を“一斉”ではなく“短い時間差”で出す、入浴前に好みのタオルや音楽を選べるようにする――こうした小さな選択肢が、安心感と自己決定感を積み重ねます。結果として、拒否的な言動や落ち着かなさが減り、日々の満足度が上がります。
さらに、顔なじみの職員が“昨日との違い”に気づきやすくなり、早めの水分補給や排泄誘導、体位調整などの細かな手当てが間に合います。これは、転倒・誤嚥・脱水といったリスクの芽を早く摘み、結果的に「安全」と「その人らしさ」を同時に守ることにつながります。
職員の価値:判断がシンプルになり、仕事の手応えと学びが増える
ユニットケアでは、職員の判断がシンプルになります。理由は、担当する人が絞られ、昨日の様子・今朝の変化・今日の重点が把握しやすいからです。「誰に何を優先するか」が見えれば、無駄な往復や“やり直し”が減り、支援の順番を自信をもって決められます。
実践面では、朝礼で「今日の3つの重点(例:水分・排泄・疼痛)」を決め、観察ポイントを名札やボードに可視化しておくと、その日の判断がさらにラクになります。小さな“決め方の型”があるほど、迷いが減り、声かけや体位変換、配薬前後の確認など「やるべき基本」に集中できます。結果として、「自分の関わりで表情が和らいだ」「食事量が戻った」などの手応えが増え、仕事の満足感や成長実感につながります。
そして、同じ顔ぶれで関わるからこそ、成功と失敗の学びがユニット内で素早く循環します。夕礼3分で「うまくいった声かけ」「注意が必要だった場面」を共有すれば、翌日からすぐに再現できます。これは新人育成にも直結し、チーム全体の判断力を底上げします。
組織の価値:再現性が生まれ、説明しやすくなり、「選ばれる力」がつく
ユニットケアの組織的な価値は、「うまくいく日」を偶然にしない再現性が手に入ることです。少人数のまとまりごとに手順と情報の通り道をそろえると、緊急対応があっても、最低限の質を保つ“型”で回せます。これは管理職にとって、日ごとのブレが小さくなる=計画が立てやすくなることを意味します。結果として、会議や申し送りに費やす時間が短くなり、現場に還元できる時間が増えます。
また、「見える化」された運営は、家族・行政・地域に対して説明がしやすくなります。例えば、ユニット単位で月次の簡単な指標(転倒の件数、配薬ミスのゼロ継続日数、家族からの感謝・要望件数、食事量や体重の安定状況など)を掲示すれば、取り組みの効果が外からも分かります。説明責任が果たせる体制はクレームを未然に防ぎ、監査・評価の場面でも強みになります。
さらに、働く人にとって「段取りが分かる」「助けを呼ぶ合図が決まっている」職場は離職が起きにくく、採用でも魅力が伝わります。求人では“家庭的で小規模”という言葉だけでなく、「朝礼5分・夕礼5分の固定」「3行記録の統一」「夜勤明けは重い担当を外す」といった具体策を示すと、応募者は入職後の姿を想像しやすくなります。組織が手にするのは、日々の安定に加えて、対外的な信頼と人材面の追い風です。
現実:運用で見える主な課題
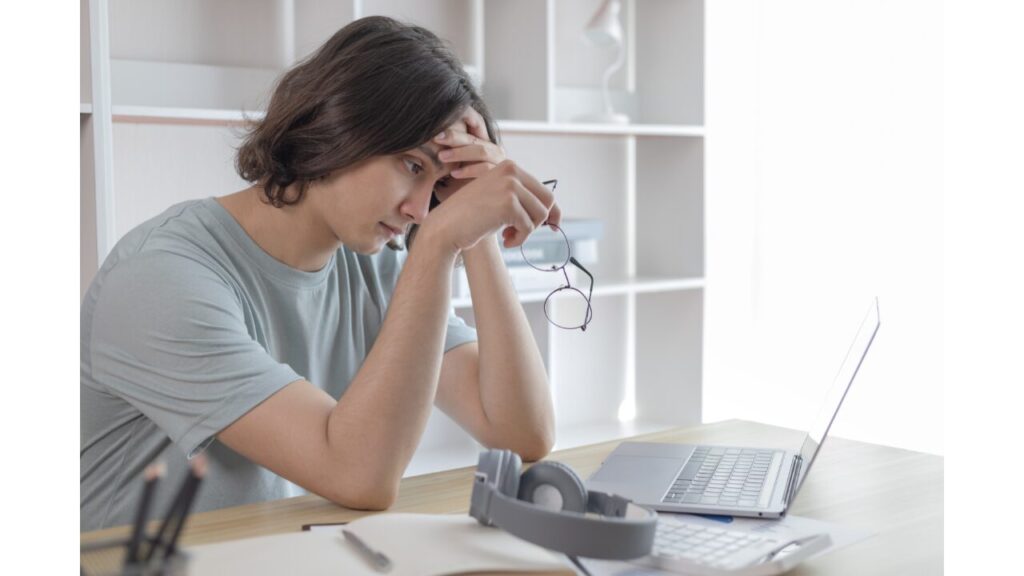
重度化・医療的ケアの増加で負担が一点に集まりやすい
入所者の多くが要介護3以上となる中で、特別養護老人ホームの平均要介護度は概ね「4」に近い水準まで上がっています。これにより、医療的ケアや見守りの密度が必要な場面が増え、ケアが特定の時間や人に集中しがちです。小さな単位であるユニットでは、特に夜間など少人数の時間帯に負担が偏ることが課題になります。
背景として、制度上も特養は中重度者の受け入れを重視しており、新規入所は原則要介護3以上という方針の下で運用されています。この重点化は必要な支援を届けるうえで意味がありますが、同時に日々のケアの密度を高め、職員配置や手順の工夫を求められます。
人手不足の影響が出やすい(特に夜勤と欠員時)
介護の仕事は「人手が足りない」という悩みが最も多く、夜勤の長時間化や少人数シフトは負担を増やします。全国の調査でも、夜勤は2交代が主流で、その多くが16時間以上の連続勤務という実態が報告されています。欠員が出たときは、ユニットという小さな単位ゆえに影響が大きく、観察や記録の時間が削られがちです。
今後、必要な介護職員数はさらに増える見込みで、2026年度には約240万人が必要と推計されています。ユニットケアの良さを守るためには、応援の入り方、夜勤明けの負担をならす勤務表、短時間で済む申し送りの型など、「人の少なさでも回せる仕組み」を先に作っておく必要があります。
職員教育とリーダー育成が追いつきにくい
ユニットケアでは、少人数の場をまとめる役割(リーダー)と、日々の観察・判断をそろえる教育が欠かせません。しかし現場では、急な欠員対応や新人受け入れで時間が取れず、研修や振り返りが後回しになりがちです。介護労働の調査でも、教育・研修や人員配置に対する満足度が低い傾向が示されており、「教えながら回す」仕組みづくりが必要です。
具体的には、観察→援助→記録→共有の順に覚えるOJTメニューを固定化し、5〜10分の短いカンファレンスで「共通言葉」を合わせることで、個人差を縮められます。こうした小さな型は、属人化を防ぎ、ケアのばらつきを抑える土台になります。
ケアの質にばらつき(属人化・情報がつながらない)
同じユニットでも、担当者によってケアのやり方が変わり、結果として入居者の体験が安定しないことがあります。原因の一つは、記録や申し送りの形式がそろっていないこと、もう一つは、生活情報(好み・こだわり・最近の変化)が共有されないことです。ユニットケアの基本は「生活のまとまり=介護のまとまり」なので、情報の流れを短くし、朝礼や終礼などの短時間ミーティングを固定することで、ばらつきを減らせます。
また、設計そのものが生活に合っていない場合(動線が長い、見守りにくい、リビングに人が集まりにくい)も、ケアの質を下げます。小規模分散の強みを活かすには、環境・手順・役割分担をセットで見直すことが重要です。
ギャップの原因を分解して考える

環境:動線・設備・見守りの設計が不足
ユニットケアがうまく回らない大きな理由の一つは、環境づくりが十分でないことです。個室があっても、リビングや台所が遠い、職員の動線が長い、見守りに死角が多いと、少人数の良さが生きません。
なぜかというと、ユニットケアは「生活の場」と「介護の場」を重ねる設計が前提だからです。人が自然に集まれるリビング、個の空間を守る個室、そして見守りやすい視線の通りがそろって、初めて“家のような暮らし”が成り立ちます。日本の公的報告でも、ユニットケアではパブリック/セミパブリック/プライベートのゾーニングと、リビング中心の生活設計が重要だと明記されています。
たとえば、リビングを動線の中心に置き、個室と短い距離で結ぶだけで、声かけや見守りがしやすくなります。キッチンでの配膳や湯せんの位置を工夫すれば、移動のムダも減ります。こうした基本の“場づくり”を整えると、同じ人員でも観察や会話の時間が増え、個別ケアに回せる力が大きくなります。
結局のところ、環境設計はケアの質そのものです。ユニットケアは「箱」だけでは機能しません。場のつくり方を見直すことが、理想と現実の差を埋める最初の一歩になります。
人:採用のミスマッチ・配置の偏り・夜勤設計の不合理
現場のつまずきの多くは「人」に関わります。ユニット型は少人数で関係が濃くなる分、採用のミスマッチや配置の偏り、夜勤の組み方の弱さが、すぐにケアの質に響きます。
その理由は、ユニットでは「誰が誰を見るか」が明確で、交代要員が少ないためです。欠員が出ると代わりが入りにくく、夜間など少人数の時間帯は負担が集中します。全国調査でも、介護の悩みのトップは「人手が足りない」で、次いで「仕事内容のわりに賃金が低い」「身体的負担が大きい」が続き、人員体制への不満が強いことが示されています。
たとえば、夜勤明けが連続して重くなる、欠員時の応援の入り方が決まっていない、といった状況では、観察や記録が後回しになりがちです。まずは「応援に入れる人のリスト化」「夜勤明けの負担をならす並び替え」「短い申し送りの型」を決めるだけでも、偏りは和らぎます。
まとめると、ユニットケアの人の課題は仕組みで減らせます。採用時の適性確認と、欠員・夜勤に強い勤務設計のセットで、日々の“回らない”を小さくできます。
ユニットケア人事異動のジレンマについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unit-care-transfer/
運営:手順書不足・目標管理不足・話し合いの時間不足
運営面の弱さも、ギャップの原因です。手順書(SOP)が統一されていない、目標や指標がはっきりしない、朝礼やカンファレンスの時間が確保されない――この三つが揃うと、属人化が一気に進みます。
理由は簡単で、少人数ゆえに個人のやり方がユニット全体に影響するからです。法令上も、ユニット型特養は「運営規程」を整備し、職員数や役割、緊急時対応、虐待防止、非常災害対策など“運営の重要事項”を定めることが求められています。これは「書類作成」ではなく、「やり方をそろえる」ための土台です。
たとえば、排泄・食事・入浴の流れを1枚の手順にまとめ、記録フォーマットを全ユニットで統一し、1日5〜10分の振り返りを固定化するだけで、ケアのバラつきは目に見えて減ります。
要するに、運営は「決める・見える・合わせる」の順で整えるのが近道です。書式・目標・話し合いの3点セットを用意すれば、ユニットは安定して回るようになります。
制度:基準や報酬と現場の実情がずれている
制度面の“ズレ”も現実の壁です。ユニット定員「おおむね10人以下」などの枠組みは、生活のまとまりを守るうえで意味がありますが、建物の制約や人員の不足とぶつかる場面があります。
また、低所得の方の居住費を助ける「補足給付」では、2024年8月から居住費の基準費用額が日額60円引き上げられ、費用の説明がより重要になりました。現場は、制度の変更点をわかりやすく伝えつつ、生活の質とのバランスを一緒に考える姿勢が求められます。
結局のところ、制度は変わり続けます。最新の基準や費用の情報を押さえ、家族説明と職員教育に反映することで、「制度と現場」のズレは縮められます。
解決の考え方:「諦めない」で「賢く」進める

段階的に整える:手順をそろえる→見える化→無駄を減らす
ユニットケアの立て直しは、段階を追うとスムーズです。まず「手順をそろえる」。次に「見える化」して共有する。最後に「無駄を減らす」。
なぜ段階が大事かというと、いきなり高度な改善は続かないからです。法令でも、ユニット型は運営規程や研修体制の整備が求められています。これは“現場のやり方を言葉にする”という最初の一歩にあたります。
実例として、排泄・食事・入浴のやり方を1シートにまとめ、申し送りのテンプレと合わせて掲示し、観察ポイントをチェック欄にするだけで、抜け漏れが減ります。さらに、音声入力など簡単なICTを併用すれば、記録時間を短縮し、対人時間を増やせます。海外の小規模“家庭的ホーム”の研究でも、日常運用が整った小規模モデルは安全面で良い結果を示しています(制度差はありますが方向性の参考になります)。
まとめると、背伸びせずに「そろえる→見える→減らす」を回すことが、ユニットケアを安定させる最短ルートです。
生活3大場面の見直し:排泄・食事・入浴の流れと役割を明確に
改善の効果が大きいのは、毎日必ず起きる三つの場面です。排泄・食事・入浴の流れを分解し、だれが何をするかを明確にすると、混乱が一気に減ります。
理由は、これらが一日の“混み合う時間”で、ミスや待ちが起きやすいからです。ユニットケアの考え方でも、画一的な日課ではなく、入居者に合わせた個別ケアが重視されています。流れを個別化しつつ、最低限の型をそろえることが肝になります。
たとえば排泄では「声かけ→移動→見守り→片づけ→記録」を分けて担当するのではなく、一連で一人(または固定ペア)が責任を持つ形にします。食事は提供時刻の“幅”を決め、温冷保持の導線を短くします。入浴は時間帯をずらし、待ちをなくす配置に見直します。これだけで、待ち時間と移動のムダが減り、事故リスクも下がります。
要するに、三つの場面を“生活の道筋”として整えると、ユニット全体が静かに回り始めます。最初にここを整えるのが得策です。
情報共有の仕組み:共通言葉/短時間カンファ/申し送りの型
情報が通らないと、ユニットはすぐにばらつきます。共通言葉を決め、短時間カンファレンスを固定し、申し送りの型をそろえることで、日々の小さな変化に早く反応できます。
なぜかというと、ユニットケアは「生活のまとまり=介護のまとまり」を前提に、情報の流れを短く設計するからです。厚労省の基準でも、運営規程の整備や研修の実施が求められており、これは“チームの共通理解”を作るための仕組みづくりと言い換えられます。
例として、朝礼5分で「昨夜の変化・今日の重点・家族連絡」を共有し、終礼5分で「ヒヤリ・良かった関わり・明日の予告」を確認するだけで、情報が一日で循環します。申し送りは「事実→解釈→次の一手」の3行テンプレに統一します。これにより、属人化が減り、誰が入っても一定の質を保てます。
つまり、情報共有は“技術”ではなく“仕組み”です。共通言葉・短時間カンファ・送受信の型という三点セットを作ることで、明日からのユニットは確実に安定します。
すぐに試せる改善アイデア集
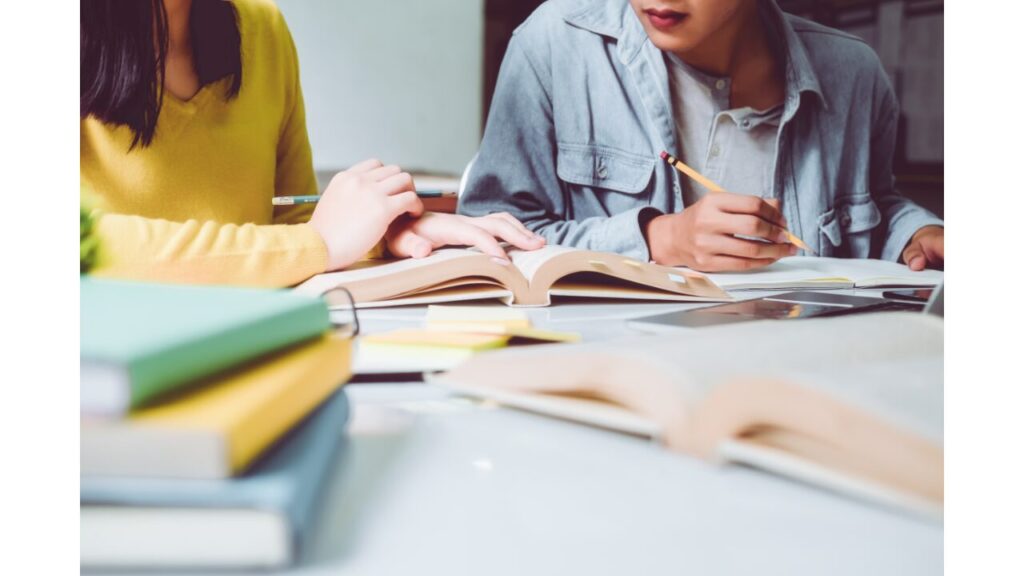
共通言葉リストの作り方(優先順位と判断基準をそろえる)
ユニットで使う言葉を一本化すると、伝達の行き違いが減り、交代で入る職員でも同じ基準で動けます。言葉の意味と優先順位がそろっているほど、判断の順番が迷子にならず、無駄な往復や「言った・言わない」が起きにくくなります。
作り方は、①よく使う言葉を洗い出す(例:見守り/声かけ/安全第一 など)②“優先順位”を明文化する(例:「転倒防止>生活のペース>職員の都合」)③判断の拠り所を添える(例:「眠気が強い時は10分置いて再声かけ」)。A4一枚にまとめ、リビングとスタッフルームに掲示しましょう。これだけで申し送りが短くなり、ケアのばらつきが目に見えて減ります。
結論として、言葉の定義と優先順位をひと目で共有できるだけで、申し送りが短くなり、ケアのばらつきが目に見えて減ります。
「10分日次リセット」:朝礼→観察ポイント→日中の再配分→夕礼
1日の始まりと終わりに短い打ち合わせを入れると、ユニット全体が静かに整います。
理由は、少人数ユニットは“その日その時”の体調や気分の影響を受けやすく、朝の段取りと夕方の振り返りで軌道修正しやすいからです。厚労省の運営基準は、規程整備や研修など“やり方をそろえる”仕組みづくりを求めており、短時間カンファレンスはその実践例です。
やり方は、朝礼5分で「昨夜の変化/今日の重点/家族連絡」を確認し、昼に2分だけ「観察ポイントのズレ」を合わせ、夕礼3分で「ヒヤリ・良かった関わり・明日の予告」を共有します。記録は3行テンプレ(事実→気づき→次の一手)に統一し、紙でもタブレットでもOKです。
結果として、情報の行き違いが減り、観察の目が増え、事故・誤薬などのヒヤリも早めに拾える体制ができます。
夜勤の負担を軽くする:巡視ルート・起床介助の前倒し・音声入力の活用
夜勤は負担が重くなりがちですが、巡視と記録を“型”にすれば、体力と注意力の消耗を抑えられます。
背景として、介護現場では「人手が足りない」が最も多い悩みで、夜勤は2交代・長時間になりやすい実態があります。だからこそ、ルートの固定化と記録の省力化が効きます。
具体的には、①巡視の順番とチェック地点を地図で示し、無駄な往復を減らす②起床介助は、状態の良い方から前倒しに着手し、ピークの重なりを避ける③記録は音声入力や定型文を活用し、後追いの書き起こしを減らす、の3点です。
こうした“段取りの標準化”は、ユニットごとの少人数体制でも安定運用を助け、夜勤明けの疲労感を和らげます。
認知症の行動・心理症状への対応:刺激を整える/関係をつなぐ/選べる提示
認知症の行動・心理症状(落ち着かない、怒りっぽい、夜間不眠など)は、環境調整と関わり方で和らぐことが多いです。
その根拠として、厚労省は「本人主体の介護と適切な理解が、症状の予防や軽減につながる」と示しており、研修体系も整備されています。大切なのは薬の前に生活を整える視点です。
実践は、①刺激を整える(照明・音・温度・匂いを穏やかにし、混雑時間を避ける)②関係をつなぐ(なじみの職員が声かけし、安心できる手順を繰り返す)③選べる提示(「AかBか」を示し、拒否が強いときは時間を置いて再提示)。海外の小規模“家庭的ホーム”研究でも、こうした日常運用の丁寧さが安全面に良い影響をもたらすと報告されています(制度は異なるが方向性の参考)。
まとめると、環境と関わりの整え方を先に変えることが、落ち着きと安心に直結します。
認知症ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/nintisyou-haikai-yoboutaisaku/
家族との連携:情報シートと月1回の短い面談で不満の芽を摘む
家族と早めに情報を共有すると、誤解や不満の芽を小さいうちに摘めます。
なぜかというと、ユニットケアは生活の場が身近で、日々の小さな変化が起きやすいからです。家族が“最近の様子”を把握できると納得感が高まり、相談もしやすくなります。厚労省はユニットケアの考え方として、生活に近い場での本人主体の支援を掲げており、家族との協力はその実現を後押しします。
方法は、①「最近の変化・食事・睡眠・気分・活動」をA4一枚の情報シートにまとめ月1回渡す②月1回・15分の“短い面談”を設け、要望をその場で整理③方針変更があれば、その日のうちにスタッフ間で共有です。
結果として、家族満足は上がり、クレームや行き違いが減ります。採用広報の観点でも、情報公開に前向きなユニットは安心感を与えます。
人づくりとシフトの工夫

ユニットリーダー育成の道筋(3か月/6か月/12か月)
リーダー育成は、短距離走ではなく段階づくりが要です。
理由は、ユニットは少人数で“顔が見える”一方、日々の判断が多く、リーダーの型が無いと属人化しやすいからです。運営基準は、運営規程・研修・非常時対応など“運営の柱”を整えることを求めており、リーダーがその要になります。
道筋の例:0–3か月は「観察と申し送りの型づくり」、4–6か月は「生活3大場面の手順統一と見守り配置」、7–12か月は「家族説明と新人OJTの設計」。月1回のミニ面談で振り返り、到達度を見える化します。
結論として、段階ごとに役割と到達点を決めるだけで、ユニットの安定度が大きく上がります。
新人の育て方:観察→援助→記録→連携の順で
新人教育は、順番を決めると早く安定します。
なぜなら、ユニットでは目の前の人の変化に気づけるかどうかが土台で、観察が弱いまま援助に入ると、ミスや負担が増えるからです。厚労省のユニットケアの考え方は、生活リズムを尊重し、顔なじみの関係で支える点にあり、観察から始める育成は理にかないます。
手順は、①観察のチェックポイントを覚える②基本の援助(排泄・食事・入浴)を先輩とペアで行う③3行テンプレで記録④朝夕の短時間カンファで連携、の流れです。これを2週間単位で回すと、定着が早まります。
結果、現場の教える負担も軽くなり、新人も“できた”感覚を得やすくなります。
介護職の新人指導について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-sinjinkyouiku-guide/
シフトの工夫:夜勤明けの負担をならす/1人対応時間の上限を決める
シフトは“疲れをためない設計”が第一です。
根拠として、介護労働の調査では人手不足が最たる課題で、夜勤は長時間になりやすい実態が示されています。だからこそ、ユニット単位でも夜勤明けの連続負担を避け、応援の入り方をあらかじめ決めることが重要です。
実践は、①夜勤明けに重い担当を当てない②“1人対応”が続く時間に上限を設け、超える時は必ず応援を呼ぶ③欠員時は“誰が・いつ・どこに”入るかの表を全員で共有、の3点です。短時間カンファと合わせて運用すると、抜け漏れが減り、安心して勤務を回せます。
結論として、シフトの工夫は“人を増やす前にできる”安全策です。
評価のものさし:記録の質、事故・苦情、家族の満足、ADLの維持
ユニットの良し悪しは、わかりやすい“ものさし”で見える化すると改善が回ります。
理由は、少人数ゆえに日々の動きが結果に直結するからです。運営基準は、運営規程や研修を通じて「やり方をそろえる」ことを求めていますが、実際に良くなっているかは、簡単な指標で振り返るのが一番です。
例として、①記録の質(3行テンプレの空欄有無・期限内入力)②事故・ヒヤリ・苦情の件数(週ごと)③家族アンケートの一問(「最近の様子がわかる」など)④ADL(食事・移動など)の維持状況を、月1回だけ確認します。
まとめると、難しい式は不要です。“見える化→小さな修正”をくり返す仕組みが、ユニットの力を底上げします。
費用と「見合う効果」を見える化

ユニット費の上手な使い方(小さな投資で大きな満足)
ユニット費(ユニットごとの備品・環境整備の小口費用)は、「少額でも毎日の暮らしに効くもの」に使うと効果が大きいです。
理由は、ユニットケアの価値が「日常の選択」と「安心感」に直結しているからです。生活の細部―照明の明るさ、座り心地、手元の整理、音の調整―を整えると、落ち着きが増し、転倒や誤薬のリスクを下げる下地になります。日本の安全・衛生の検討資料でも、施設が把握する主な事故は転倒・転落・誤薬・誤嚥が上位で、環境調整と手順の整備が対策の柱です。
実例として、すべりにくいルームシューズ、手元を照らす間接照明、食器の滑り止め、見やすいラベル、配薬トレイの色分けなどは数千円〜数万円で導入できます。配薬は世界的にもエラーの起点になりやすく、WHOは「Medication Without Harm(薬での事故ゼロへ)」で手順の標準化と確認を推奨しています。
結局のところ、ユニット費は「毎日使う・触れる」ものに集中投資するのが近道です。小さな投資の積み重ねが、満足と安全の土台を厚くします。
ユニット費について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/unithi-tukaikata-kanzengaide/
効果の例:転倒が減る/感染が減る/職員が辞めにくくなる/満足度が上がる
ユニットの整備と運用をそろえると、「事故が減る」「感染が広がりにくい」「職員の負担感が下がる」「家族の納得が高まる」といった目に見える効果が期待できます。
その根拠として、日本の資料では施設内で扱う主な事故に転倒・誤薬・誤嚥が並び、これらは環境調整・手順標準化・情報共有で減らせるとされています。さらに、家庭的で小規模なモデルはCOVID-19の発生率・死亡率が低かったとする査読研究が複数あり、設計と日常運用の相乗効果が示唆されます。
たとえば、朝夕の短時間カンファレンスで「事実→気づき→次の一手」を共有し、配薬はチェックリスト+ダブルチェック、転倒リスクは夜間動線の明るさ・手すり・呼び出しの位置で予防する――こうした“型”は、薬の取り違えや連絡ミスを減らすと国際的にも推奨されています。
結論として、費用は“結果”で回収します。事故・感染・不満の減少という「見える効果」を毎月の指標で確認し、投資と成果をセットで説明しましょう。
安全と安心の守り方

転倒・誤薬・窒息などのヒヤリハットを「型」で減らす
ヒヤリハットは偶然ではなく、繰り返される“型”から生まれます。だからこちらも“型”でつぶします。
その根拠として、転倒・誤薬・誤嚥(窒息を含む)は介護施設の主要事故で、予防は「評価→環境調整→確認手順→記録・共有」の流れで行うのが基本です。日本の調査・判例レビューでも、深夜のトイレ移動や配薬手順の不備など、繰り返しやすい場面が整理されています。
やり方は、①転倒:夜間ルートの照明・手すり・床材・ベッド高さを点検し、起床時間帯をずらして混雑を避ける②誤薬:配薬トレイの色分けとダブルチェック、交付前後の声出し確認③誤嚥・窒息:食形態・姿勢・一口量・ペースを統一、むせた後の“待つ→再開”ルールを明文化、です。手順とチェックリストをユニットで共有し、朝夕5分の振り返りで“ほころび”を直します。
結局のところ、事故は「型」で減ります。毎日の点検と短い話し合いを固定化すれば、再発は確実に減らせます。
感染対策とゾーニング:小規模分散の強みを活かす
感染対策は「持ち込まない・持ち出さない・拡げない」の3本柱です。ユニットという小さな生活単位は、ゾーニング(エリア分け)との相性がよく、広がりを抑えやすいのが利点です。
理由は、生活のグループがもともと分かれているため、接触の網目が大規模ホームより細かく管理できるからです。実際、家庭的で小規模なホームはCOVID-19の発生率・死亡率が低かったとする研究が複数あり、日常のゾーニング・換気・衛生の徹底が成果につながったと考えられています。
実践は、①ユニット間の職員往来を最小限にする②発熱・咳などの症状が出たら“生活エリアごと”に早めに区分③食事・入浴など混み合う時間帯をずらす④換気と手指衛生を“見える化”して徹底、です。これらは大掛かりな投資をせずに始められ、効果が出やすいポイントです。
結論として、小規模分散は感染対策の味方です。日常の動線と情報の流れを整えれば、“広げない”体制が自然に回ります。
まとめ:ユニットケアは「仕組み化」で理想に近づく

この記事の要点(10秒で振り返り)
明日からの3ステップ(現場で動かす最短ルート)
最後に
ユニットケアは「人を増やす前にできる工夫」で、ぐっと回りやすくなります。
まずは一枚の表・一つの手順・一回の短い話し合いから。小さな改善を積み重ねれば、理想と現実の差は必ず縮まります。
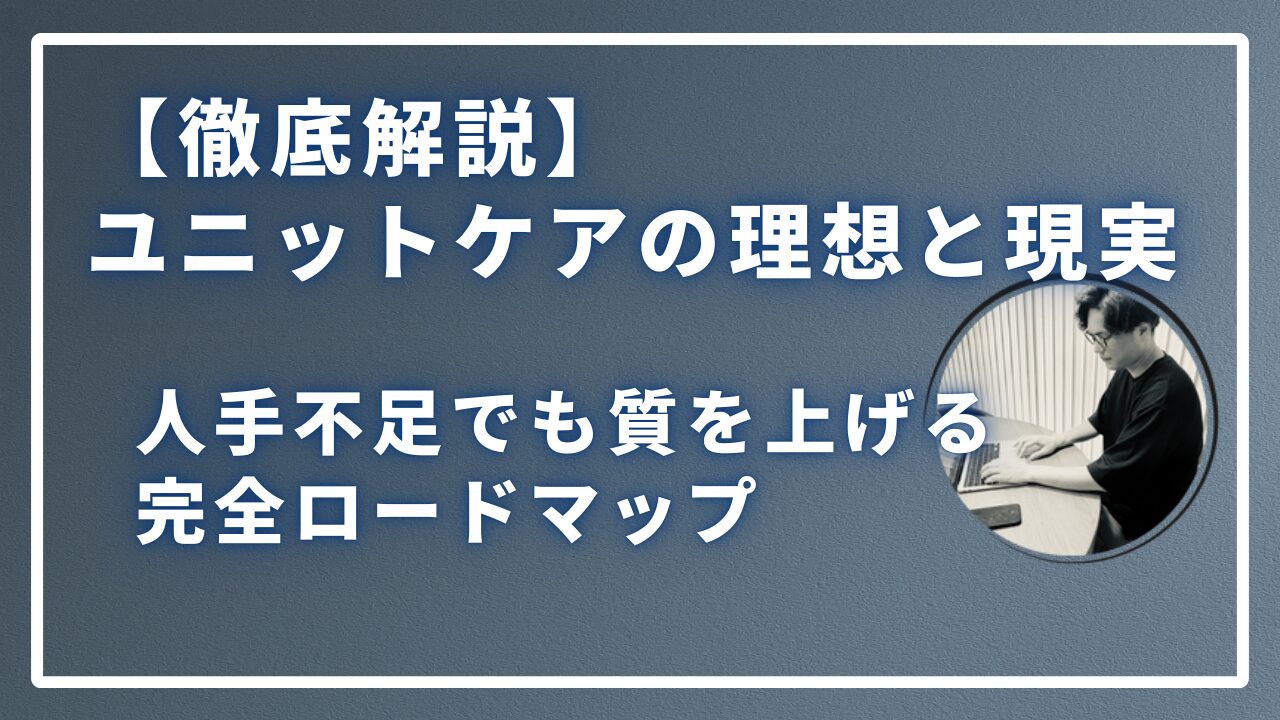
コメント