カスタマーハラスメント(カスハラ)は、介護現場で深刻化し、職員にとって大きな問題となっています。利用者やその家族からの理不尽な要求、暴言、さらには暴力行為が、現場で働く職員の心と身体に大きな負担を与えています。
本記事では、カスハラの定義や事例、効果的な対策について、わかりやすく具体的に解説します。初めての方にも理解しやすいよう、例え話や専門用語の説明を交えながら、カスハラの全体像をお伝えします。
1. はじめに

カスタマーハラスメント(カスハラ)の現状とその深刻さ
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、介護職員が日常的に直面する問題であり、近年、介護現場でその深刻さが増しています。
利用者やその家族からの理不尽な要求や暴言、暴力行為によって、多くの介護職員が心身の健康を損なうケースが増加しています。このカスハラによるストレスや精神的負担が、介護職員の離職率の上昇を招き、現場の人手不足をさらに悪化させているのです。
カスハラの増加を示すデータ
厚生労働省が行った2020年の職場のハラスメントに対する実態調査によると、介護職員の約15%が過去3年間にカスハラを経験していると回答しており、その中で約45%が仕事に対する意欲が減退したと感じていることがわかりました。
これは介護業界にとって非常に深刻な問題であり、現場で働く介護職員の士気やサービスの質に直結する問題です。
具体例: ある特別養護老人ホームで働くAさんは、日々忙しい業務の中で利用者の対応に追われていました。ある日、利用者のご家族から「昨日、父が夕食を残していたのはあなたのせいだ!もっと気を使って食べさせなさい」と電話で執拗に責められました。Aさんは、利用者に対して十分に食事のサポートをしていたものの、家族から「それでは不十分だ」と一方的に責任を押し付けられ、結果として精神的に追い詰められてしまいました。このような状況が続いたため、Aさんは職場を離れることを決意しました。
カスハラ問題の重大性
カスハラは職員個人だけでなく、介護施設全体のサービス品質や運営に大きな影響を及ぼします。
カスハラが放置されると、職員がストレスを抱えながら働くことになり、その結果、利用者へのケアの質が低下する可能性が高くなります。
また、カスハラによって職員が次々と離職することで、施設は新しい人材を確保するのが困難となり、サービス全体の質の低下につながります。
2. カスタマーハラスメント(カスハラ)とは

カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、利用者やその家族がサービス提供者に対して理不尽な要求や暴言、威圧的な態度、さらには身体的暴力を加える行為を指します。これは通常のクレームとは異なり、相手を精神的・肉体的に追い詰める目的を持つ悪質な行為です。
具体的なカスハラの事例
具体例:ある訪問介護の現場で働くBさんは、利用者から「私の家の窓を全部掃除しろ」と突然命じられました。訪問介護の契約内容には清掃は含まれていなかったため、Bさんは丁寧に「申し訳ありませんが、こちらのサービスでは対応できません」と説明しました。しかし、利用者は「なんでやってくれないんだ!お前の給料は誰が払っていると思っているんだ!」と激しく怒鳴り、さらに「この施設を辞めさせてやる」と脅迫されました。このような行為は、単なるクレームを超えて、職員の心身を傷つけるカスハラの典型的な例です。
ポイント: カスハラは、介護職員の働く環境を悪化させるだけでなく、利用者に対するサービス品質の低下や施設全体の評判に悪影響を及ぼすため、適切な対策が必要です。
介護現場におけるカスハラの特徴
介護現場では、カスハラが特に起こりやすい環境にあります。その特徴として、「長期間にわたる接触」「相手が高齢者やその家族であることから逃げにくい状況」「感情的な対応が求められる」が挙げられます。介護職員は利用者と長期的な関係を築くため、一度カスハラが始まると継続的に受けることが多いのが実情です。
具体的な特徴の例
あるデイサービスの職員Cさんは、利用者のご家族から「毎日帰りに必ず母の写真を撮って私に送ってほしい」と要求されました。Cさんは、利用者へのケアに集中するため、日々の写真撮影は難しいと伝えましたが、家族は「お金を払っているのだから、そのくらいやるのは当然だ」と納得せず、何度も同じ要求を繰り返しました。このような行動は、介護現場でのカスハラ特有の「繰り返し」の側面を強調しています。
ポイント: 介護現場では、利用者やその家族と長期間にわたる関係を築くことが多いため、カスハラがエスカレートしやすく、職員が逃げ場を失うケースが多いです。
一般的なクレームとカスハラの違い
一般的なクレームは、サービスに対する不満や改善点を伝えるもので、事業者にとってサービス向上のための貴重な意見となります。一方で、カスハラは、相手を攻撃し、威圧することを目的とした言動であり、職員の尊厳や人格を傷つけるものです。
具体的な違いの事例
一般的なクレームでは、「食事の時間が少し遅かったので、次回は気を付けてほしい」という要望が出されます。しかし、カスハラの場合は「お前のせいで母の体調が悪くなった!責任を取れ!」といった暴言や脅迫に発展します。前者はサービスの改善を求める建設的な意見であるのに対し、後者は職員に対する攻撃であり、受ける側にとっては大きな精神的負担となります。
ポイント: カスハラは介護現場における深刻な問題であり、その影響は職員の心身の健康だけでなく、施設全体の運営やサービスの質にも及びます。利用者やその家族との長期的な関係性や、介護サービスに対する誤解・期待が原因でカスハラが発生しやすくなっています。現場で働く介護職員を守り、安心して働ける環境を整えるために、カスハラに対する理解と適切な対応策が求められます。
※ クレーム対応について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-claim-taisaku-7step/
3. 介護現場で発生するカスハラの事例

利用者からのカスハラ事例
利用者自身からのカスハラは、介護職員にとって特に辛いものです。長期間にわたる関係性の中で、毎日のように理不尽な要求や暴言を受けることが、職員の精神的な負担を増加させます。利用者との直接的な接触時間が長いだけに、対応が困難なケースが多く見られます。
具体例1: 身体的暴力
介護職員Oさんは、夜勤中に利用者のNさんから突然、顔を叩かれました。Nさんは認知症の進行があり、感情をコントロールすることが難しい状態でしたが、Oさんはそれまで優しく対応し続けていました。
しかし、その日Nさんは「お前がいるから眠れないんだ!」と叫びながらOさんを攻撃しました。OさんはNさんの症状を理解していたため我慢しましたが、このような暴力行為が何度も繰り返されることで、次第にOさんは「自分は何をしているのだろう」と無力感に苛まれるようになりました。
ポイント: 身体的暴力を伴うカスハラは、職員の心身に大きなダメージを与えます。認知症などの症状が関与している場合でも、対応策やサポート体制を整えることが必要です。
具体例2: 精神的暴力
別の介護施設で働くPさんは、利用者のTさんから毎日のように「お前は何もできない」「どうせ仕事ができないんだろう」と暴言を浴びせられていました。
Tさんは比較的若い利用者で、身体的には自立していましたが、過去の職場経験から他人を見下す態度がありました。Pさんは「利用者だから仕方ない」と我慢して対応していましたが、次第に自分の仕事に対する自信を失い、「私には介護の仕事は向いていないのかもしれない」と感じるようになりました。
ポイント: このような精神的な暴力は、職員の自己肯定感を低下させ、最終的には離職を考えるきっかけとなるため、施設全体でのフォローが必要です。
利用者以外(家族・親族など)からのカスハラ事例
利用者本人だけでなく、その家族や親族からのカスハラも非常に深刻です。家族からの攻撃的な要求は、直接的な利用者対応とは異なり、職員が対応方法を見つけにくいケースが多いのが特徴です。家族からの期待や不安が高まることで、理不尽な要求や暴言に発展することがあります。
具体例1: 過度な要求や不合理なクレーム
介護施設で働くQさんは、利用者の息子から「母親の食事は毎回他の人とは別メニューにしてほしい。母はアレルギーがあるから特別な料理を毎回用意してもらわないと困る」と言われました。
Qさんはアレルギー対応は行っていましたが、「他の利用者と同じ食事でも問題ない」と医師からも確認されていたため、特別対応は難しいと説明しました。しかし息子は納得せず、「この施設は高いお金を払っているんだから、それくらいやるのが当然だろう!」と怒鳴り、他の利用者の前でも職員を非難しました。
Qさんは何度も丁寧に説明しましたが、息子からの要求はエスカレートするばかりで、最終的には「ここでは母親は安心して過ごせない」と周囲に言いふらす事態になりました。
ポイント: 家族からの過度な要求は、介護施設のサービス内容を超えたものであることが多く、その対応には限界があります。施設側は家族に対して事前にサービス内容を丁寧に説明し、理解を促すことが重要です。
具体例2: 突然の訪問や無断での介入
別の施設では、利用者の娘が突然施設に訪れ、職員に「母親の寝室のベッドはもっと豪華なものに変えるべきだ」と指示してきました。
職員が「施設の設備の変更はご相談の上で行っております」と説明すると、「私が買ってくるから勝手に取り付けておいて」と一方的に要求されました。さらに、「職員は母のことを全然考えていない!」と怒鳴り散らし、他の利用者や職員にも迷惑をかけました。
ポイント: 家族からの無断での介入や突然の訪問は、施設全体の運営に支障をきたします。こうした行為を未然に防ぐために、事前に施設のルールを明確に伝え、協力を求めることが大切です。
新型コロナウイルス感染症によるカスハラ事例の増加
コロナ禍によって、感染対策や面会制限が強化されたことで、新たな形のカスハラが増加しています。これらの対策は利用者や職員を守るためのものですが、それを理解せずに過度な要求や暴言を吐く家族が増えています。
具体例1: 面会制限に対するクレーム
ある施設では、感染拡大防止のために面会を制限していました。しかし、利用者の家族から「他の施設では面会できると聞いた。なぜここではできないのか?」とクレームが入り、「母が寂しがっているのはお前たちのせいだ!」と職員が責められる事態になりました。
家族は「母が元気でいられるのは私がいるからだ」と感情的に話し、職員の説明を聞こうとしませんでした。
ポイント: 感染対策に対する家族の理解不足から生まれるカスハラは、現場職員にとって大きなストレスとなります。施設は、感染対策の重要性を丁寧に説明し、家族に安心感を与えるよう小まめな情報共有に努めることが必要です。
具体例2: コロナ感染時の対応に対する不満
ある利用者が新型コロナウイルスに感染し、隔離措置が取られた際、その家族は「もっと早く感染を防げなかったのか!」と施設を非難しました。
職員は感染防止対策を徹底していたものの、家族からは「あなたたちの怠慢のせいで感染した」と責任を押し付けられ、さらにはSNSで「この施設は感染対策が甘い」と書き込まれるなど、施設全体に対する不当な批判にまで発展しました。
ポイント: 感染症対策に対するカスハラは、施設の評判や職員のモチベーションに直結する問題です。施設側は家族に対して定期的に感染対策の状況を説明し、誤解を解消する努力を怠らないことが重要です。
※ 介護職員の9割が経験した事例について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-cushara-jirei7sen/
4. 介護現場でのカスハラが発生する原因

顧客至上主義と介護現場の実情
介護施設の利用者やその家族の中には、「高額な料金を払っているのだから特別な待遇を受けるべきだ」という誤った考え方を持つ方も少なくありません。
このような「お客様は神様」という意識が強く、施設の方針や他の利用者への配慮を無視して自分たちだけの要求を押し付けてくることがあります。
サービスの範囲や認識のズレ
介護サービスの内容や範囲について正確な理解がない利用者や家族が、無理な要求をしてくるケースは多く、これがカスハラに発展することがあります。
特に「介護職員は何でもやってくれる」という誤解から、介護サービスの枠を超えた依頼をされることがあります。
ストレス発散によるハラスメント行為
介護を必要とする家族が日常的に抱えるストレスや不安が、介護職員に対してハラスメント行為として表れるケースもあります。
特に、介護負担が家族の生活に影響を与えている場合、感情的になり、職員に対して八つ当たりのような行動が取られることがあります。
認知症や精神疾患の進行
認知症や精神疾患を持つ利用者が、病気の進行によって職員に対して攻撃的な行動を取ることがあります。これに加えて、利用者の家族がその訴えを真に受け、職員を責めるケースも少なくありません。こうした状況は、職員にとって非常に困難な対応を強いられる場面を生み出します。
5. カスタマーハラスメントを放置するリスク

カスタマーハラスメント(カスハラ)を放置することは、施設全体に多大な悪影響を及ぼします。職員のメンタルヘルスの悪化や離職、施設の評判低下、さらには法的リスクを伴う可能性もあります。ここでは、カスハラを放置することによるリスクを具体的に解説します。
職員のメンタルヘルスの悪化と離職率の増加
カスハラによる理不尽な要求や暴言、暴力を受け続けると、職員は精神的なダメージを受け、次第にメンタルヘルスが悪化していきます。このような状態で働き続けることは非常に困難であり、結果的に職員の離職率が増加します。
ポイント
- メンタルヘルスが悪化した職員は、サービス品質を維持することが難しくなる。
- 職員の離職が増えることで、人材不足が深刻化し、残された職員の負担が増加する。
事業所の法的リスクや風評被害
カスハラを放置すると、事業所自体が法的なリスクを負う可能性があります。特に、職員がハラスメントによる精神的苦痛を受けている場合、事業所が適切な対応を怠ったと判断されると、労働基準監督署からの指導や訴訟に発展する恐れがあります。
具体的な事例: ある施設では、職員が利用者の家族からの執拗なカスハラに耐えられなくなり、労働基準監督署に相談しました。その結果、施設側が適切な対応をしていなかったことが明らかになり、是正指導を受けることとなりました。このことが報道され、施設の評判は一気に悪化し、利用者の新規契約が減少する結果となりました。
ポイント
- カスハラへの対応を怠ると、事業所全体の信用を失うリスクがある。
- 風評被害はインターネットやSNSを通じて広がりやすく、施設の存続に影響を与える。
施設運営への深刻な影響
カスハラが放置されると、施設全体の雰囲気が悪化し、職員間のコミュニケーションが不足することにもつながります。これにより、サービスの質が低下し、利用者全体に対するケアが十分に行き届かなくなる恐れがあります。
ポイント: カスハラを放置すると、職員の離職や施設の評判低下、法的リスクなど、様々な問題を引き起こすため、早急な対応が求められます。
6. 介護施設が取り組むべきカスハラ対策

カスハラ問題に対処するためには、施設全体での取り組みが必要です。以下に、効果的な対策について具体的に解説します。
トップダウンでの「カスハラを許さない」姿勢の明確化
施設のトップが「カスハラを絶対に許さない」という姿勢を示すことが重要です。管理者が率先してカスハラに対する取り組みを行うことで、職員は安心して働ける環境を作ることができます。
カスハラ対応マニュアルの策定と研修の実施
カスハラに対応するためのマニュアルを作成し、職員に対する研修を定期的に行うことも重要です。具体的な対応方法や報告手順を示すことで、職員がカスハラに直面した際に迷わず対応できます。
職員同士での情報共有とエスカレーションの仕組み構築
カスハラが発生した際に、職員同士で情報を共有し、適切にエスカレーションできる仕組みを作ることが重要です。これにより、カスハラの早期発見や迅速な対応が可能となります。
顧問弁護士や警察との連携による法的対応
カスハラが深刻な場合、顧問弁護士や警察と連携して法的対応を行うことも検討する必要があります。特に暴力行為や脅迫がある場合、速やかに法的措置を講じることで職員を守ることができます。
7. 弁護士に相談・依頼する必要性とメリット

カスハラ対策によるメンタルヘルス対策と職員の人材定着
弁護士に相談することで、カスハラに対する適切な対応策を講じることができ、職員のメンタルヘルスを守ることができます。これにより、職員が安心して働ける環境を整え、人材の定着につながります。
法的措置の相談・実施とクレーム対応の後方支援
弁護士を通じて法的措置を取ることで、カスハラに対する抑止力を高めることができます。また、クレーム対応の際に弁護士からのアドバイスを受けることで、適切な対応が可能となります。
8. カスタマーハラスメントの裁判例とそのポイント
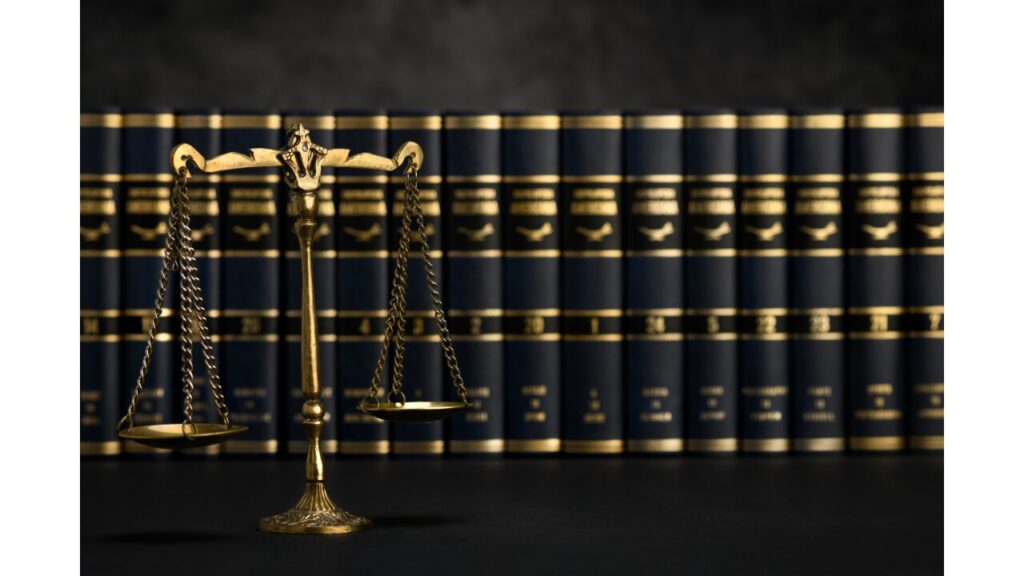
代表的なカスハラ裁判事例
カスタマーハラスメント(カスハラ)の問題が深刻化する中、いくつかの裁判例はカスハラへの対処において非常に参考になります。これらの裁判事例は、どのような行為がカスハラと認定され、施設や職員がどのような対応を求められるのかを明確に示しています。
ポイント: この裁判例から学べることは、施設側がカスハラに対して毅然とした態度を示し、職員を守るための措置を講じる必要性です。カスハラを放置すると、事業所自体が法的責任を問われる可能性があるため、早期に対応することが重要です。
裁判所が認めたカスハラ行為の判断基準
裁判所がカスハラと認定する際には、いくつかの判断基準が設けられています。主に「職員に対する言動が社会通念上、許容できる範囲を超えているか」「継続的かつ執拗に行われているか」などが判断のポイントとなります。
ポイント: 施設としては、カスハラの判断基準を理解し、早期に問題を察知し対応することが必要です。これにより、職員を守りながら施設の法的リスクを回避することができます。
裁判事例から学ぶ対応のポイント
カスハラの裁判事例から学べる重要なポイントは、施設が早期に問題を把握し、適切な対処を行うことです。
裁判では、施設がカスハラに対してどのように対応したかが問われるため、被害報告のシステムや職員へのサポート体制を整備しておくことが求められます。
具体的な対策: カスハラの兆候を見逃さず、職員からの報告を受けた場合は、迅速に上司や管理者が対応に当たる体制を整えることが重要です。また、弁護士など専門家と連携し、法的措置を視野に入れた対応策を取ることが必要です。
ポイント: 裁判事例から学ぶことで、施設側はカスハラに対するリスク管理を徹底し、職員の安心・安全な労働環境を確保するための方針を明確にすることが重要です。
9. カスハラを防ぐための社内体制の構築
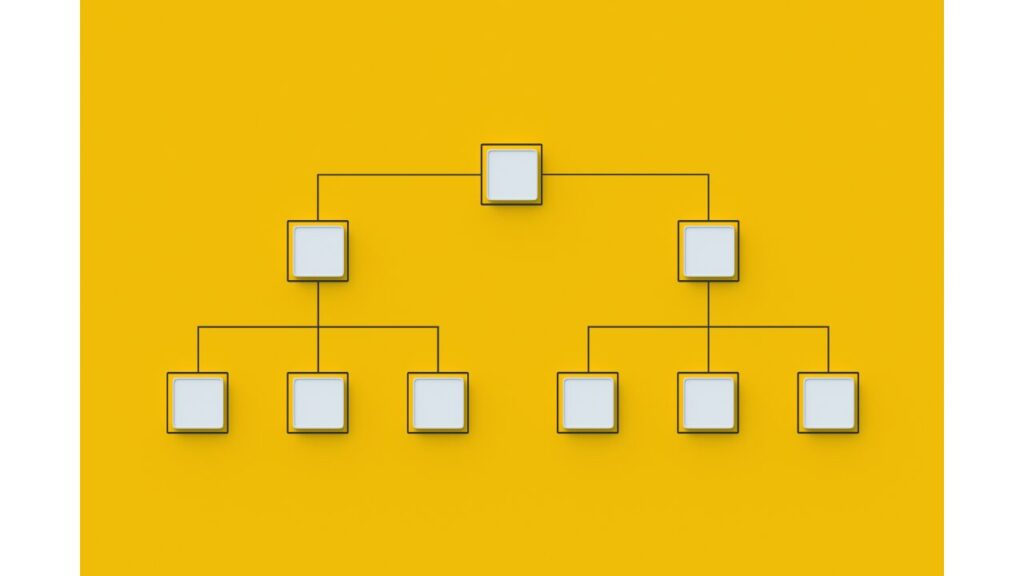
カスハラを未然に防ぎ、発生した際に迅速かつ適切に対応するためには、施設内での体制構築が不可欠です。社内での相談体制や職員教育、外部機関との連携が大きな役割を果たします。
社内相談窓口の設置と活用
カスハラに直面した際、職員が気軽に相談できる社内相談窓口を設けることは非常に重要です。この窓口では、カスハラの内容や被害状況を記録し、職員を守るための対策を検討します。
定期的な研修やシミュレーション訓練
カスハラに対する知識と対応力を身につけるためには、定期的な研修が不可欠です。特に、実際のカスハラ事例を使ったシミュレーション訓練は、職員が現場でどのように対応すべきかを実践的に学ぶ機会となります。
ポイント: 研修では、カスハラの定義や判断基準、対処方法、エスカレーションの仕組みをしっかりと伝え、職員が自信を持って対応できるようサポートすることが大切です。
社外ネットワークや支援団体との連携
カスハラの問題に対処する際、社外の専門家や支援団体との連携も重要です。例えば、地域の介護業界団体や弁護士事務所と定期的に情報交換を行い、最新の対策や法的な対応策を共有することは、施設全体のカスハラ対策に役立ちます。
ポイント:社内外での体制を整え、職員が安心して働ける環境を作ることが、カスハラの防止と対策において重要な役割を果たします。
10. カスハラ研修や相談窓口など外部サポート体制の利用

カスハラ問題に対応するためには、外部の専門家や支援機関を活用することも非常に有効です。外部の研修や相談窓口を利用することで、施設内では解決できない問題に対しても適切な対応が可能となります。
カスハラ研修サポート
専門家を招いたカスハラ研修は、職員がカスハラに対して適切に対応するスキルを身につける上で非常に効果的です。特に、法的な観点からのカスハラの理解や、カスハラを未然に防ぐためのコミュニケーション技術を学ぶことは、現場でのトラブルを減らすことにつながります。
外部相談窓口の設置による安心感の提供
施設内だけでなく、外部にも相談窓口を設置することで、職員はより安心してカスハラ問題を相談できます。外部相談窓口は、第三者の視点からアドバイスを提供し、適切な対応策を提案するため、職員が孤立せずに問題を解決できる環境を整えます。
ポイント: 外部窓口の利用は、施設内の相談体制を補完するものであり、職員が「相談しても無駄だ」と感じることなく、カスハラに立ち向かうための心強いサポートとなります。
まとめ
カスタマーハラスメント(カスハラ)問題の深刻さと対策の重要性
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、介護現場で働く職員にとって非常に深刻な問題であり、施設全体の運営やサービス品質にも多大な影響を及ぼしています。
利用者やその家族からの理不尽な要求や暴言、時には暴力によって、職員のメンタルヘルスが悪化し、離職率が高まることで人材不足が深刻化する一方、施設全体の評判や運営に対するリスクも増加しています。
カスハラ問題への具体的な対応策
カスハラ問題に対処するためには、施設全体での明確な取り組みが必要です。まず、トップダウンで「カスハラを許さない」という姿勢を示すことや、職員が安心して相談できる窓口の設置、カスハラ対応マニュアルの策定と研修の実施など、社内体制をしっかり整備することが重要です。
また、弁護士や警察との連携を通じて法的対応を準備し、カスハラが発生した場合に迅速に対応できる体制を構築することも必要です。さらに、外部の専門家や支援機関を活用することで、施設内では解決できない問題に対処するためのサポート体制を整えることが有効です。
早期の対策がもたらすメリット
カスハラへの適切な対応を早期に講じることで、職員のメンタルヘルスを守り、安心して働ける環境を整えることができます。これにより、離職率が低下し、サービスの質を維持・向上させることが可能です。また、施設全体でカスハラ問題に対する理解と対策が徹底されることで、利用者やその家族に対する信頼も向上し、事業所の評判や経営の安定につながります。
結論:カスハラ対策は施設運営の要
カスハラ問題を解決するためには、施設全体での取り組みと、職員を守るための具体的な対策が不可欠です。
介護職員が安心して働ける環境を整えることは、利用者に対するケアの質を高めるだけでなく、施設全体の運営を健全に保つためにも重要です。
今後もカスハラ問題に対する対策を継続的に見直し、改善を図ることで、職員と利用者双方にとってより良い介護現場を実現することが求められます。
このブログ記事を通じて、カスハラ問題への理解を深め、具体的な対策を講じるための指針を提供しました。読者の皆様が、介護現場でのカスハラに対して適切な対応を取り、職員と利用者が安心して過ごせる環境を築く一助となれば幸いです。
とは?-1.jpg)
コメント