はじめに
高齢者施設紹介シリーズの第二弾では、老人保健施設(老健)について詳しく解説します。
老健は特養や病院とは異なる役割を果たしており、利用者の状態や家族のニーズに応じた適切な選択が重要です。
本記事では、老健の目的や特徴、入所条件、リハビリの内容、家族の役割など、多岐にわたるポイントを網羅し、分かりやすく説明していきます。
老人保健施設とは?

老健の目的と介護保険制度における位置付け
老健の主な目的は、自宅での生活が難しくなった高齢者、退院後すぐに在宅復帰するのに不安のある高齢者に対して、医療ケアとリハビリを提供し、再び在宅生活を送るための支援を行うことです。
介護保険制度において、老健は「介護老人保健施設」として分類され、病院から退院後の中間的な施設としての役割を担っています。
入居者は、原則として要介護認定を受けた方が対象で、特にリハビリが必要な方に適しています。
- 在宅復帰を目指す施設である
- 病院と在宅の中間的な施設としての役割がある
入所に関する基本事項

入所要件
老健への入所には、基本的に要介護1以上の認定が必要です。
また、医療的なケアが必要でありつつも、病院での入院治療は不要と判断された方が対象となります。
老健はリハビリを通じて在宅復帰を目指す施設であるため、入所者は一定の回復力や在宅復帰の意欲を持っていることが期待されます。
- 要介護1以上の認定が必要
- あくまでも介護施設なので治療の必要がない方
料金体系
老健の料金は、介護保険でカバーされる部分と自己負担部分があります。
自己負担分は、利用者の所得や介護度によって異なります。また、日常生活に必要なサービス(食費や居住費など)も別途自己負担となり、施設ごとに異なるため、入所前に詳細な料金プランを確認することが重要です。
また、介護サービス以外にも、電気料金、レンタル品など利用する場合は追加費用が発生する場合があります。
平均的な費用の目安
①ユニット型個室の場合
月額約10万円~15万円程度。
介護度や所得に応じて異なるが、個室のため居住費が高めに設定されています。
②従来型多床室の場合
月額約7万円~12万円程度。
多床室のため、ユニット型個室に比べて居住費が抑えられているのが特徴です。
介護保険負担限度額について
利用者の年金や資産に応じて、介護保険負担限度額認定が適用される場合があります。
この認定を受けることで、食費や居住費が減免される可能性があります。
特に低所得者の場合、自己負担額が大幅に軽減されることがあり、月額負担が数千円から数万円程度に抑えられる場合もあります。
申請には、利用者の所得証明や資産状況の確認が必要となるため、事前に役所や施設の担当者に相談しておくことが推奨されます。
- 居室や利用者の経済状況によって費用は大きく異なる
- 介護保険負担限度額認定の確認と申請を忘れずに
施設の種類と選び方

従来型とユニット型の違い
老健には従来型とユニット型の2つのタイプがあります。従来型は大部屋での生活が中心で、集団的なケアが行われます。
一方、ユニット型は少人数の個別ユニットでの生活を提供し、よりプライバシーを重視したケアが可能です。
- 従来型は多床室が中心で居住費が安価
- ユニット型は個室でご自宅に近い環境であるが居住費が従来型に比べて高い
働いている専門職
老健では、医師、看護師、介護福祉士、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)など、多職種が連携してケアを提供しています。
医師が常駐していますが、医療ケアが必要な際は、外部の医療機関と連携して対応することが一般的です。
- 医師が常駐している
- リハビリスタッフが多く在籍している
施設でのリハビリと医療対応

老健での医療 – できること、できないこと
老健では、基本的な医療ケアやリハビリを受けることができますが、高度な医療処置や緊急対応は限られています。
例えば、慢性疾患の管理や軽度の医療行為(点滴や薬の管理など)は可能ですが、施設の体制によっては、経管栄養、喀痰吸引、在宅酸素などの受け入れが難しい場合もあります。
また、重篤な状態や急変時には、外部の病院への搬送が必要となることがあります。
老健はリハビリと在宅復帰支援を主な目的としています。
- 医療依存度の高い方は入所が難しい場合がある
- 特養は薬の管理、軽微な処置、点滴管理などできることが限られる
入院した場合の対応
老健に入所中に入院が必要になった場合、病院と連携し、適切な治療が受けられるよう手配が行われます。
入院期間中は老健の利用が一時停止となり、退院後の再入所が可能ですが、状態や施設の状況によっては再調整が必要になることもあります。
- 入院すると退所になる
- 入院治療が終わり次第、状態に応じて再入所調整を行う
リハビリの有無とその内容
老健の最大の特徴は、リハビリが充実している点です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別に対応し、利用者の身体機能の回復をサポートします。
リハビリの頻度や内容は、個々の状態に合わせて計画され、在宅復帰を目指すためのプログラムが組まれます。
- リハビリの頻度や内容は個々の状態に応じて決まる
- 退院後の活動量を向上させるため短期集中リハビリもある
生活の質を高めるための支援

外出・外泊の状況
老健では、入所者が積極的に外出や外泊をすることができるようにサポートしています。
ただし、コロナ禍によって外出や外泊には最善の注意を払っています。施設によっては一部制限をされているところもありますので、事前の確認が必要です。
リハビリや医療ケアの一環として外出が推奨されることもありますが、頻度や範囲は施設の規定や利用者の健康状態に依存します。
- 積極的に外出、外泊支援をしている
- コロナ禍により施設の判断で対応は異なる
入所期間の制限
老健は原則として在宅復帰を目指す施設であるため、入所期間に制限が設けられる場合があります。
一般的には3ヶ月から6ヶ月が目安とされますが、状態に応じて延長が認められることもあります。
最終的には、利用者の健康状態やリハビリの進捗次第で判断されます。
- 他の高齢者施設と異なり入所期間がある
- 一般的には3ヶ月から6ヶ月
看取りの対応
老健では基本的に在宅復帰を目指しますが、状態によっては看取りの対応が行われることもあります。
しかし、特養やホスピスほど看取りケアに特化しているわけではないため、病院や他のケア施設との連携が求められることが多いです。
- 看取り対応も可能
- 看取りには家族の理解と協力が必要
受診対応と診療科の受診
老健では、基本的には常駐医師が対応しますが、施設内で診療できる診療科には限りがあります。
必要に応じて外部の病院での診察を受けることもあり、その際は家族のサポートが必要となる場合があります。
- 専門的な治療が必要な場合は受診が必要
- 受診対応については施設ごとに対応が異なる(施設対応、家族対応)
家族との協力体制

家族の役割
老健での家族の役割は重要です。
入所者のケアに対する協力や、施設とのコミュニケーションを通じて、より良いケアが提供されるよう努めることが求められます。
また、家族が定期的に施設を訪問し、入所者の状況を確認することも推奨されます。
- 入居者にとって家族との時間は重要
- 施設職員、家族とが協力して入所者を支える
ケアの計画とトラブルへの対応
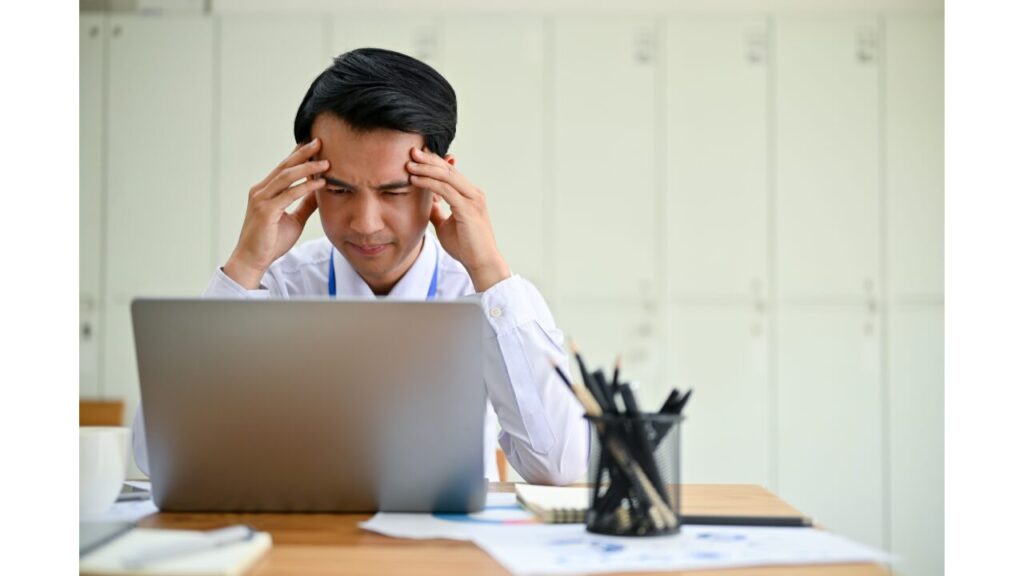
ケアプランとカンファレンス
老健では、個々の入所者に合わせたケアプランが作成されます。
定期的にカンファレンスが開催され、医師やケアスタッフ、家族が集まり、入居者の状態やケア内容について話し合います。
このプロセスを通じて、最適なケアが提供されるよう努めます。
- カンファレンスは入居者の状況を共有できる場
- 必ず参加し施設への要望を伝えよう
トラブルの事例と対応
老健で発生しうるトラブルには、医療対応の遅れやケアの質に関する問題、他の入所者とのトラブルなどがあります。
これらは、スタッフとのコミュニケーションや迅速な対応が求められます。
施設を選ぶ際には、トラブル対応の方針や過去の事例についても確認しておくことが重要です。
- トラブルがゼロの施設は無い
- トラブルに対して真摯に対応する施設かどうか見極める
入居者の生活環境とプライバシー

携帯持ち込みとWi-Fi環境
老健では、携帯電話の持ち込みが可能な場合が多く、利用者が家族と連絡を取りやすい環境が整えられています。
しかし、Wi-Fi環境は施設によって異なるため、事前に確認しておくことが推奨されます。
- 携帯は持ち込み可能だが、管理の責任までは施設に求められない
- ポケットWi-Fiが持ち込みも可能な場合もある
カメラの設置について
プライバシーや他の入所者との関係を考慮すると、カメラの設置には慎重な対応が必要です。
施設によっては、カメラ設置が制限される場合もありますので、事前に施設に相談し、許可を得ることが必要です。
ただし、近年ではICT化が進み、居室に見守りカメラを設置する施設も増えています。その場合にはプライバシー保護の観点から入所者、家族の同意のもと取り付けを行います。
- 従来型とユニット型でプライバシーの観点は異なる
- 施設の体制として、見守りカメラが整備されているところもある
まとめ
老健は、施設で提供できる範囲の医療とリハビリを通じて在宅復帰を目指す施設として、重要な役割を果たしています。
本記事を通じて、老健についての理解が深まり、施設選びの参考となれば幸いです。
次回はさらに別の高齢者施設についてご紹介しますので、ぜひご期待ください。
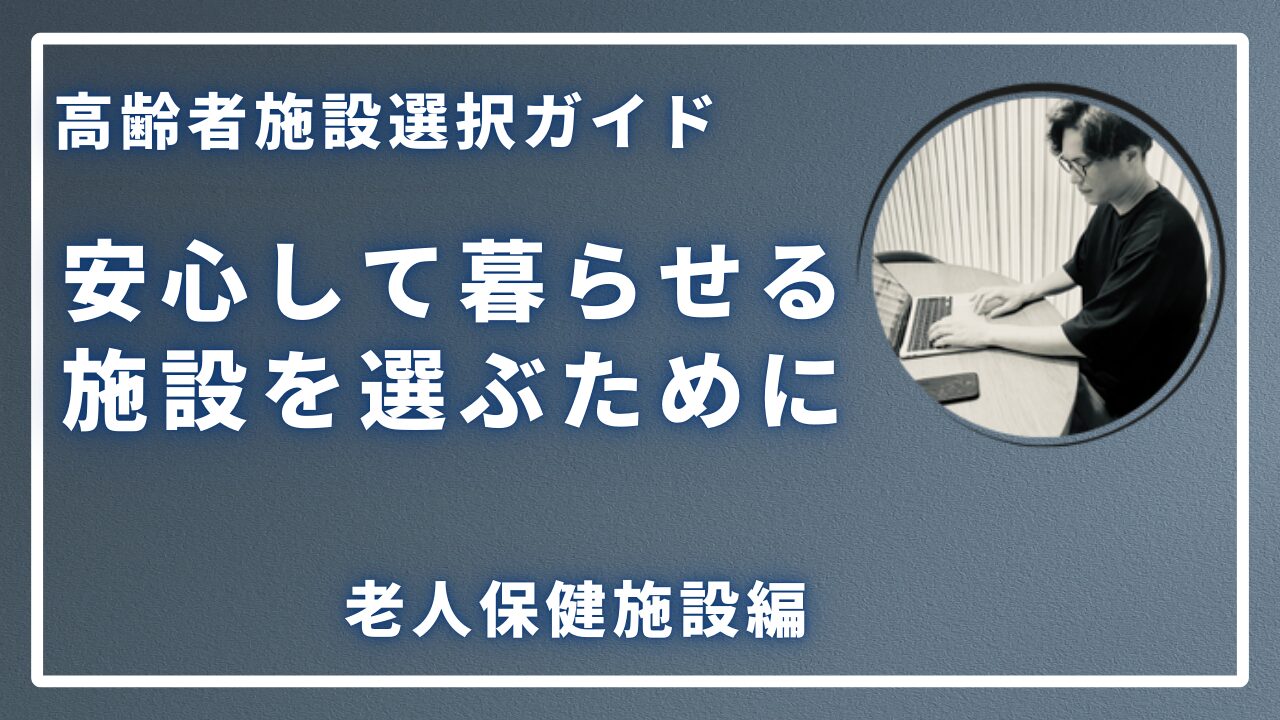
コメント