はじめに

最近、兵庫県知事の斎藤元彦氏に対するパワーハラスメントの疑惑が大きな話題となりました。この問題は、彼が職員に対して厳しい態度を取る中で生じたとされています。
このような事件は、他人事ではなく、私たちの職場でも起こり得る問題です。私自身もこの報道を目にして、同じように苦しんでいる方が他にもいるのではないかと考えさせられました。
また、私たちの職場でも最近、ハラスメントが問題となる出来事がありました。その際、被害を訴えている職員の立場に立って考えることがいかに重要かを痛感しました。
このような背景から、ハラスメントについて深く考え直す必要性を感じ、今回の記事を通じて、職場でのハラスメントの種類や防止策について取り上げることにしました。
ハラスメントは単に一部の問題ではなく、職場全体の健全さに深く関わる重要なテーマです。この記事が、皆さんの職場環境を見直すきっかけになれば幸いです。
1. ハラスメントとは何か

ハラスメントは、他者に対して不適切な言動を行うことで、相手に不快感や恐怖感を与える行為です。
職場におけるハラスメントの主な種類には、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントなどがあります。
厚生労働省はハラスメントを「相手の意に反して不快感や威圧感を与える言動や行為」と定義しています。
パワーハラスメント
パワーハラスメント(パワハラ)は、上司が部下に対して権力を利用して行うハラスメントです。
過度な業務指示や無視、人格否定などが含まれます。日本労働組合総連合会(連合)が行った調査によれば、2021年にパワハラを経験したと答えた労働者は、全体の約27.6%を占めています 。
◆職場でハラスメント被害を受けた率 「パワハラ」27.6%、「セクハラ」8.5%、「マタハラ」1.7%、「ケアハラ」2.1%、「SOGI ハラ」2.2%、「ジェンダー・ハラスメント」4.2%、「コロナ・ハラスメント」3.1%
斎藤知事の行動が、権力を利用して他者を支配し、心理的に圧迫していたかが問われています。
セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動や行為によって相手に不快感を与えるハラスメントです。
厚生労働省のデータによると、職場でのセクハラに関する相談件数は近年減少傾向にあります。
各ハラスメントの相談件数の推移を聞いたところ、セクハラ以外では「件
数は変わらない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」が最も高かった(「件数の
増減は分からない」を除く)。
モラルハラスメント
モラルハラスメント(モラハラ)は、精神的な圧力や攻撃を行い、相手の自尊心を傷つける行為です。
侮辱や無視、嫌がらせが代表的です。特に、長時間労働や過度なストレスが背景にある場合、モラハラがエスカレートしやすいとされています。
労働局に設置されている総合労働相談コーナーへの相談は増加傾向にあります。
日本国内においてモラハラは増加し続けているようです。都道府県の労働局などに設置されている総合労働相談コーナーへの相談は、2007年度で28,335件。2019年度には87,570件と、約3倍に増加しています。
2. 新たに注目されるハラスメントの種類
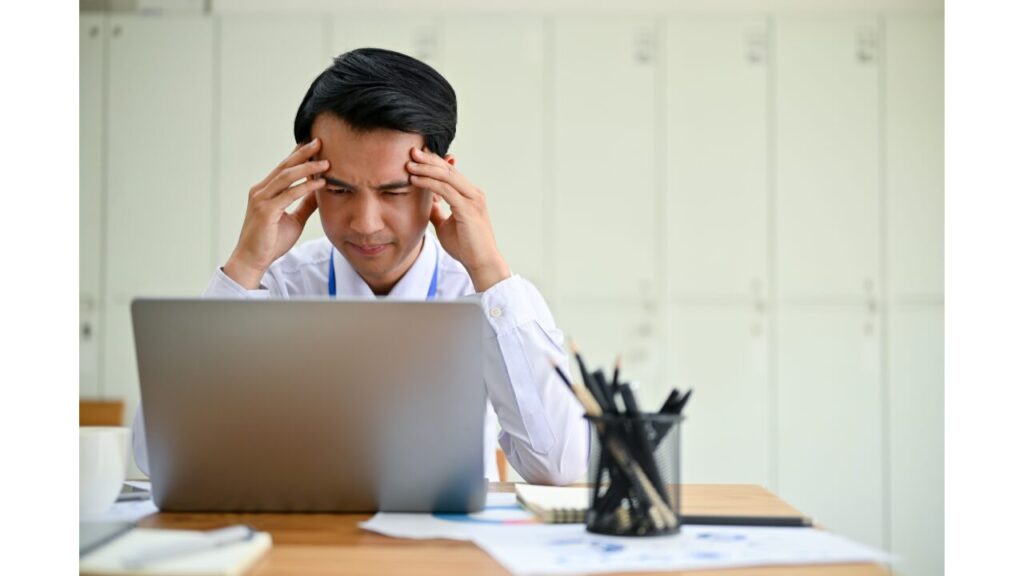
近年、以下のような新たなハラスメントが注目されています。
テクノロジーハラスメント
リモートワークの普及に伴い、テクノロジーを悪用したハラスメントが増加しています。
特に、仕事時間外にチャットやメールを送ることで、相手のプライベートな時間を侵害する「テクノロジーハラスメント」が問題視されています。
インターネットを通じたハラスメントは、物理的な距離があっても相手に深刻なダメージを与えることがあります。例えば、遠隔操作での監視や、過剰な連絡がこれに該当します。
エイジハラスメント
エイジハラスメントは、年齢に基づく差別や偏見に基づくハラスメントです。
特に若年層や中高年層に対する偏見が含まれます。内閣府の調査では、高齢者の約4分の1がエイジハラスメントを経験したと報告しています 。
年齢を理由に業務の幅が狭められたり、昇進の機会が奪われるケースが多く見られます。
年齢差別の経験について、内閣府が高齢者にアンケートを行ったところ、約4分の1にあたる人数が「年齢が原因で実際に困った経験がある」と答えています。加えて、すべての世代を対象にしたアンケートでは、半数以上の方が高齢者に対する差別や偏見があると感じていることが示されました。
ワークハラスメント
ワークハラスメントは、職場内での役職や業務内容に関連した嫌がらせや差別的な行為を指します。
特に、業務量の不均衡や不公平な評価が原因となることが多いです。日本経済新聞が報じたところによれば、最近では過剰な業務量を強いる「過労ハラスメント」や、正当な評価を得られない「昇進ハラスメント」も問題視されています 。
3. 職場でよくあるケース

職場では、ハラスメントが表面化しにくいことが多々あります。
例えば、上司からの圧力や、同僚からの陰湿な嫌がらせがエスカレートするケースが挙げられます。特に、パワハラは表立って指摘されることが少なく、被害者が声を上げづらい状況を生み出します。
ある調査によれば、職場でハラスメントを経験した人の約60%が、誰にも相談せずに問題を抱え込んでいるという結果が出ています 。
◆「ハラスメントを受けても誰にも相談しなかった」ハラスメント被害経験者の43.2%
◆ハラスメントを受けても誰にも相談しなかった理由
1位「相談しても無駄だと思ったから」2位「相談するとまた不快な思いをすると思ったから」
4. 自分が加害者になっているかもしれないケース

ハラスメントは、時として無意識に行われることがあります。例えば、部下に対しての厳しい指導が、相手にとってはパワハラと受け取られる場合があります。さらに、軽い冗談のつもりが、相手にとってはセクハラやモラハラと感じられることもあります。厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止マニュアル」では、上司が部下に与える心理的な影響を認識し、慎重な言動が求められると指摘されています 。
斎藤知事自身が、自分の行動がパワーハラスメントとして受け取られるとは認識していなかった可能性も考えられます。リーダーシップを発揮しようとする一方で、知らず知らずのうちに周囲に圧力をかけてしまっているケースとして考察することができます。
5. 被害にあった場合の対処法

ハラスメントの被害にあった場合、まずは信頼できる同僚や上司に相談することが重要です。
また、企業のコンプライアンス窓口や、労働組合、外部の専門機関への相談も考慮すべきです。証拠を集めるために、メールやメモを残しておくことも有効です。
陰湿なパワハラほど、証拠に残りづらいもの。パワハラの「言った言わない」の問題は、証人尋問で決着がつくケースもあります。記憶があり、かつ、客観的な事情に整合すると裁判所に示すにも、当時の日記やメモは大切。労働者側で準備できる証拠は、最大限集める努力をしてください。パワハラの証拠となるメモは、日時・場所・態様を具体的に書くのが大切です。
6. ハラスメントをしないための対策

ハラスメントを防ぐためには、自分の言動に対して常に意識を持つことが大切です。
相手の気持ちを尊重し、不快感を与える可能性のある言動は控えましょう。また、定期的な研修や学習を通じて、自身の知識をアップデートすることも重要です。
企業が定期的に行うハラスメント防止に取り組んでいる企業は、労働者の意識向上に大きく寄与しており、厚生労働省の調査によれば、問題発生率の低下が報告されています 。
ハラスメントを受けた経験の割合を、勤務先が行っているハラスメントの予防・解決のため
の取組評価別にみると、パワハラにおいては、勤務先が「積極的に取り組んでいる」と回答
した者で、ハラスメントを経験した割合が最も低く(15.2%)、「あまり取り組んでいない」と回答
した者で最も高かった(35.1%)。
斎藤知事の事例を踏まえ、どのようにすればリーダーがハラスメントを回避できるのかを考察することも有益です。感情的な反応をコントロールする方法や、職員との健全なコミュニケーションの重要性を強調することができます。
7. 職員を守る職場環境の構築

企業は、ハラスメントが起こらない環境を整える責任があります。
具体的には、定期的なハラスメント防止研修の実施や、相談窓口の設置、透明性のある処罰制度の導入などが挙げられます。
また、上司が部下に対して適切な指導を行い、信頼関係を築くことも重要です。経済産業省のガイドラインでは、ハラスメント防止のための具体的な行動指針を示し、全従業員が積極的に取り組むことを推奨しています 。
8. 専門機関や相談窓口

ハラスメント問題に直面した際には、以下のような専門機関や相談窓口を利用することができます。
- 厚生労働省の「パワーハラスメント相談窓口」
- 各都道府県の労働局
- 労働組合
- 民間の労働相談機関
これらの機関は、匿名での相談も可能な場合が多く、気軽に利用できる環境が整っています。
9. 上司や部下からのハラスメント

上司だけでなく、部下からのハラスメントも問題となることがあります。
部下からの嫌がらせや無視、誹謗中傷なども同様に深刻な問題です。これに対しては、職場全体での対策と、コミュニケーションの改善が求められます。
特に、双方向のコミュニケーションが重要であり、部下の意見を尊重しつつも、上司としての立場を明確にすることが大切です。
まとめ
ハラスメントは職場において非常に深刻な問題です。被害を防ぐためには、個々人の意識改革と、職場全体の環境改善が必要です。
自身が加害者にならないよう注意し、被害にあった場合には適切な対応をとることで、安心して働ける職場を作りましょう。
企業としても、ハラスメント防止のための取り組みを強化し、労働者が安心して働ける環境を提供することが求められます。

コメント