本記事は、2027年見込みの「育成就労制度」を介護の視点でやさしく解説します。
転籍「2年」案の背景、3年で特定技能1号レベルまで育てる骨子、就労1年後の待遇向上策(介護は処遇改善加算+キャリアプラン案)、訪問系サービスの最新ルール、導入メリットと課題、90日ロードマップまで、現場が今知るべきポイントを1本にまとめました。
はじめに|まず「結論」と最新ポイント

育成就労制度は「人を受け入れる」から「人を育てる」へ発想を切り替える新しい仕組みで、介護分野では転籍の制限が“当面2年”という案で議論が進んでいます。
制度の骨子は「3年間で特定技能1号レベルまで育てる」ことで、就労開始から1年後には待遇を上げるための手立てが求められます(介護は処遇改善加算の取得とキャリアプランの作成を検討中)。
政府は2025年12月に分野別の運用方針を決める見込みで、2027年の制度開始を目指す流れです。現場の意向調査では、受け入れを増やしたい施設が過半数で、人材不足への対応と定着に期待が集まっています。
参考資料:公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 令和6年度外国人介護人材に関する実態調査報告書
いま押さえる3点
①転籍制限「介護は2年」案
介護は、日本語の習得と専門技術の定着に時間がかかること、地方から都市部への人材流出を防ぐ必要があることを理由に、転籍の制限期間を“当面2年”とする案が示されています(原則は1年、分野ごとに1〜2年で設定)。最終決定は2025年12月予定です。
②制度の骨子「3年で特定技能1号レベル」「1年後は待遇向上」
育成就労は3年間の就労・学習で特定技能1号相当まで引き上げる設計です。就労開始1年後には待遇向上策が必要で、介護については賃金表だけでなく「処遇改善加算の取得+個々のキャリアプラン作成」を求める方向で検討されています。
③現場の温度感「受け入れ拡大の意向が過半」
全国老人福祉施設協議会の調査では、回答施設の45%がすでに外国人介護人材を受け入れ、そのうち57%が「今後さらに増やしたい」と回答しています。理由は「人材不足への対応」や「将来に備えた採用」が中心でした。
育成就労制度とは?(やさしく全体像)
育成就労制度は、これまでの技能実習で指摘された「転籍不可による人権侵害」などの問題を改め、「きちんと育てて、段階的にキャリアを上げる」ことを柱にした制度です。
特定技能制度と連動し、受け入れ分野ごとに「3年間で特定技能1号レベルに到達する道筋」を示します。制度づくりは有識者会議で詰められ、分野別の運用方針は2025年12月に政府が決定見込みです。
制度の目的と基本設計(「受け入れ」から「育成」へ/3年の育成フェーズ/人権保護を強化)
この制度の目的は、外国人材を単に数合わせで受け入れるのではなく、3年の育成期間で確かな技能と日本語力を身につけてもらい、特定技能1号へスムーズに移行できる人材を増やすことです。
基本設計では、入国時点で最低限の日本語を確認し、就労1年以内に日本語と基礎技能の評価を受け、移行前には特定技能1号の評価試験(または技能検定3級等)と日本語A2相当(JLPT N4目安)をクリアする道筋を示しています。
さらに、転籍の仕組みを整え、暴力やハラスメントなどがあれば本人の意向で職場を変えられるようにし、人権保護と支援体制を強化します。
参考資料:出入国在留管理庁 第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)について 令和7年9月17日
施行時期の見込みと今後の決定プロセス(有識者会議→12月閣議決定見込み)
今後は、法務省・出入国在留管理庁の有識者会議で分野別の運用方針(たとえば転籍の年限や評価のタイミングなど)を最終調整し、2025年12月に政府として基本方針を決定する見込みです。
制度の施行は2027年頃が想定されています。したがって、介護現場は「いつ・何を準備するか」の工程表(日本語教育、OJT設計、処遇改善加算の取得体制、キャリアプランの雛形)を前倒しで整えるのが現実的です。
介護分野のキモ(転籍・待遇・日本語)

転籍は「原則1年」だが介護は当面「2年」案の理由(日本語・専門技術の習得と地方から都市部への過度な流出防止)
介護では、最初の2年間はむやみに職場を変えにくい設計が検討されています。
理由は、利用者と安全に関わるための日本語力やケアの専門技術を身につけるのに時間がかかること、そして地方から賃金の高い都市部へ人材が短期間で流れすぎると地域の介護が回らなくなる恐れがあるためです。
福祉新聞の報道では、転籍の制限は全体の原則「1年」だが、介護を含む8分野は当面「2年」案とされ、年内(2025年12月)に政府の方針が決まる見込みと示されています。
この方向性は入管庁の有識者会議の審議結果に沿った内容です。
参考資料:出入国在留管理庁 第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)について 令和7年9月17日
就労1年後の「待遇向上策」:介護は昇給義務でなく「処遇改善加算取得+キャリアプラン」案
就労から1年がたった頃には、待遇を上げるための具体策が必要になります。
介護は報酬が公定価格で決まるため、機械的な「必ず昇給」を義務づけるよりも、まずは処遇改善加算をきちんと取り、個々の職員の成長に合わせたキャリアプランを作る方向で検討されています。
処遇改善加算は、賃金アップの配分ルールやキャリアパス要件(職位・職責と賃金体系、資質向上の計画など)を整えて申請し、職場環境の改善にも使える公的な仕組みです。
求められる日本語・技能レベル(特定技能1号相当まで育成)
育成就労は「3年間で特定技能1号レベルまで育てる」ことが柱です。
つまり、現場で一人前として働ける技能と、日本語はおおむねA2相当(JLPTでいえばN4目安)以上をねらいます。分野共通の試験方針や資料では、評価の節目を設定し、育成フェーズの終盤で特定技能1号への移行に必要な基準(技能評価・日本語)を満たしていく道筋が描かれています。
介護の特定技能1号ページでも、受入れ条件や運用の考え方が整理されています。
技能実習・育成就労・特定技能の“ちがい”早見表

目的/在留枠/在留期間/転籍の可否と制限/要件(日本語・技能)/監理支援体制を横並び比較(表)
| 項目 | 技能実習(現行・順次廃止へ) | 育成就労(新制度・2027年想定) | 特定技能1号 |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献(技能移転)+人材受入れ | 「受け入れ」より「育てて定着」を重視(3年でSSW1水準へ) | 人手不足分野で即戦力として就労 |
| 在留期間の考え方 | 1号・2号・3号で最長5年 | 育成フェーズ3年を基本 | 最長5年(更新上限あり、介護は2号なし) |
| 転籍の可否 | 原則困難(例外あり) | 原則1年で可/介護など当面2年案 | 転職可(要手続) |
| 日本語・技能要件 | 実習計画に即した評価 | 段階評価でSSW1相当へ(日本語A2目安) | 技能試験+日本語試験(介護は所定要件) |
| 監理・支援体制 | 監理団体(OTIT等の枠組み) | 監理支援機関(許可制) | 登録支援機関/所属機関の支援義務 |
| 位置づけの関係 | ― | 育成→特定技能1号への移行を想定 | 育成の出口・受け皿 |
出典:制度比較は入管庁の制度比較資料、特定技能1号(介護)の公式ページ、育成就労の審議資料・試験方針に基づく要点の整理。
※表内の「介護は当面2年案」「3年でSSW1へ」「監理“支援”機関」等は有識者会議や福祉新聞報道の範囲で示された2025年9月時点の内容です。最終決定は政府方針の告示・通知をご確認ください。
「特定技能1号」との関係(育成→特定技能へスムーズに移行させる想定)
育成就労のゴールは、特定技能1号として一人前に働ける水準に到達し、同じ事業所や地域で長く力を発揮してもらうことです。
この流れが整えば、採用のやり直しやOJTの重複が減り、利用者にとっても顔なじみの職員が増えて安心につながります。
入管庁の審議資料でも、育成フェーズを終えた人材のスムーズな移行を想定しており、介護分野の公式ページでも事業所ごとの受入れ上限や支援義務など運用のポイントが整理されています。
※ 外国人材の受け入れについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/technical-training-system-2024/
訪問系サービスはできる?|最新ルール整理

現状:特定技能・技能実習の訪問系サービスは要件付きで解禁(2025年施行)。必要書類と事前確認の流れの概略。
2025年4月から、条件を満たす特定技能・技能実習の介護人材は、訪問介護など「訪問系サービス」に就けるようになりました。
技能実習は4月1日、特定技能は4月21日施行です。厚労省は「初任者研修修了」や「概ね1年以上の実務経験」などを前提に、事業所に対して研修の実施、一定期間の同行訓練、本人の意向確認とキャリアアップ計画の作成、ハラスメント相談窓口の設置、緊急時対応(ICT活用を含む)の整備を求めています。
実務の流れは大きく「遵守事項の確認→所管への事前確認→従事開始」という順序です。特定技能では、受入機関が遵守事項を満たしているかを、介護分野の協議会(JICWELS)が事前に確認し、従事前に「適合確認書」を発行します(申請手順・必要書類は同サイトで一覧化)。
技能実習も同様に、該当通知・留意事項に従い手続きを進めます。自治体からも同趣旨の周知・日付が案内されています。
育成就労での扱いは?(施行前のため最終方針待ち。最新の官公庁通知を随時参照)
育成就労は施行前で、訪問系サービスへの従事ルールは最終決定待ちです。
法務省・入管庁の有識者会議で分野別運用方針を詰めており、2025年12月に政府方針が固まる見込みです。
したがって、当面は厚労省・入管庁が公表する告示・通知(介護分野ページ、会議資料、Q&A)を随時確認し、実装時にギャップが出ないよう準備を進めるのが安全です。
受け入れ方式と体制づくり(実務)

受け入れの流れ:育成就労計画の認定/監理支援機関(許可制)との役割分担(案)
育成就労では、1人ひとりに「育成就労計画(期間は最長3年、到達させる技能・日本語水準を明記)」を作り、所管機関の認定を受けることが前提です。
あわせて、従来の“監理団体”は「監理支援機関」に衣替えし、主務大臣の許可制のもとでマッチング、監理・指導、本人支援を担います(無許可では実施不可)。
この枠組みで、現場OJTと日本語学習、評価の節目を計画的に回すのが基本線です。
受け入れ要件チェック:労働条件/生活支援(住居・買い物同行)/日本語教育/介護導入研修/キャリアプラン
はじめに、就業規則や労働条件を書面で明確にし、時間外・深夜・安全衛生の取り扱いを整えます。
次に、住居の確保、移動・買い物の初期支援、日本語学習の場(就業内外)を用意し、介護導入研修とOJTの計画を作ります。
さらに、訪問系に広げる場合は、初任者研修修了・実務経験・同行訓練・ハラスメント相談体制・緊急時対応など、厚労省が求める追加要件を満たします。
最後に、本人の成長段階に合わせたキャリアプランを作って見える化することで、定着と学習を両立させます。
職場づくり:多言語マニュアル・やさしい日本語/夜勤の導入手順(段階訓練)/メンタルヘルス・異文化理解
多言語マニュアルや「やさしい日本語」を活用し、業務手順・連絡方法・緊急時対応を共有します。
夜勤は段階的に導入し、まずは日勤で基本技術とコミュニケーションを固め、つぎに見習い夜勤(先輩の付き添い)、最後に単独配置の可否を評価する流れが安全です。
メンタルヘルス支援や異文化理解の研修も定期的に行い、困りごとの相談ルートを明確にします。
訪問系に踏み出す場合は、厚労省の遵守事項(同行訓練・相談窓口・ICTを含む緊急対応など)を現場ルールに落とし込み、JICWELSの「適合確認」手続を並行して進めるとスムーズです。
導入メリットと課題(介護の現実目線)

メリット:長期雇用・育成の見通し/制度設計の明確化/地域での信頼性向上
育成就労を活用すると、3年間で「特定技能1号レベル」まで計画的に育てる道筋ができ、長く働ける人材を育てやすくなります。
制度の設計(評価の節目、日本語・技能の基準、支援の義務)があらかじめ決まっているため、OJTや研修計画を立てやすく、採用・教育の無駄も減らせます。
地域から見ても「育成前提で受け入れている施設」は信頼感が高まり、家族や紹介元にも説明しやすくなります。これらは、制度の骨子(3年でSSW1水準、A2相当の日本語、試験合格で移行)に裏付けられています。
課題:初期費用・教育負担/日本語・専門技術の習熟時間/地方の人手不足の深刻化リスク
一方で、住居の確保、入国直後の生活支援、日本語学習や導入研修など、初期費用と教育負担は確実に発生します。
介護は対人サービスのため、日本語と専門技術の定着にも時間が必要です。さらに、転籍の仕組みが整うと、賃金格差のある地域間で人材が動きやすくなり、地方の人手不足が悪化する懸念もあります。
こうした「習熟に時間がかかる」「都市部へ流出が起きうる」点は、介護分野の転籍制限が当面2年案とされた理由としても示されています。
老施協データで読む“定着”のツボとつまずき(費用負担・長期帰国休暇・日本語習熟度/トラブルの傾向)
現場データでは、受け入れ施設の約半数が外国人介護人材を活用し、そのうち57%が「さらに増やしたい」と答えています。
背景には人手不足への対応と将来採用の備えがありますが、課題として「経費負担の大きさ」「帰国時の長期休暇」「日本語習熟度のばらつき」も挙がります。離職理由では「他職種への転職」が最多で、「賃金への不満」も続きます。
定着のカギは、生活支援と日本語学習の場づくり、段階的な業務拡大、キャリアプランの可視化にあります。これらは老施協調査と福祉新聞の報道が示す傾向です。
現場の声と最新データ

「受け入れ拡大したい」57%の背景(不足対策と将来採用)
多くの施設が「人手不足の解消」と「将来に備えた採用」を理由に、外国人介護人材の受け入れを増やしたいと考えています。
実際、会員1,837施設の調査で、受け入れ施設の57%が拡大意向と答えました。不足を埋めながら、育成就労で計画的に育て、特定技能へつなげることで、採用のやり直しや教育の重複を減らせる期待が背景にあります。
受け入れ率が高い県・低い県の傾向(奈良・愛知・群馬/秋田・高知・山口)
受け入れが進んでいる県として奈良・愛知・群馬が挙げられ、逆に秋田・高知・山口は低めでした。
地域の事業所数や求人倍率、生活インフラ、賃金水準の違いが影響していると考えられます。地域差を前提に、住居・交通・学習環境など「生活面の下支え」を整えることが、受け入れ拡大の土台になります。
失踪・他職種転職の課題(賃金・定着支援・キャリア設計の必要性)
離職の要因では、他職種への転職が最多で、賃金不満も大きな要素です。短期で辞めてしまうほど、採用と育成のコストは回収できません。
賃金テーブルの見直しや処遇改善加算の活用に加え、日本語・技術の習熟を見える化するキャリア設計、長期休暇の運用ルール、相談窓口の整備など、定着支援をパッケージで行うことが重要です。
これらの傾向は、老施協の定着度調査と福祉新聞の報道に現れています。
よくある質問(FAQ:やさしい言葉で即答)

Q. 育成就労はいつ始まる?→A. 2027年見込み。詳細は2025年12月に政府方針予定。
育成就労は、技能実習に代わる新制度として「2027年ごろの施行」を想定して準備が進んでいます。
分野ごとの細かな運用(たとえば転籍の年限や評価の節目)は、有識者会議の議論を経て「2025年12月に政府方針が固まる見込み」です。
制度の全体像は入管庁の公表資料で示されており、3年間で特定技能1号水準まで育てる考え方が土台です。
Q. 介護はなぜ転籍「2年」なの?→A. 日本語と技術の習得に時間、都市部への流出懸念から。
介護は利用者の安全と信頼が最優先で、日本語のやり取りや専門技術の定着に時間が必要です。
さらに、短期間で都市部へ人材が集中すると地方の介護が回らなくなるおそれもあります。そこで、転籍は全体の原則「1年」方針の中でも、介護など8分野は「当面2年」案とされています(最終決定は12月予定)。
Q. 1年後の昇給は必須?→A. 介護は「処遇改善加算の取得+キャリアプラン作成」を待遇向上策として検討。
就労から1年後は待遇を上げるための手当てが求められますが、介護は公定価格(介護報酬)の影響が大きいため、機械的な昇給義務よりも「処遇改善加算の取得」と「個人のキャリアプラン作成」を組み合わせる案で調整が進んでいます。
Q. 訪問介護はできる?→A. 特定技能・技能実習は要件付きで解禁済。育成就労は最終方針を確認してから。
2025年4月に、特定技能と技能実習の「訪問系サービス」が要件付きで解禁されました(技能実習は4/1、特定技能は4/21)。
初任者研修修了や概ね1年以上の実務経験、同行訓練、相談窓口、緊急時対応など、事前に整えるべき要件があります。育成就労は施行前のため、最終方針が出たら改めて確認してからの対応になります。
Q. 監理団体はどうなる?→A. 監理“支援”機関として許可制での関与に(案)。
新制度では、従来の「監理団体」は「監理支援機関」に衣替えし、許可制のもとで受け入れ事業所と連携して育成・支援・監理を担う方向で整理されています。
育成就労計画の作成・運用、評価の節目、日本語教育の支援などで役割を負う設計です(詳細は年末方針で確定見込み)。
導入ロードマップ(90日プラン)

0–30日:制度方針の把握/人員計画・日本語教育計画/住居確保
まずは最新の政府資料を読み込み、2025年12月に固まる方針のチェックポイントを整理します。
あわせて、来年度の採用人数、夜勤体制、日本語A2(N4目安)到達までの学習計画、入国直後の住居・生活支援(交通・買い物・携帯契約)を確保します。
これにより、育成就労開始後に“最初のつまずき”を防げます。
31–60日:監理支援機関の比較・選定/育成就労計画の設計(OJT・研修・評価)
候補の監理支援機関を複数比較し、手数料・支援範囲・トラブル対応の実績を確認します。
並行して「育成就労計画」を下書きし、OJTの段階(配属→同行→単独)、集合研修(日本語・介護導入・感染対策)、評価の節目(半年・1年・2年)をカレンダーに落とし込みます。特定技能1号への移行に必要な試験と日本語の準備も先に組み込みます。
61–90日:就業ルールと多言語マニュアル整備/初任者研修支援スキーム設計/処遇改善加算の取得体制の点検
就業ルール(休憩・残業・夜勤・相談窓口)をやさしい日本語と多言語で整備し、記名確認の運用まで決めます。
訪問系サービスに広げる想定があれば、初任者研修の取得支援、同行訓練、緊急時対応(ICT連絡)を計画に入れます。
あわせて処遇改善加算の算定体制とキャリアパス要件を見直し、「1年後の待遇向上策」を確実に実行できるよう点検します。
まとめ|“受け入れ”から“育てて定着”へ

ポイント再確認と次のアクション(方針確定=12月、施行=2027年を見据え、今できる準備を前倒しで)
育成就労の要点は、3年間で特定技能1号レベルまで計画的に育てること、介護は当面「転籍2年」案で人材の定着と安全なケアを両立させること、そして1年後の待遇向上策を仕組みとして回すことです。
12月の政府方針で詳細が確定するため、いまのうちに日本語教育・OJT・住居・処遇改善加算体制を前倒しで整えておくと、制度開始時にスムーズに移行できます。
出典(参考情報)
- 福祉新聞(2025/9/22)「育成就労、介護の転籍制限2年」
- 福祉新聞(2025/9/12)「外国介護人材『受け入れ増やしたい』全国老施協が調査」
- 法務省・出入国在留管理庁:育成就労制度 有識者会議・制度概要資料
- 厚生労働省:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事に関する通知(2025年施行)
- JICWELS:特定技能の訪問系サービス「適合確認」手続の案内
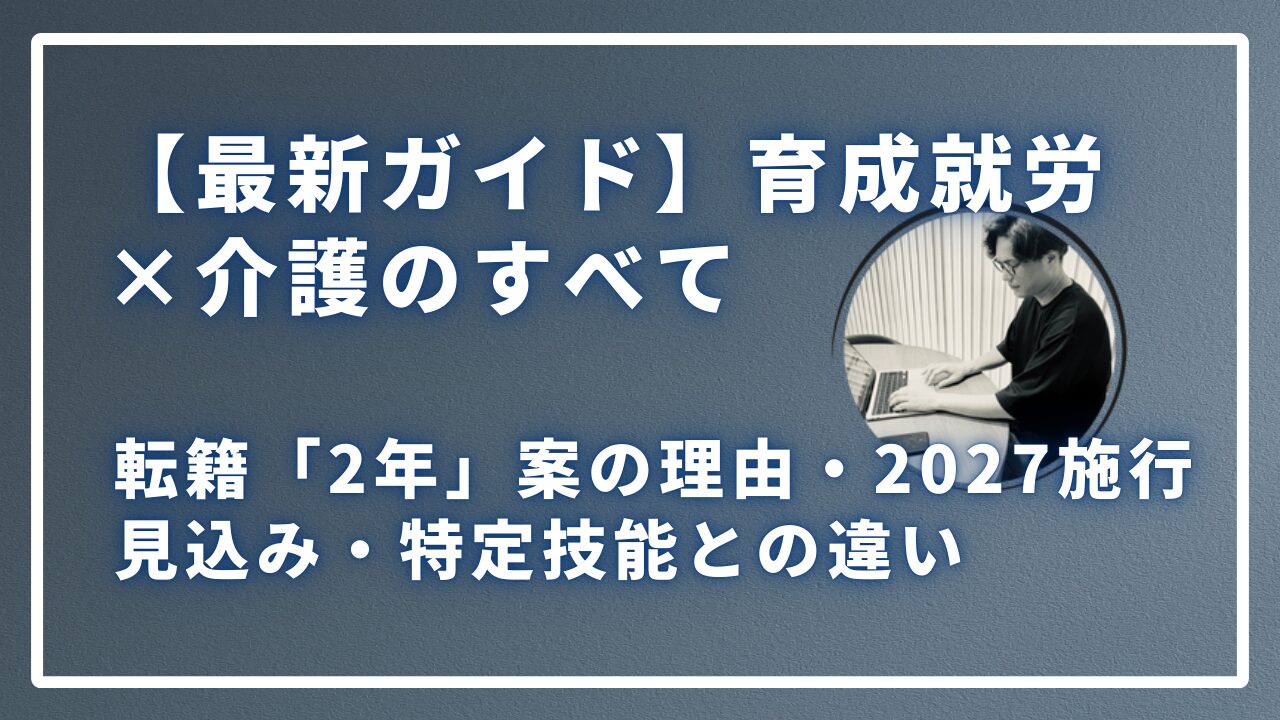
コメント