介護の現場で「何から話せばいい?」「どこまで応じるべき?」と迷わないための実務ガイドです。今日から使える7ステップ、使い回せる台本、施設・通所・訪問での事例別の型、そして正当な苦情とカスタマーハラスメント(カスハラ)の線引きを、国際規格(ISO 10002)と公的資料(厚生労働省・法令等)に沿って整理しました。困ったときの公式の相談先、記録の保存期間まで一気に分かります。
はじめに|この記事で分かること

読者の悩み(すぐ使える型がほしい/線引きを知りたい)
介護のクレーム対応は、「何から話せばいいか」「どこまで応じるべきか」で迷いがちです。
本記事は、今日から使える“話し方の型”と、正当な苦情とカスタマーハラスメント(理不尽な要求)の線引きを、一つの流れで使えるように整理します。
厚生労働省が示すカスタマーハラスメントの考え方(要求内容の妥当性と、手段・態様の相当性)に沿って判断できるようにしたうえで、施設・訪問介護で役立つ例文と記録の取り方まで網羅します。
本記事のゴール(迷わず動ける手順と台本を持つ)
ゴールは二つです。①一次対応の7ステップ(傾聴→共感→事実確認→謝罪の使い分け→提案→引継ぎ→フォロー)を“台本つき”で身につけること、②苦情が解決しないときに、事業所・自治体・国保連・運営適正化委員会など外部の正規ルートへ適切に繋げられることです。
これは各都道府県の運営適正化委員会や国保連の苦情相談制度として整備されており、介護現場を一人にしない仕組みが制度的に用意されています。
用語整理|クレーム・苦情・カスハラの違い

クレームとは(期待との差から生じる不満)
クレームは「期待と実際がズレた」ことで生まれた不満の表明です。
介護サービスは人が人を支えるため、説明のズレや受け止め方の差が起きやすく、満足度に影響します。一般の品質規格でも、クレーム(complaint)は“製品・サービスへの不満の表明”として扱われ、組織は受け止め・是正・再発防止までを含む対応プロセスを整えます。
送迎時間の遅れ、連絡ミス、言葉遣いなど、事実確認と説明で改善できるものが多く、台本に沿った初動と記録で早期に収まります。
まずは“不満の中身”を落ち着いて受け止め、事実を確かめ、改善策と期限を示すのが基本です。
苦情とは(改善の要望や申し出)
苦情は、サービスを良くするための「正式な申し出」です。
介護分野では、苦情を事業所が適切に受け付け、解決に努める責務が社会福祉法で定められ、第三者機関(運営適正化委員会)や国保連の相談窓口も整備されています。
事業所の窓口で解決しにくい場合、都道府県の運営適正化委員会が助言・調整を行い、国保連でも介護サービスの苦情相談を受け付けています。
「苦情は改善の入口」。遠慮なく正規ルートで受け、事実確認→是正→再発防止までを記録に残しましょう。
カスハラとは(要求の妥当性や態様が常識から外れる行為)
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、“要求の中身”や“やり方”が常識から外れ、職員の就業環境を害する行為です。
厚生労働省は「要求内容の妥当性」と「その実現手段・態様の相当性」を軸に定義づけ、暴言・過度の長時間拘束・度重なる威嚇・不当な金銭要求などを例示しています。
契約外の家事を強要する、名乗らず罵倒し続ける、謝罪や担当変更を過度に迫る、などは該当し得ます。対応は“複数名対応・記録・時間制限・窓口一本化・外部連携”が原則です。
正当な苦情と区別し、職員を守る仕組み(初動マニュアル・相談窓口・弁護士連携)を事前に整えておきましょう。
判断の軸(内容の妥当性/手段・態様の相当性)
線引きは「何を求めているか」と「どう求めているか」の2軸で行います。
求める内容が法令・契約や合理性から外れていないか、要求の伝え方が社会通念上妥当かを見れば、対応の優先度やエスカレーション(上位者への引き継ぎ)の必要性が明確になります。
内容が妥当でも、深夜の執拗な電話や1時間以上の拘束、録音拒否の怒鳴り込みは“態様が不当”。逆に態様が丁寧でも、契約外の家事や不当な金銭要求は“内容が不当”。
どちらか一方でも不当なら、複数対応・記録・時間制限・上司同席・必要に応じ外部機関へ繋ぐ判断を。厚労省のカスハラ手引と企業向けマニュアルは現場の基準づくりに有用です。
早見表(現場掲示用のミニ表)
スタッフ全員が同じ判断になるよう、該当例と初動対応を一枚にまとめて掲示しましょう。
交代制の現場では、「誰が受けても同じ対応」を徹底することが、早期収束と職員保護に直結します。
具体例(ミニ表サンプル):
この表は厚労省の定義・考え方(内容の妥当性×手段・態様の相当性)に沿って作ると、現場の迷いが減ります。
【即実践】介護のクレーム対応7ステップ

①傾聴(最後まで遮らず聞く)
最初の数分で結果が大きく変わります。相手の話を遮らず、一度で最後まで聞き切ると、感情が落ち着き、事実確認に進みやすくなります。
メモは「要点のみ」を静かに取り、被せ質問は控えます。傾聴はどの業界でも有効とされ、苦情対応の国際規格(ISO 10002)でも“受け止め→記録→検証”の最初の動作として重視されています。

私も過去にメモを取ることに集中しすぎて、話を聞いてもらえなかったという印象を与えてしまった失敗談があります。
②共感・謝意(気持ちを受け止めた一言)
「教えてくださり助かります」「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません」など、相手の気持ちを先に受け止めると、対話の姿勢が伝わります。ここで事実の是非を論じないのがコツです。
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策でも、初動での受け止めと冷静な応対を推奨しており、以降の線引き・エスカレーション判断が行いやすくなります。



「謝ったら過失を認めたことになる」と言われますが、ここではあくまで相手に不快な思いをさせてしまったことをお詫びしているのであって、過失を認めたことにはなりません。
③事実確認(人・物・時間・場所・証拠をそろえる)
「いつ・どこで・誰が・何を・どうした(しなかった)」を、相手の語りと記録・現場確認で突き合わせます。写真・ナースコール履歴・連絡帳・勤務表など、確認できる証拠は一覧化して保全します。
苦情の受付から経過までを記録することは、各国保連や自治体の要領でも明示されています(相談・苦情記録票の保存)。



事実確認の資料や職員への聞き取りなどの証拠は、誠意を持って可能な限り集めた方が良いです。いい加減で曖昧な対応は逆効果。
④謝罪の使い分け(全面/部分/遺憾の表明)
過失が明らかなときは全面的に謝罪します。過失が一部のときは、その部分を明確に謝罪します。過失が不明でも、不快な思いをさせた事実には「遺憾」を表明できます。いずれも、原因の仮説を断定せず、調査の手順と期限をセットで伝えます。
過剰な約束はトラブルの元になるため避けましょう。謝罪と是正・再発防止を分けて説明する整理はISO 10002のプロセスにも合致します。



「◯月◯日までに回答します」とはっきり伝えておきましょう。後日「◯◯の件ですがどうなりましたか?」と相手から聞かれるようではダメです。
⑤解決策・代替案(期日・責任者・再発防止も明記)
「誰が・いつまでに・何をするか」を具体的に示し、再発防止策は“仕組み化”まで踏み込みます(例:連絡様式の統一、ダブルチェック導入、掲示ポスターの更新)。提案は1案に固執せず、代替案も提示し、相手の合意を文面に残します。
苦情対応のよい実務は、改善と見直しのサイクルに組み込むことが国際規格で推奨されています。
⑥引き継ぎ基準(いつ上司/医師/弁護士に上げるか)
次のいずれかに当てはまれば即エスカレーションです。
①安全や健康に関わる恐れがある
②高額な賠償や契約変更が関わる
③暴言・威嚇・長時間拘束など態様が不当
④職員へのハラスメントの疑い
組織の窓口を一本化し、必要に応じて医師・弁護士・警察・市町の介護保険課・福祉課につなぎます。これらの外部機関は制度として整備されています。
⑦フォローアップ(約束の期日に結果を伝える)
合意した期限までに結果を報告し、相手が納得したかを確認します。未完了なら理由と新期限を先に伝えます。
完了後は、事例の要点と再発防止策をチームで共有し、記録は所定期間保存します。この“締め”が次のトラブルを防ぐ最短ルートです。
例文・台本|そのまま使えるフレーズ集


初期対応の第一声(電話/対面)
電話:「お電話ありがとうございます。◯◯事業所の△△でございます。お話を最後までうかがいますので、どのような点でご不快な思いをされたか、順にお聞かせください。」
対面:「本日はお時間をいただきありがとうございます。ご心配とご不便をおかけし失礼いたしました。まず事実関係を確認するため、時系列で教えていただけますか。」
謝罪の言い回し(避ける言葉「でも/だって/ですから」)
全面的な謝罪:「このたびは当方の不手際によりご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。責任者◯◯が本日中に是正策をご案内します。」
部分的な謝罪:「本件について、連絡が遅れた点は当方の不備です。申し訳ありません。原因は調査中ですが、まず連絡体制の見直しを進めます。」
遺憾の表明(過失が不明な段階):「不快なお気持ちにさせてしまったことは大変遺憾に存じます。事実を確認し、必要な対応を◯日までにご連絡します。」
事実確認の聞き方(誤解をほどく質問)
- 「最初に気づかれた時刻と、そのとき誰がそばにいたかを教えてください。」
- 「どの物品がいつ無くなったのか、思い出せる範囲で大丈夫です。」
- 「当事者のやり取りで覚えている言葉はありますか。」
- 「こちらの記録(連絡帳・ナースコール等)と突き合わせて確認してもよろしいですか。」
提案・代替案の伝え方
「本日中に◯◯の点検と△△の二重確認を実施します。責任者は□□です。完了は◯/◯を予定しています。
別案として、終了までの間はご家族への連絡方法を固定(例:18時に日次連絡)することもできます。ご希望に沿う形を選んでください。」
「今回の件は、連絡様式の統一で再発を防げます。来週から全ユニットで同じ書式に切り替えます。」
完了報告とお礼の一言
「お約束の◯/◯までに対策を完了しました。点検記録と新手順をお渡しします。ご指摘のおかげで改善が進みました。ありがとうございます。1か月後に状況を確認し、結果をご連絡します。」
よくある事例と対応の型(施設・通所)


職員の言葉遣い・態度への不満
まず「最後まで聞く→気持ちを受け止める→事実を確かめる→対応案を示す」の順で進めます。
言葉の受け取り方は人によって違うので、伝え方の標準フレーズを作り、全員が同じ言い回しで対応できるようにします。完了後は、接遇フレーズ集の更新や朝礼ロールプレイに反映します。
苦情の受け止め→記録→是正→再発防止という流れはISO 10002の推奨プロセスと一致します。
転倒・けがなどの事故
安全の確認が最優先です。応急対応→医療連絡→家族連絡→現場保存→記録→原因分析→再発防止の順で進めます。
床の滑り・浴室・濡れた通路などは転倒の起こりやすい環境なので、滑り止め床材や清掃手順の見直し、雨天時の動線表示など具体策まで落とし込みます。
厚労省の転倒災害資料でも、浴室等の滑り・濡れた通路・清掃後の乾燥確認などの対策が示されています。
私物の紛失・破損
まず事実関係を整理します(いつ・どこで・誰が・何を)。動線や保管場所、持ち出しの有無を突き合わせ、記録・伝票・防犯カメラ等の証跡を保全します。
説明は推測で断定せず、期限と責任者を明らかにして調査と代替案を提示します。苦情受付から経過・結果までの記録と保存は、各団体の苦情対応要領・運営基準でも求められる基本です。
連絡・説明不足(連絡ミス、伝言の齟齬)
「誰が・いつ・何を・どの手段で」伝えるかを一枚にまとめ、書式と手順を統一します。
重要な連絡はダブルチェック(送信者と確認者)にし、家族連絡は時間帯・窓口を固定します。
未解決や長期化が予想される場合は、外部の正規ルート(運営適正化委員会、市町の介護保険課・福祉課)に繋げられる体制を案内できるようにします。
料金・追加費用への不満
重要事項説明書と契約書の内容に沿って説明し、追加料金の根拠を文書で提示します。
説明前の合意が曖昧な場合は、書式を見直し、料金・加算・提供範囲・禁止行為を分かりやすい言葉で明記します。介護保険事業者の運営基準では、契約・重要事項の説明や記録保存が求められ、実地指導でも確認されます。
共通フォーマット(事実→影響→是正→再発防止→期日→責任者)
全パターンで、報告・説明の型を統一します。
- 事実:いつ/どこで/誰が/何を
- 影響:利用者・家族・他者への影響
- 是正:今日すぐ行うこと
- 再発防止:書式・手順・教育・環境の見直し
- 期日:完了日・経過報告日
- 責任者:実施責任者・承認者
訪問介護のクレーム対応(在宅ならではの注意点)
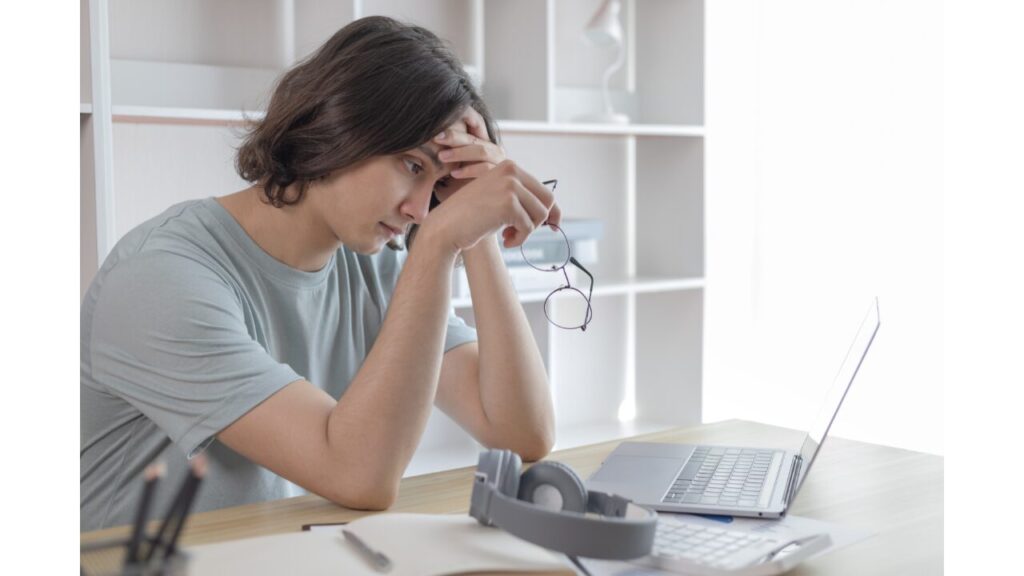
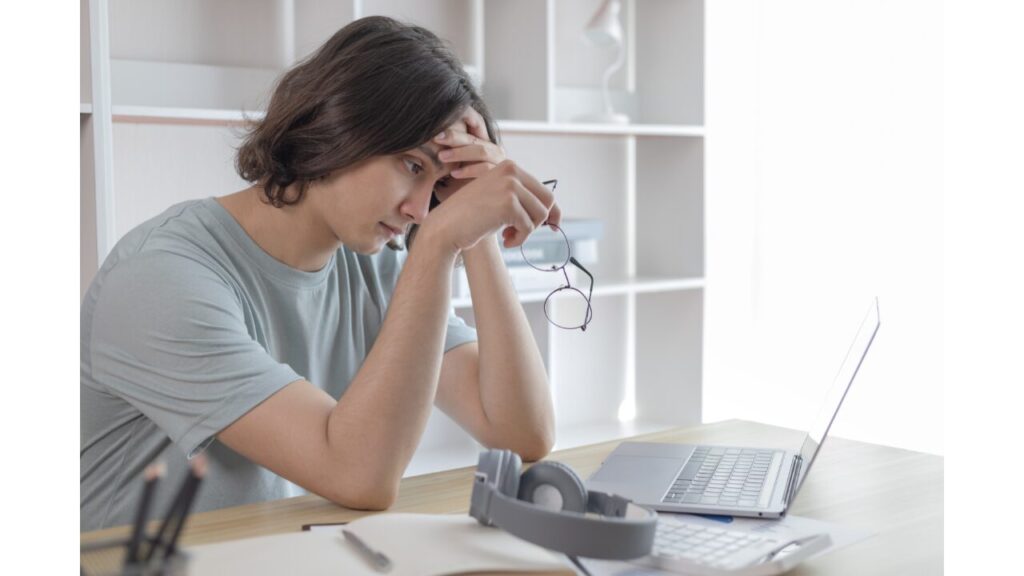
安全配慮(複数対応・録音・退避の基準)
相手宅での対応は、施設以上に安全配慮が重要です。暴言・長時間拘束など不当な態様が見られる時は、単独対応を避け、複数名で訪問し、滞在時間に上限を設けます。
記録は詳細に残し、音声記録は事業所方針・法令・相手の同意に留意して運用します。危険がある場合は退避を優先し、責任者へ即時連絡、必要に応じて医師・弁護士・警察・関係機関と連携します。
これらは厚労省のハラスメント対策マニュアルが示す組織対応の原則に沿います。
契約外の要求を断るときの伝え方
訪問介護は「身体介護」「生活援助」など契約で決まった範囲で提供します。契約外(危険行為・不合理な家事・家族個人の用事など)の要求が来た場合は、運営基準・重要事項説明書に基づく根拠を示し、代替案(ケアマネ経由で別サービス提案等)を一緒に検討します。
正当な理由があれば提供を断ることができ、その際は居宅介護支援事業所への連絡や他事業所の紹介など必要な措置を速やかに講じます。
連絡経路の一本化(誰に、いつ、どう共有するか)
訪問介護は現場が分散するため、情報の行き違いが起きやすい領域です。家族・本人への連絡窓口、ケアマネへの報告経路、事業所内の共有手順(様式、記録の保存期間)を一本化し、どの職員が受けても同じ動きになるようにします。
運営基準は、訪問介護計画等の記録を整備し「完結の日から2年間の保存」を求めています。自治体によっては保存期間をより長く定める運用があるため、地域の手引きも確認しておくと安心です。
理不尽なクレーム(モンスター)への対応


見分け方チェックリスト(内容/態様の評価)
理不尽かどうかは「何を求めているか(内容)」と「どう求めているか(手段・態様)」の2軸で判断します。
内容が契約や法の範囲から外れていないか、態様が暴言・長時間拘束・威圧など社会通念から外れていないかを落ち着いて点検します。
どちらか一方でも常識から外れていれば、通常の苦情とは扱いを分け、複数対応・記録・時間制限をすぐに実施します。厚生労働省はこの2軸での見分け方を示しています。
原則(複数対応・記録・時間設定・窓口一本化)
理不尽だと判断したら、単独対応をやめ、必ず二人体制以上で対応します。
やり取りは記録に残し、面談や電話は時間を区切ります。連絡先は窓口を一本化し、同じ要求が別ルートで繰り返されるのを防ぎます。
これらは介護現場向けの厚労省マニュアルでも基本原則として示されています。
7-3. 外部連携(医師・弁護士・警察・関係機関)
健康・安全に関わる恐れ、法的紛争の可能性、犯罪のおそれがある場合は、早い段階で専門家と連携します。
介護の苦情には第三者の仕組みがあり、都道府県の「福祉サービス運営適正化委員会」や、市町の介護保険課・福祉課が利用できます。
事業所で抱え込まず、制度の窓口に繋ぐことで、公正な調整と職員保護の両立がしやすくなります。
過剰対応を避ける考え方
相手の要求が不当な場合、誠実に説明した上で、できないことはできないと明確に伝えます。
無期限の謝罪・無制限の面談・過度な金銭補償などは、さらに要求をエスカレートさせる可能性があります。
「内容の妥当性×態様の相当性」の軸に沿って、必要な是正だけを行い、それ以上は組織の基準に従って線を引きます。厚労省マニュアルは、過剰対応の回避と記録の徹底を求めています。
クレーム対応マニュアルの作り方


章立て(目的・範囲・定義・権限)
まず「目的(利用者満足と職員保護の両立)」「適用範囲(全職種・委託含む)」「定義(苦情・クレーム・カスハラ)」「権限(一次対応者・責任者・エスカレーション先)」を最初に固定します。
定義はカスハラの2軸(内容の妥当性/手段・態様の相当性)を採用し、現場の判断がぶれないようにします。国際規格ISO 10002は、組織が「計画→運用→改善」までを包含する苦情対応プロセスの枠組みを示しており、章立ての基礎になります。
対応フロー図(受付→確認→提案→フォロー)
フローは受付→傾聴→共感→事実確認→謝罪の使い分け→解決策提示→合意→フォローの一本線で表します。
理不尽シグナルが出た時点で“複数対応・時間設定・窓口一本化”に分岐する図にします。フロー図の最後に「記録保存→月次レビュー→再発防止」を必ずつけ、運用サイクルに乗せます。
様式集(受付票/対応記録/エスカレーション表)
期限管理(SLA)と「未完了案件ボード」
「誰が・いつまでに・何をするか」をSLA(対応期限)として記載し、未完了案件ボード(一覧表)で毎週確認します。
期限を過ぎる前に理由と新期限を事前連絡すること、完了後は再発防止策と共有先をセットで記録することをルール化します。
介護の記録は運営基準で「完結の日から5年間」保存が求められ、自治体によってはより長期の保存を求める運用もあります。保存期間の基準はマニュアルの最後に明記しておきましょう。
カスタマーハラスメント対策の仕組み


事業所方針の掲示と周知
事業所として「正当な苦情には誠実に対応するが、暴言・威圧・不当要求には組織で線を引く」という方針を、受付・面談室・職員掲示板に見える形で示します。
方針には、判断の軸(要求の内容が妥当か/手段・態様が相当か)と、窓口・記録・エスカレーションの基本を入れます。厚生労働省は、カスハラ対策として事前の準備と周知(方針・ポスター・リーフレット)を推奨しています。
介護現場でのカスタマーハラスメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/customerharassment/
カスタマーハラスメントについての対策について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-kasuhara-taisaku/
年2回の研修(基礎→ロールプレイ→ケース会議)
年2回を目安に、①用語と線引きの基礎、②台本を使ったロールプレイ、③直近事例の振り返り(再発防止)を回すと、現場のブレが減ります。
厚労省の介護現場におけるハラスメント対策マニュアルは、研修用ツールや事例集を整備しており、実地で使える教材として有効です。
相談窓口・ホットライン(産業保健・EAPの活用)
管理者ラインに加え、事業所内の相談窓口と外部の専門窓口を用意します。外部は、産業医・保健師と連携できる産業保健総合支援センターや、メンタル不調の早期対応に役立つEAP(従業員支援プログラム)が利用できます。
産業保健総合支援センターは地域ごとに相談窓口を設け、事業場のメンタルヘルス対策の助言を行っています。EAPは厚労省のメンタルヘルス指針が示す「事業場外資源によるケア」に位置づけられます。
限界設定(退去・契約解除の手順と記録)
暴力や他利用者の安全を脅かすなど、重大な支障がある場合は、契約と法令に沿って退去・契約解除を検討します。
有料老人ホーム設置運営標準指導指針は、契約解除条項は「入居者の権利を不当に狭めない」「信頼関係を著しく害する場合に限る」などの原則を示しており、予告期間の設定が入居者の利益を不当に害さないよう求めています。
手続きは、契約書・重要事項説明書に沿って、経緯・通知・協議内容を記録して進めます。
予防と再発防止(コストを下げる近道)


データ化(分類×重大度×発生源の見える化)
苦情・クレームを「種類(接遇/事故/紛失/説明不足/料金など)」「重大度」「起点(ユニット・時間帯・手順)」で数値化し、月次で可視化します。
改善は数字で管理すると速く回ります。苦情対応プロセスを計画→運用→改善のサイクルで回し、傾向分析と是正を行うことが有効です。
接遇フレーズの標準化(全員が同じ言い方をする)
「第一声」「謝罪の言い回し」「確認の質問」「締めの一言」を台本化し、全員が同じ言い方で対応できるようにします。
属人化をなくすことが、初動のブレを減らし、一次収束率を上げます。この“標準化→運用→見直し”は、ISO 10002が求める手順の文書化と継続的改善にあたります。
事例の共有(成功・失敗の学びを蓄積)
対応後は、事実→影響→是正→再発防止→期日→責任者の型でケースノートを残し、週次・月次で共有します。
保存は法令・運営基準に沿って行います。たとえば訪問介護では、提供に関する各種記録を完結の日から2年間保存することが求められます(自治体で上乗せあり)。記録と見直しを続けることが、次のトラブルを防ぐ最短ルートです。
よくある質問(FAQ)


どこまで謝罪すべき?
相手の気持ちに対するお詫びは必ず伝えます。そのうえで、過失が明らかな部分は「当方の不備」を明確に謝罪し、過失が不明な段階では「不快な思いをさせた事実」への遺憾を表し、調査の手順と期日をセットで伝えます。
過剰な約束(無制限の面談・過大な補償の確約)は長期化の原因になるため避けます。苦情対応は「受付→評価→是正→再発防止→見直し」という流れで運用するのが国際標準で、謝罪は是正策と分けて説明するのが実務上も安全です。
賠償が必要かどうかの考え方
人身・物損など具体的な損害があり、事業者側の過失が認められるときは、契約や法に沿って賠償対応を検討します。
まず事実確認と原因分析を行い、保険(施設賠償責任保険など)の適用可否を含めて、責任者が方針を示します。介護分野でも、事故時の賠償に備えて保険加入・賠償資力の確保が望ましいと示されています。
判断が難しいときは弁護士や保険会社と連携し、記録を残しながら進めるのが安全です。
記録はどこまで残す?保管期間は?
苦情の受付内容、やり取り、合意事項、実施した是正策と再発防止策、フォロー結果までを一連で記録します。
介護保険事業所ではでは、施設サービス計画書やサービスの提供記録などの指定記録は「完結の日から5年間」保存が求められます(地域で上乗せ運用がある場合は自治体通知を確認)。保存期間と保管方法はマニュアル末尾に明記しておくと、引継ぎ時も迷いません。
理不尽な要求の打ち切り方
要求の「内容が妥当か」「手段・態様が相当か」の2軸で判断し、どちらかが不当なら、複数対応・時間設定・窓口一本化に切り替えます。できないことは根拠(契約・運営基準・安全配慮)を示してはっきり伝えるのが基本です。
暴言・威嚇・長時間拘束などが続く場合は、管理者同席で対応し、必要に応じて医師・弁護士・警察や第三者機関へ連携します。過剰対応は避け、記録を徹底しましょう。
まとめ|信頼回復と職員保護を両立させる


要点整理(型×例文×記録×研修×方針)
迷った時ほど型に戻ります。
これらは、国際規格(ISO 10002)の「計画→運用→改善」の考え方や、厚労省のカスハラ対策・介護現場向けマニュアルの基本線と一致します。個人対応から組織対応へ。これが最短の近道です。
明日からのToDo(受付票配布/週次レビュー/第一声の練習)
これだけで初動のムラが減り、一次収束率が上がります。制度上の相談ルートも併記しておくと、いざという時にすぐ動けます。
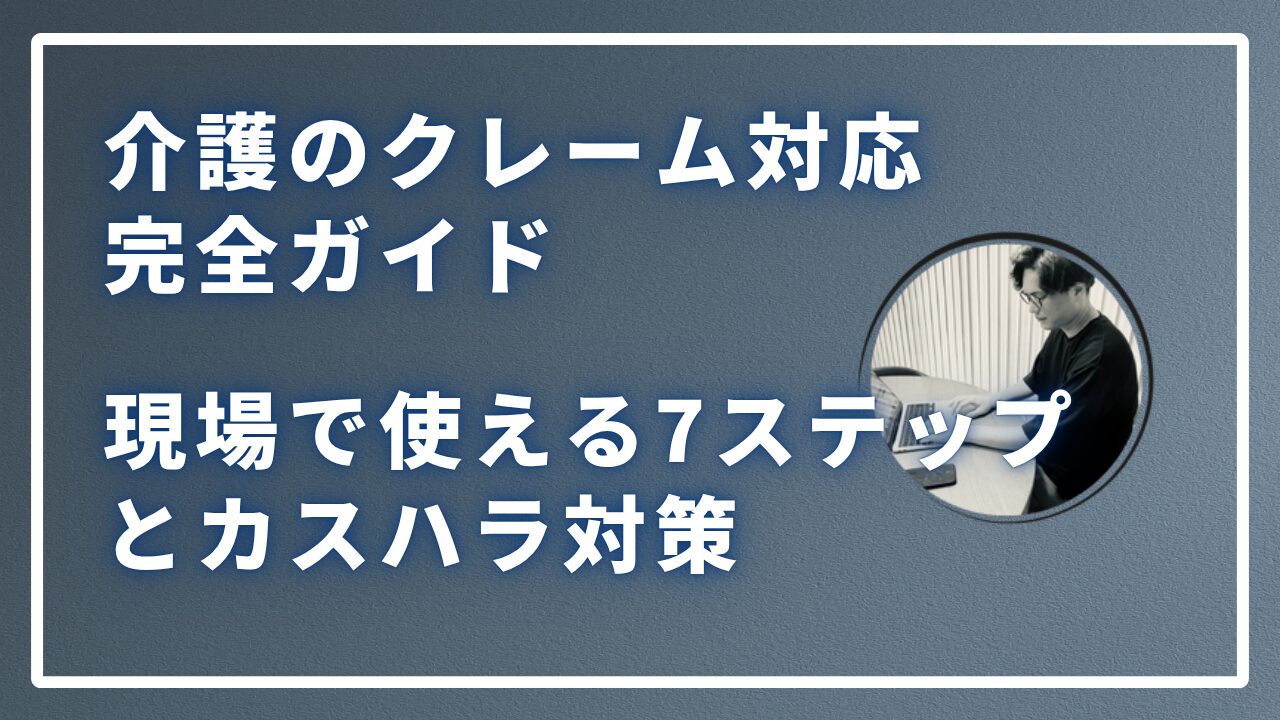
コメント