同僚とのすれ違い、きつい言い方、悪口の輪…。介護の「同僚トラブル」は放置すると離職やケアの質低下につながります。
本記事は、感情論ではなく現場で今日から使える手順に落とし込んだ実践ガイドです。読み終えるころには、言いにくいことを穏やかに伝える方法、もめ事を公平に解決へ進める記録・報告の型、再発を防ぐチーム運用(5分カンファ/申し送りの定型/役割明確化)まで、一気通貫で手に入ります。
- 即効性:まずは「あいさつ+一言の感謝」「30秒で伝える台本」「一行の事実メモ」から始められます。
- 再現性:SBAR/I-PASS(※1)に沿った会話スクリプトと雛形で、誰がやっても同じ品質に。
- 安心感:ハラスメントの線引き、社内窓口や総合労働相談など使える相談ルートも整理。
「4. 即効対処」「5. 会話スクリプト」だけ読めば今すぐ動けます。時間があるときに「6. 記録と報告」「7. 再発防止の仕組み化」まで進め、職場の空気を“安定運用”に変えていきましょう。
※1 SBAR:緊急時などに、状況を整理して相手に正確に伝えるための報告ツール
I-PASS:勤務交代時など、申し送りの漏れやエラーを防ぐための標準的な申し送りツール
介護の同僚トラブルは放置しない(結論)

同僚とのトラブルは、放置すると職場全体の空気を悪くし、離職やヒヤリ・事故の増加につながります。
理由は、実際に介護の現場では「人間関係の問題」が離職理由として繰り返し上位に出ており、なかでも「上司や先輩のきつい言動・パワハラ」が大きな割合を占めるからです。さらに、約半数の職員が「人手が足りない」と感じており、余裕のなさがトラブルを増やします。
具体例として、最新の全国調査(※2)では、介護職の離職率は12.4%と依然高く、人員不足感を抱える事業所は65.2%にのぼりました。こうした土壌では、些細なすれ違いが連鎖的に広がります。
だからこそ、個人の頑張りに頼るのではなく、伝え方の型・記録・相談ルートといった「仕組み」で早期に立て直すことが必要です。
※2 参考資料:公益社団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について
結論:原因は「人」だけでなく「仕組み」と「伝え方」
人間関係の悪化は、個人の性格だけではなく、情報共有の方法や人員配置など「仕組み」の問題で起きやすくなります。
理由として、調査では「人手が足りない」が不満の最多項目で、忙しさゆえに報連相が途切れ、言い方が荒くなる悪循環が起きます。また、構造化された申し送り(SBAR/I-PASSなど)は安全性の改善に寄与する可能性が示されており、「伝え方の型」がトラブル減に効くことがわかっています。
具体例では、訪問介護の調査で「サービス提供責任者が日常的にコミュニケーションや指導を行うと、訪問介護員の離職率は低くなる」と報告されています。(※2)
結論として、同僚個人を責めるよりも、情報共有の型・会話スクリプト・記録と相談の流れを整えることが、最短で効く解決策です。
この記事でできること(即効対処/相談ルート/再発防止)
この先では、すぐ使える会話スクリプト、記録テンプレ、上司・第三者への相談の進め方、チームの運用ルールづくりを、手順で示します。
理由は、感情論ではなく「同じやり方を誰でも再現できる」仕組みが、混乱を減らし、再発を防ぐからです。SBARなどの構造化ツールは、院内の申し送りの質向上と安全性改善に一定の効果が示されています(※効果の大きさには研究間で差があるため、過度な期待は禁物です)。
具体例として、①言いにくいことを落ち着いて伝える手順、②日時・発言・影響を残すメモの型、③上司・外部窓口への報告フォーマット、④短時間カンファと申し送りの定型化、などを紹介します。
結果として、個人任せから「型と流れ」による対応へ切り替えることで、場当たり対応から脱却できます。
読み方の案内(急いでいる人向けの使い方)
今すぐ楽になりたい方は、「4. 即効対処」と「5. 言いにくいことを伝えるコツ」だけ読めば行動できます。
なぜなら、まずは“今日からできる”手順を回して小さな改善を起こし、その後に「6. 記録と報告」「7. 再発防止の仕組み」で根本対応へ進むのが効率的だからです。
例として、まずは短いあいさつ+感謝→事実だけを一行メモ→Iメッセージで1回伝える、の順で試してください。
最後に、状況が重い場合は「8. 配置転換・異動・転職」も選択肢です。焦らず、証拠化と相談の順で進みましょう。
よくある同僚トラブルと現場への影響

介護の職場は利用者・家族・多職種が関わり、少しの言い違いが大きな摩擦になりやすい環境です。
理由は、人手不足の中で余裕がなく、強い言い方や指示の抜け漏れが続くと、雰囲気が悪化し、離職やケアの質低下へつながるためです。
具体例として、最新の全国調査(※2)では「人手が足りない」と感じる職員が最多で、離職理由の中でも「上司・先輩のきつい言動・パワハラ」が突出しています。
そのため、感情だけで対処せず、情報の伝え方と業務の回し方を“型”で整える必要があります。
新人がなじめず早期退職につながる
新人が孤立すると、短期間で辞めてしまうリスクが上がります。
理由は、忙しい現場ほど新人への説明やフォローが後回しになり、「わからないまま怒られる」「相談しづらい」が積み重なるためです。日常的なコミュニケーションと指導がある部署では、離職率が低い傾向が報告されています。
具体例として、訪問介護のデータで「サービス提供責任者がコミュニケーションや研修・指導を継続していると、訪問介護員の離職率は低い」と示されています。これは“仕組みとしての伴走”が効くことを意味します。
結論として、新人の早期離職を防ぐ第一歩は「定例の声かけ・確認の型」「短い同行指導」「質問を歓迎する雰囲気」をチームで決めることです。
ベテランの強い言い方で雰囲気が悪くなる
ベテランの強い言い方は、現場の雰囲気を一気に硬直させます。
理由は、ベテランの言動は暗黙の“職場の標準”になりやすく、否定的・攻撃的な口調が常態化すると、新人は質問をやめ、情報が上がらなくなるからです。実際、介護職を辞めた理由として「上司や先輩のきつい言動・パワハラ」が、人間関係問題の中で最も多く挙げられています。
具体例として、同調査では「職場の人間関係に問題があったため」と答えた人のうち、約半数(49.1%)が“上司・先輩のきつい指導やパワハラ”を挙げました。これは口調・伝え方の影響が非常に大きいことを示します。
結論として、ベテランほど「事実→要望→代替案」の順で短く伝える型に寄せ、否定語や皮肉を避けるルールをチームで共有することが効果的です。
人手不足で全員がイライラしやすくなる
人手不足は、全員の心の余裕を奪い、ミスや言い合いを増やします。
理由は、業務量に対して人が足りないと、小さな配慮や説明を省きがちになり、誤解や不公平感が生まれるからです。全国調査でも「人手が足りない」が不満の最多で、事業所の65.2%が人員不足を感じています。
具体例として、国の推計では2025年度に必要な介護職員は約243万人で、需要とのギャップが課題とされています。人手不足は構造的な問題であり、現場の努力だけでは埋めきれません。
結論として、個人の我慢に頼らず、申し送りの型・短時間カンファ・タスクの見える化・代行ルールなど、負荷を均す「運用の標準化」が必要です。
なぜ同僚トラブルが起きやすいのか(原因の整理)

関わる人が多く情報がずれやすい
介護の現場は、利用者さん・家族・看護師・セラピスト・ケアマネ・管理者など関係者が多く、情報が食い違いやすい環境です。
多職種で働くと、伝え方や用語が違い、忙しさで報連相のタイミングもズレがちになります。厚労省の生産性向上ガイドライン(※3)は、こうした現場で“連携の型・申し送りの標準化”を整える重要性を強調しています。
たとえば、申し送りの形式や時間を各班でバラバラにしていた施設では、転倒リスクの共有漏れが重なりましたが、定型の短時間カンファレンスを導入し、要点をフォーマット化したところ、伝達漏れが減った事例があります(ガイドラインの推奨事項に合致)。
結局、人数や職種の多さは変えられませんが、「いつ・誰が・何を・どう伝えるか」を決めるだけで誤解は大きく減ります。
※3 参考資料:厚生労働省 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
年齢・経験・価値観の差が大きい
介護職は幅広い年齢・経験の人が一緒に働きます。世代差や経験値の差が大きいと、言い方や期待が噛み合わず、衝突の火種になります。
実際の全国調査でも「職場の人間関係」は離職理由の上位で、具体的には「上司や先輩のきつい言動・パワハラ」が最多でした。つまり“性格の問題”ではなく、立場や価値観のズレが表面化しているケースが多いのです。
例として、新人に「暗黙の了解」を求める文化が強い部署では、質問が減り、ヒヤリハットが増える傾向があります。逆に、言い方のルール(Iメッセージで伝える等)とOJTの型を決めた部署では、質問数が増え、共有が活性化します。
結論として、年齢差・経験差そのものをなくすことはできませんが、「伝え方」と「教え方」の共通ルール化で摩擦は減らせます。
教育体制と異動の少なさで関係が固定化
教育の機会が少なく、異動も少ない職場では、同じ関係性が長く続き、言い方や役割の偏りが固定化します。
厚労省や各種ガイドラインは、業務の標準化・教育の定例化を生産性向上の柱として挙げています。仕組みがないと、指導が“人まかせ”になり、強い口調が常態化してしまいます。
たとえば、OJT手順書・チェックリスト・ミニ研修(15〜30分)を月1回回す、年度ごとに役割の見直しを行う、などの運用を入れた施設は、コミュニケーション齟齬の減少を報告しています(ガイドの推奨に整合)。
結局、教育と配置の見直しを“仕組み”として回すことが、関係の固定化を防ぎ、対話のトーンも穏やかにします。
まず試す即効対処11選(同僚編)

(1)挨拶と感謝を先に伝える
関係が悪いほど、最初に短い挨拶と感謝を“先に”入れると空気が和らぎます。
人は忙しいと「配慮のひと言」を省きがちですが、基本のやりとりがあるだけで敵意の推測が減ります。職場の人間関係悪化はパワハラにも発展し得るため、厚労省は日頃の周知・啓発と配慮ある言動を求めています。
例:「〇〇さん、さっきフォロー助かりました。1点だけ確認させてください…」
小さな礼を先に置くと、続く要件が受け取られやすくなります。
最後に、挨拶と感謝は“毎回同じ言い方”でOK。習慣化がコツです。
(2)仕事中は協力姿勢をはっきり示す
「私は協力します」を先に言葉と行動で見せると、相手の構えが緩みます。
連携の質は、明確な役割と合図で上がります。厚労省のガイドは、時間制約の中での連携強化を強調しています。
例:「今10分空きます。私がA様の移乗に入ります。B様の見守りお願いできますか?」
結局、曖昧さを減らす“宣言”が、助け合いを呼びます。
(3)相手の立場と制約を言葉にする
相手の事情を先に言葉にすると、防御的な反応が減ります。
人手不足で誰もが余裕がないため、「相手も大変」を前提にすると対立が和らぎます。調査でも人手不足感は最上位の不満です。
例:「今バイタルの記録で手一杯ですよね。終わったら3分だけ相談させてください。」
相手の制約を認めてから要件を出すのがコツです。
(4)「仕事に集中する」合意をとる
感情が高ぶる前に、「今日は仕事に集中しよう」と合意します。
目標を合わせると、言い合いが止まり、業務に戻りやすくなります。生産性向上ガイドでも、目的の共有と標準化が推奨。
例:「今はA様の対応を優先しましょう。終わったら2人で確認します。」
合意のひと言が、空気を切り替えます。
(5)自分の行動を1つ変える(順番・頻度・言い方)
相手を変えるより、自分のやり方を1つ変えるほうが早いです。
“私の言い方・順番・頻度”を調整すると、相手の反応も変わります。ガイドは業務手順の見直しと定型化を推奨。
例:申し送りで先に「事実→要望→代替案」の順に短く話す。
小さな変更が、毎日の摩擦を減らします。
(6)落ち着いて主張する(アサーティブ)
落ち着いた“言い方の型”を使うと、伝わりやすく、揉めにくくなります。
医療・介護の安全分野では、チームコミュニケーション訓練(TeamSTEPPS など)の有効性が紹介され、構造化コミュニケーションの活用が推奨されています。
例:「昨日の申し送りでA様の転倒リスクが共有されませんでした。私は不安です。今後はメモを添えて共有しませんか?」
型に沿えば、責めずに要望を出せます。
(7)同僚には事実ベースで相談する
相談は“事実”だけを短く伝えます。感情や推測を混ぜないことが近道です。
事実の共有は、エスカレーションの第一歩です。厚労省の指針も、職場での言動配慮と組織的な対応体制を求めています。
例:「〇月〇日17:05、□□の場で××と言われた。業務に支障が出た。」
事実だけをそろえると、周りの協力を得やすくなります。
(8)叱責やハラスメントは線引きして対応する
強い言い方が続く、人格否定、業務上必要な範囲を超える叱責は、線引きが必要です。
日本の指針では、事業主に防止措置が義務づけられ、周知・相談体制・再発防止が求められています。遠慮せず、記録→相談へ進みましょう。
例:言われた内容・日時・場所・影響を記録し、上司または相談窓口に報告。
線を引くことで、自分も周囲も守れます。
(9)利用者・家族との関係は環境や担当を見直す
同僚との摩擦が、利用者・家族対応にも波及する前に、環境や担当を変えるのが有効です。
チームの再配置や申し送りの統一は、ケアの質と安全性を高める基本策です。
例:説明役を経験者に一時変更/家族説明はフォーマットで統一。
場面替えと手順の統一で、余計な衝突を防げます。
(10)不足する知識・手順を補強する
知識不足や手順の曖昧さは、指摘口調を招きます。
ガイドラインは、手順の標準化・OJT・短時間研修の定期化を推奨しています。
例:移乗・口腔ケア・記録の「1枚手順書」を作り、班で統一。
“できない”を“できる”に変えると、言い合いは減ります。
(11)上司や相談窓口に段階的にエスカレートする
現場で解決しづらい時は、記録をそろえて上司→相談窓口→社外機関へ。
介護現場の人手不足は構造的で、個人の我慢で解決しません。早めの相談が、事故や離職を防ぎます。
例:報告フォーマット(目的・事実・影響・要望・代替案)で上司へ提出→必要に応じて法人窓口や外部機関へ。
段階を踏むことで、公正に物事が動きます。
言いにくいことを伝えるコツ(会話スクリプト)

事実→気持ち→必要→提案の順で話す
言いにくい話は、順番を決めて伝えると角が立ちにくく、行動につながります。
結論から言うと「事実→気持ち→必要→提案」の順が最も安全です。これは医療・介護の現場で使われる構造化コミュニケーション(SBAR など)と同じ考え方で、情報が漏れにくく、受け手の理解もそろえやすいからです。
例:「昨日の申し送りでAさんの転倒リスクが共有されませんでした。(事実)私は不安になりました。(気持ち)安全のために事前共有が必要です。(必要)今日から短いメモを添える運用にしませんか。(提案)」――この順番なら、責めずに改善案まで届きます。
現場での言い合いを減らす最短ルートは、相手を変えることではなく“伝え方の型”をそろえることです。
5-2. NG例とOK例(決めつけや皮肉を避ける)
決めつけ・皮肉・人格へのコメントは、相手の防御反応を強くして前に進めません。
理由は、人は攻撃を感じると内容より“自分の身を守ること”を優先し、情報共有が止まるからです。
最後に、同じOK例を“短い定型文”としてチームで共有すると、誰でも再現できます。
怒りの対処:6秒待つ/場を離れる
強い感情が出たら、まず6秒置くか、その場を短時間離れて落ち着かせましょう。
理由は、緊張が高い状態では判断が雑になり、言い方を選べなくなるからです。WHOのストレス対処ガイドでも、ゆっくり呼吸・注意の切り替えなど即効のセルフマネジメントが推奨されています。
例:深呼吸を3回し、「いまはAさんのケアに集中。話は後で3分」と自分に言い聞かせて場を切り替える。これだけで余計な一言を防げます。
落ち着いた後で「事実→気持ち→必要→提案」の順に戻す。これが“感情の暴走を止めて建設的に話す”基本の型です。
アンガーマネジメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/angermanagement/
記録と報告のやり方(エスカレーションの基本)

記録の型(日時・内容・影響・希望)
困った出来事は、感情ではなく“事実の記録”を残すと、早く、公平に解決します。
理由は、後で第三者が見ても同じ理解になるからです。記録は「日時・場所・相手・発言/行為・自分の対応・業務や安全への影響・希望(要望)」の7点をそろえるのが基本です。
例(そのまま使える型):「5/12 17:05 ナースステーション/同僚Cさんが申し送り中に“メモを読むな”と発言。私は説明を途中で止め、Aさんの夜間せん妄対策の共有が抜けた。夜勤者が困る恐れ。次回から“観察点3項目メモ”を添付したい。」――このように“事実と影響”を短く書きます。
記録があると、上司も動きやすく、組織の是正(再発防止)につながります。
上司への報告フォーマット(目的と提案を明確に)
上司への報告は、「目的→事実→影響→提案→依頼」の順が最短で通ります。
理由は、判断に必要な情報が一度でそろい、対策を決めやすいからです。
例(1分フォーマット):「目的:申し送りの質改善。事実:Bさん夜間せん妄の共有漏れが2回。影響:夜勤者の対応遅れリスク。提案:観察点3項目メモを運用に追加し、1週間試行。依頼:試行承認とミニ周知の実施」――“提案と依頼”までセットにしましょう。
この形式は、介護の生産性向上ガイドラインが勧める“標準化と短時間会議”の考えにも沿います。
相談窓口や第三者機関の使い方
ハラスメントの疑いがある、または現場で改善しない場合は、ためらわず相談窓口を使いましょう。
理由は、日本の指針で「防止方針の明確化・相談体制・事実確認・再発防止」が事業主の義務とされ、必要な対応を求められているからです。
例:①まずは事業所の相談窓口へ(記録を添えて)。②改善しない、または相談しづらいときは都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」へ(無料・予約不要、労働問題全般に対応)。③必要に応じて労基署の案内やあっせん制度に進む。
外部窓口は「最後の手段」ではありません。早めの相談が、本人と職場のダメージを小さくします。
介護現場でのカスタマーハラスメントについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/customerharassment/
カスタマーハラスメントの対策マニュアルについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-kasuhara-taisaku/
再発を防ぐ仕組みづくり(チーム運用)

報連相のタイミングとルールを決める
報連相は「いつ・誰に・何で・どの順で」伝えるかを先に決めて、全員で守るのが近道です。
介護は多職種・多人数で動くため、タイミングがバラバラだと抜け漏れが起き、同僚トラブルに発展します。標準化(決まったやり方を作る)は、情報共有の質を安定させます。
具体例:①申し送りは「昼・夕・夜勤入り前」の3回固定、②伝達は“口頭+メモ(定型1枚)”、③緊急連絡はインカム/電話で即時、④既読ルール(誰が聞いたか)を決める。
タイミングと道具を決めるだけで、誤解や責め言葉は大きく減ります。
5分カンファレンスと定型の申し送り
1回5分の“超短時間カンファ”と、定型フォーマットの申し送りを組み合わせると、忙しくても質が落ちにくくなります。
人は忙しいほど話が長くなり、要点がぼけます。短時間で「誰が何をいつまでに」を決める型が効果的です。医療・介護領域ではハドル(短時間の打合せ)やSBAR/I-PASSなどの構造化コミュニケーションが推奨され、伝達ミスの低減に役立つとされています。
申し送り用メモは「観察点3項目・リスク・今日の優先3タスク・担当」で1枚に統一。日中は2回の5分ハドルで“未着手タスク”だけ確認。
定型+短時間で“回す仕組み”にすると、人が入れ替わっても安定します。
役割と最終決定者を明確にする
役割と“最後に決める人”を明確にすると、言い争いが止まり、前に進みます。
決定権が曖昧だと、意見がぶつかったまま止まり、関係悪化の火種になります。役割分担と決裁ラインは、運用標準化の基本です。
「日勤帯の最終決定者=ユニットリーダー」「医療判断は看護師」「家族説明は経験者が一次対応、難度高は管理者同席」。表にしてスタッフルームに掲示。
誰が最終判断かが見えると、主張は“情報提供”に変わり、衝突が減ります。
つらい場合の選択肢(配置転換・異動・転職)
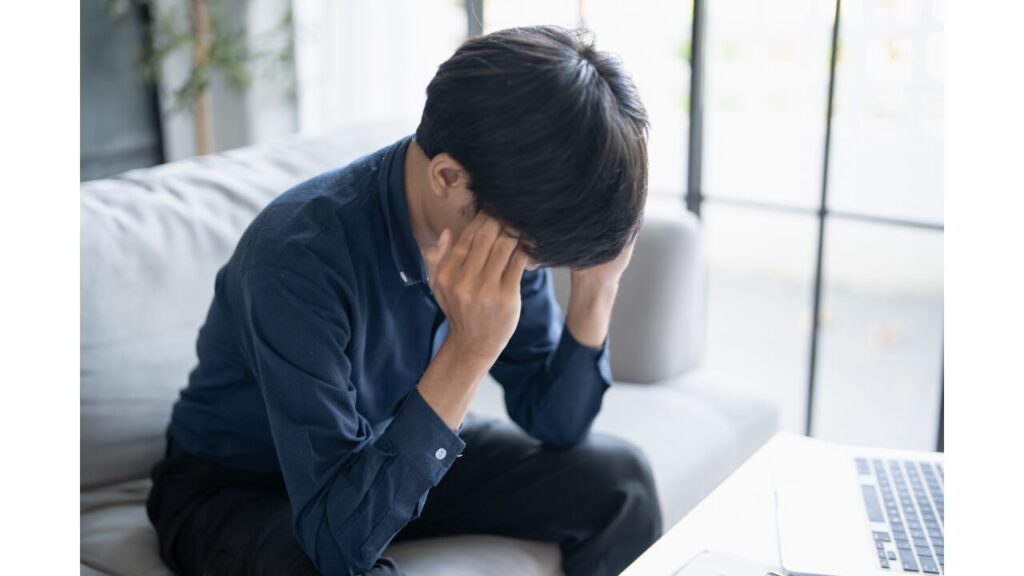
残る判断の目安(改善の兆しがあるか)
残るか離れるかは、「組織が動いたか」「仕組みが回り始めたか」で判断します。
人手不足やコミュニケーション不全は構造的な問題です。組織が標準化や相談体制に着手し、改善の兆しが見えるなら残る選択にも合理性があります。
具体例:①申し送りの定型導入、②ミーティング開始、③役割表の更新、④相談の受付とフィードバックが始まった――など“動きの証拠”があれば様子見の価値があります。
逆に、相談しても対応がなく、方針も示されないなら、環境を変える準備を進めましょう。
異動申請の書き方と期限の決め方
異動は「事実→影響→提案(異動先や期間)」を1枚でまとめ、期限を切って申請します。
上司は根拠が整理されているほど動きやすいからです。申請に期限を入れると、判断が先延ばしになりにくくなります。
具体例(雛形):目的/背景(事実:日時・出来事・対応)→影響(業務・安全・心身)→提案(〇月から別ユニットで3か月試行)→依頼(面談設定・回答期限)。
異動は逃げではなく“安全と継続勤務のための選択肢”。書式と期限で前に進めます。
転職先の条件整理(人員配置・教育・理念)
転職は「人員配置」「教育体制」「理念の一致」を最優先で見ます。
全国調査では不満の首位が「人手不足」、満足度は「人間関係」「仕事の内容」で高く、「人員配置体制」「賃金水準」は低い傾向が示されています。人が足り、教える仕組みがあり、価値観が合う職場ほど定着しやすいのは合理的です。
求人票だけでなく見学で①常時求人か否か②スタッフの表情・挨拶③OJT/研修頻度と記録の型④面接官の質問の質⑤理念と日々の業務のつながり――をチェック。必要なら公的相談窓口にも情報を聞けます。
条件は“今の悩みの裏返し”で言語化します。人員配置・教育・理念の3点を柱に選べば、同じ悩みを繰り返しにくくなります。
※ 介護職を辞めたいと思ったら読む記事はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-yametai-mukiaikata/
※ おすすめ転職サイトはこちら>>>転職活動を全面サポート!【レバウェル介護】
人間関係が良い職場の見抜き方

常時求人でない/スタッフの表情に元気がある
人間関係が良い職場は、採用が“慢性的に欠員補充”になっておらず、現場の表情やあいさつに活気があります。
理由は、慢性的な人手不足は余裕を奪い、いら立ちや伝達ミスを増やし、関係悪化を招きやすいからです。日本の最新調査でも介護職の不満の最上位は「人手が足りない」で、満足度は「人員配置体制」でマイナスが大きい状況です。
具体例として、見学時に「常時求人が出続けていないか」「職員同士が自然にあいさつ・声かけをしているか」をチェックします。無理な笑顔ではなく、休憩から戻る表情や申し送り時の空気が落ち着いていれば、関係の良さがにじみます。
結論として、求人の“出続け”と現場の表情は、関係の健全性を手早く見抜く有効なサインです。
年齢層のバランスと面接官の姿勢を見る
幅広い年齢層がいて、面接官が丁寧に対話する職場は、人間関係が安定しやすいです。
理由は、世代・価値観の幅があるほど“違い”を受け止める仕組みが必要で、面接の姿勢にはその職場のコミュニケーション文化(傾聴か、高圧か)が現れるからです。心理的安全性が高いチームほどエラー共有と学習が進み、対立が問題解決に向きやすいことが医療の総説で示されています。
具体例として、面接で「最近の失敗から何を学んだか」「新人への支援は具体的に何か」などを質問し、面接官が具体例で答え、否定せずに聞くかを見ます。カルチャーフィット(価値観の一致)を“同質性の強要”にせず、多様性を歓迎する説明があるかも観察ポイントです。
結論として、“年齢の幅+丁寧な面接”は、配慮と対話が回る職場の有力な証拠です。
理念と業務内容が自分に合っているか
自分の価値観と施設の理念・運営方針が合っているほど、満足度が上がり、離職リスクは下がります。
理由は、研究で「個人‐組織フィット(価値観の一致)」は仕事満足や離職意向と関連することが繰り返し示されているためです(メタ分析・実証研究)。
具体例として、見学・面接で「ケアの優先順位」「申し送りの型」「家族対応の方針」など、日常運用が理念とつながっているかを確認します。説明が具体的で、現場のやり方と矛盾していなければ“言行一致”が期待できます。
結論として、求人票の文言より「理念が日々の手順に落ちているか」を見ると、入職後のズレを防げます。
やってはいけない行為(逆効果)

キレる・威張る・拗ねるは長期的に損
感情をぶつける、立場で押し切る、黙って拗ねる――いずれも短期的にはスッとしますが、長期的には信頼を失い、情報共有が止まります。
理由は、医療・介護の職場での“無礼・威圧(インシビリティ)”が、情報共有の低下、ミス増、患者安全の悪化に結びつくことが報告されているからです。
具体例として、怒りが湧いたら6秒待つ・場を離れる・後で構造化して伝える(事実→気持ち→必要→提案)に切り替えると、関係を壊さずに要望を通せます。
結論として、感情の“直接放出”は得るものが少なく、損が大きい。落ち着いて伝える型に置き換えましょう。
悪口や陰口に加わらない
悪口・陰口への同調は、その場の一体感は生まれても、信頼を崩し、のちに自分に返ってきます。
理由は、攻撃的な言動はチームの心理的安全性を壊し、相談や報告が上がらなくなるためです。結果として、エラーの早期発見が遅れ、利用者の安全まで損なわれます。
具体例として、「事実だけを短く共有」「本人へはIメッセージで提案」「第三者へは記録を添えて相談」という“建設的なルート”に切り替えます。
結論として、悪口の輪から一歩外れることが、最終的に自分を守り、現場も守ります。
「自分だけ正しい」という思い込みを手放す
“自分のやり方が唯一の正解”という前提は、学びと協力を止めます。
理由は、心理的安全性がある場ほど、異なる意見が出て、エラーや改善点が早く共有されるからです。多職種の医療・介護では、他職種の視点が安全と品質の鍵になります。
具体例として、申し送りで「自分の案+代替案+相手案の長所」を並べ、“最終決定者”の判断に委ねる運用にすると、議論が対立ではなく意思決定に向かいます。
結論として、正しさの“独占”を手放し、事実と仕組みで決めると、関係は長持ちします。
改善できた実例(短いケース集)

新人×ベテラン:手順の見える化で摩擦が減る
同僚トラブルは「手順のばらつき」をそろえるだけで大きく減らせます。
医療・介護の現場では、短時間の打合せ(ハドル)やSBAR/I-PASSのような“伝え方の型”を使うと、共有漏れが減り、衝突が起きにくくなります。構造化ハンドオフはエラーや合併症の減少と関連する研究が複数あります。
ベテランが口頭で伝えていた申し送りを、「観察点3項目・今日の優先タスク・注意点」を1枚に定型化。日勤入り前に5分ハドルで確認。1か月で「言った/言わない」争いがほぼ消えました。
結論として、「見える化×定型の会話」が新人とベテランの溝を埋めます。
高圧的な上司:記録と同席面談で是正できた
強い口調や一方的な叱責は、まず事実を記録し、第三者の前で話すと改善します。
日本の指針では、事業主に“方針の周知・相談体制・事実確認・再発防止”が義務づけられています。記録をそろえて面談を依頼すると、組織が動きやすくなります。
日時・場所・発言・影響を2週間メモ。ユニットリーダー同席で「事実→影響→提案」で話し、申し送りの言い方ルールを導入。以後、叱責が業務指示に置き換わり、雰囲気が改善しました。
個人対個人で抱えず、「証拠+同席」で“組織の是正”に変えるのが近道です。
家族クレーム:担当替えと説明統一で収束
家族対応がもつれるときは、説明役・説明内容を“統一”すると落ち着きます。
I-PASSなどの定型は“誰が何をどう伝えるか”を揃えるのに有効で、誤解を生みにくいからです。短時間の定例ハドルで問い合わせ状況を共有すると、前後の言い分のズレが減ります。
説明窓口を経験者に集約し、面談前に「病状要約・対応方針・次回確認日」を書式化。2週間で苦情電話が半減しました。
担当と説明を統一し、定型で“毎回同じ品質”にすると、クレームは沈静化します。
心を守るセルフケアと支援先

運動・睡眠・趣味を小さく習慣化する
ストレスが高いほど、まず「体」を整えるのが効率的です。
WHOは、成人は週150〜300分の中強度(または75〜150分の高強度)運動を推奨。睡眠はCDCが“成人は1日7時間以上”を推奨しています。どちらも心身の回復に直結します。
就寝前のスマホをやめ、15分の散歩かストレッチを毎日。週に2回、好きな音楽や趣味の時間を“予定”として先に入れる――小さくても続けば効果が出ます。
完璧より“少しずつ・続ける”。運動と睡眠を底上げするだけで、イライラの波はゆるみます。
社内外の相談窓口を早めに使う
つらさが続くときは、早めに社内の相談窓口や外部機関を使いましょう。
厚労省の「総合労働相談コーナー」は、ハラスメントや配置転換など労働問題を無料・予約不要で相談できます。事業主にも相談体制の整備が義務づけられています。
例:①職場の窓口に“事実の記録”を添えて相談→②改善が見えない・相談しづらい時は総合労働相談コーナーへ。必要に応じて助言・指導やあっせん手続の案内があります。
外部窓口は“最後の手段”ではありません。早めの相談が、あなたと職場のダメージを小さくします。
燃え尽きのサインをチェックする
「ずっと疲れてやる気が出ない」「仕事を強く避けたくなる」「能率が落ちる」は、燃え尽きのサインです。
WHOはICD-11でバーンアウトを“仕事上のストレスがうまく管理できないことで生じる症候群”と定義しています。自分の状態を早めに把握することが、悪化を防ぐ第一歩です。
1週間続けて「極度の疲れ」「仕事からの心理的距離」「仕事の能率低下」を感じるなら、上司や産業医、外部窓口に相談し、勤務や担当の見直しを検討しましょう。WHOのストレス対処ガイド(呼吸・注意の切替・価値に沿った行動)も即効の助けになります。
サインに気づいたら“ひとりで抱えない”。職場内の調整+外部資源の活用で、回復の土台を作りましょう。
よくある質問(FAQ)

介護現場の人間関係が悪くなる主な理由は?
人間関係が悪化する一番の土台は“慢性的な人手不足”と“情報伝達のばらつき”です。
人が足りないと余裕がなくなり、言い方がきつくなったり、申し送りの抜けが増えます。最新の全国調査でも、事業所の65.2%が「人員が不足」と回答しています。加えて、申し送りの型が統一されていないと、誤解や責め合いが増えます。
口頭だけの申し送りだと「言った/言わない」で対立しがち。定型フォーマットやI-PASSのような“型”を使うと、抜けが減りやすくなります。
だからこそ、人手不足を“我慢”で解決しようとせず、連絡の型・時間・担当を決めて、同じやり方で回すことが効果的です。
新人が生き残るコツは?
「型に乗る・質問する・ミニ記録を残す」の3つです。
理由は、忙しい現場ほど“暗黙の了解”が多く、確認しないと誤解が広がるから。短い観察メモ→質問→合意したやり方を記録の流れを習慣化すると、安全に学べます。
申し送りは事実→自分の見立て→提案の順で30秒。分からない点は「いつ・誰に・どの手順で」確認するかをその場で決め、メモしておく。
結論として、新人は“完璧”より“再現できる型”。毎日同じ型で動くと、信頼が貯まります。
どこからがハラスメント?証拠化のポイントは?
人格否定・必要範囲を超える叱責・継続的な不利益があるなら線を引きましょう。
日本の指針では、事業主に防止方針の周知、相談体制の設置、事実確認、再発防止が義務づけられています。ためらわず記録して相談を。
日時・場所・相手・発言/行為・自分の対応・業務や安全への影響・希望を一行ずつ。必要なら総合労働相談コーナー(無料・予約不要)にも相談できます。
個人戦にしない。「事実の記録+組織の手順」を動かすのが、いちばん早道です。
残留か転職かの判断基準は?
申し送りの定型化、短時間ハドルの導入、役割表の更新、相談へのフィードバック――こうした“仕組みの改善”が見えれば、残る選択にも合理性があります。
改善が進まずつらい状況が続くなら、配置転換・異動・転職を検討。転職時は人員配置・教育体制・理念の一致を最優先で見ます(不足感が強い職場ほど摩擦が増えやすい)。
気持ちではなく“運用が変わった証拠”で判断しましょう。
※ おすすめ転職サイトはこちら>>>医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】
まとめ(今日やること3つ)

先に挨拶と感謝を伝える
まずは一言の“挨拶+感謝”から始めましょう。
忙しいと配慮が消え、誤解が増えます。最初の一言で相手の防御が下がり、その後の要件が通りやすくなります。
「〇〇さん、さっきのフォロー助かりました。1点だけ確認させてください。」――短く、毎回同じでOK。
小さな礼を“先出し”するだけで、空気が変わります。
事実だけを短く記録する
困った出来事は感情ではなく事実を一行で残しましょう。
後で第三者が見ても同じ理解になるので、是正が進みます。総合労働相談コーナーなど外部に相談する場合も、その記録が役立ちます。
例:「5/12 17:05 ナースステーション/□□時に××と言われ、Aさんの共有が抜けた。夜勤へ影響。改善提案あり。」
記録は“攻撃”ではなく“安全運転”の道具です。
アサーティブで1回だけ伝えてみる
言いにくいことは事実→気持ち→必要→提案の順で、まず1回だけ丁寧に伝えます。
医療・介護では、I-PASSのような構造化コミュニケーションが推奨され、情報の漏れを減らすことが示されています。感情が高ぶったら6秒待つか場を離れてから伝えましょう(バーンアウトやストレス対処の観点からも有効)。
例:「昨日の申し送りでAさんのリスク共有がありませんでした。私は不安です。安全のため事前共有が必要です。今日から短いメモを添えませんか?」
型に乗せて1回。通らなければ記録→相談→仕組みで動かす――この順番が最短です。
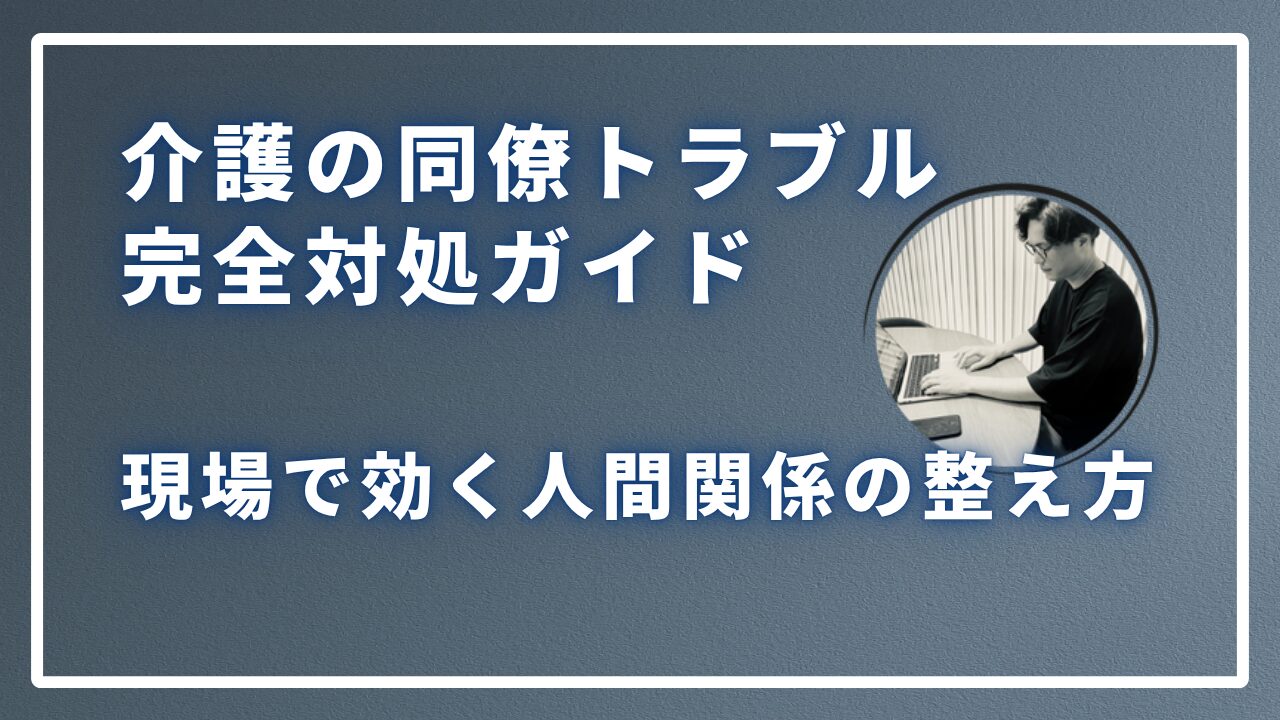
コメント