「明日レク担当なんだけど、何やればいいか分からない…」
そんな悩みを抱える介護職の方、多いのではないでしょうか?
本記事では、レクリエーションが苦手な方でも安心して取り組める“シチュエーション別レク7選”をご紹介します。
道具不要・準備ゼロ・座ってできる…など、どの場面でも「これだけやればOK」と思えるレクを厳選!
この記事を見れば、レクに対する苦手意識がきっと軽くなります。
高齢者レクリエーションが「苦手」な理由とは?

レクが得意じゃない介護職員は珍しくない
介護職であっても、レクリエーションが得意な人ばかりではありません。実際に「進行が苦手」「盛り上げるのが怖い」と感じている職員はとても多く、決して少数派ではありません。
レクのスキルは介護福祉士の資格の中でも必須とはされていないため、現場で突然「今日お願いね」と言われて戸惑うケースも多くあります。
つまり、レクが得意じゃないと感じるのは自然なことですし、それは“介護ができない”ということとは全く関係ありません。安心してください。
「盛り上がるか不安」「進行が苦手」「何を選べばいいか分からない」などの共通の悩み
レクリエーションへの苦手意識は、「ちゃんとやらなきゃ」というプレッシャーから来ていることが多いものです。
「うまく盛り上がるか?」「誰も笑ってくれなかったらどうしよう」「このネタで本当に大丈夫?」そんな不安が、行動のブレーキになってしまいます。
実際、ベテラン職員でもレクのたびに「今日は何にしようか」と迷うことは珍しくありません。悩むのは、利用者に喜んでもらいたいという思いがあるからです。
だからこそ、完璧を目指すのではなく、「楽しめる雰囲気づくり」ができていれば十分なんです。
でも大丈夫。大切なのは“無理せず楽しめる工夫”だけ!
レクリエーションで一番大切なのは、「内容」ではなく「雰囲気」です。
つまり、職員が楽しんでいれば、その空気は自然と利用者にも伝わります。
「難しいことはしなくてOK」「失敗しても笑ってしまえばそれでOK」このくらいの気持ちで取り組んだ方が、レクは案外うまくいくものです。
今回は、そんな「苦手でも乗り切れる」「これだけやっておけばOK」というシチュエーション別の簡単レクを7つご紹介します!
シチュエーション別おすすめレク7選【これだけやればOK】

予定外で急にレクを任されたとき
急に「今からレクお願いします!」と言われたときでも、あわてなくて大丈夫です。
そんなときは、座ったままでもできて道具も不要な「連想しりとり」が最強の味方です。
たとえば、「くだもの」→「のり」→「りんご」など、しりとりの中に“連想”を入れるだけで、脳が自然と活性化し、笑顔も生まれやすくなります。
「今日はしりとりですが、テーマは“食べ物”です! じゃあ、最初は“ごはん”から!」と始めればOK。失敗しても笑いに変えられるので、進行もラクです。
準備ゼロで即スタートできるので、ピンチのときに覚えておくと安心です。
その他のおすすめレク:
- 制限つきしりとり:例「た行で始まるものだけ」などルールを加えるとゲーム性UP。
- 古今東西ゲーム:「○○といえば?」に答えていくテンポの良いレクで、急な場面でも盛り上がる。
道具なし・準備なしで乗り切りたいとき
「道具も何もない! どうしよう!」というときは、カラダ一つでできる「グーパー体操」と「口じゃんけん」がおすすめです。
グーパー体操は、「グーは手を閉じる、パーは開く」という簡単な動作を交互に繰り返す体操で、リズムに合わせて声を出すことで認知機能にも刺激になります。
口じゃんけんでは「言う手と出す手を変える」など、簡単なのに脳が混乱して思わず笑ってしまうゲーム性が魅力です。
笑いも出て、時間つぶしにもなるので、準備がなくても焦らず使えます。
その他のおすすめレク:
- ジェスチャーゲーム:お題に合わせてジェスチャーだけで表現、座ったままでも実施可能。
- 私は誰でしょう?:職員や有名人の特徴をヒントにして当てるゲーム。場の空気が和らぎます。
初めてのレク進行で緊張しているとき
レクの進行を任されると、「盛り上がらなかったらどうしよう」と不安になりがちです。そんなときは、音楽の力を借りましょう。
童謡や昭和の名曲の“出だし”を流して当ててもらう「イントロドン」は、世代を超えて盛り上がるレクリエーションです。知っている曲が流れると、自然に笑顔になり、会話も増えます。
「分かった方は手を挙げてくださいね」と進行もシンプルなので、初めてでも安心して取り組めます。
場の空気が和むので、緊張もほぐれやすくなります。
その他のおすすめレク:
- 私は誰でしょう?(職員編):職員の特徴を当てるゲーム。身内ネタで場が和みます。
- 3択クイズ(○×でも可):簡単な問題を選択肢形式で出題。全員が答えやすいのが特長。
午後の眠気タイムに眠気覚ましレク
午後の時間帯は利用者も職員もついウトウトしがち。そんなときは、少し体を動かすレクで眠気を吹き飛ばしましょう。
風船バレーは、椅子に座ったままでできる軽運動で、誰でも参加しやすく、自然と声も出てきます。途中に「笑い体操」を入れることで、心も体も一気に活性化します。
失敗しても笑える、力を抜いてできるレクだからこそ、午後のゆるんだ時間帯にぴったりです。
マンネリ防止にもなり、施設全体の空気も明るくなります。
その他のおすすめレク:
- タオル体操:フェイスタオルを使って、軽い運動+ストレッチ。
- 新聞破りゲーム:手の力で新聞紙をできるだけ細くちぎる。ちょっとした競争も楽しめる。
認知症の方が多いフロアでの対応
認知症の方が多い場面では、「覚えていない」「わからない」と感じさせないレクが大切です。
そこで有効なのが、昔の思い出を語ってもらう“回想法”を取り入れたレクリエーションです。例えば「これは何に使う道具でしょう?」と昭和の道具を見せて、話を聞くだけでも十分です。
「懐かしいね」「昔こうだったよ」といった声が自然と出て、利用者の自己肯定感を高めるきっかけにもなります。
特別なスキルは必要なく、会話を大事にするだけで成立するレクです。
その他のおすすめレク:
- 写真アルバムトーク:昔の風景や行事の写真を見ながら自由に話してもらう。
- 昭和の歌当てクイズ:歌詞の一部を読み上げてタイトルを当てる。懐かしさで記憶がよみがえることも。
※ 認知症について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ninntisyou-syoujou-kaisetu/
男性利用者が多く参加しにくい雰囲気
レクは女性の方が参加率が高くなりがちで、男性利用者が遠慮しがちなこともあります。そんなときは“競技性”と“知的好奇心”をくすぐる工夫が有効です。
新聞を丸めた棒を使った「棒サッカー」は、勝敗のあるゲーム要素があり、男性の参加意欲を引き出しやすいです。終了後に「都道府県クイズ」を行えば、頭の体操にもなります。
少し“勝ち負け”の要素がある方が燃える方も多く、自然と参加率も上がります。
「みんなで競う」ことで空気が一体化しやすくなります。
その他のおすすめレク:
- 釣りゲーム(マグネット):魚を狙って釣り上げる、集中力と達成感が魅力。
- カラオケタイム(男性曲中心):演歌や青春時代の曲で「俺も歌ってみようかな」の一言が出やすい。
時間が余った時の“つなぎレク”
「思ったより時間が余っちゃった…」そんな場面で便利なのが、短時間でも使える“つなぎレク”です。
後出しジャンケンは、「私に勝ってください、チョキを出しますよ〜」といった形で、参加者が一瞬で判断して手を出すゲームです。単純だけど笑いが出やすく、場があったまります。
最後に手遊び歌(「むすんでひらいて」など)をゆっくり一緒にやれば、自然にクールダウンできます。
予備として持っておくと、どんな場面でも活躍します。
その他のおすすめレク:
- しりとりタイム:人数に応じて回しながら、ゆっくりつないでいくだけでも場が落ち着きます。
- タオル送りゲーム:輪になってタオルを音楽に合わせて送る。止まった人に質問など入れても面白い。
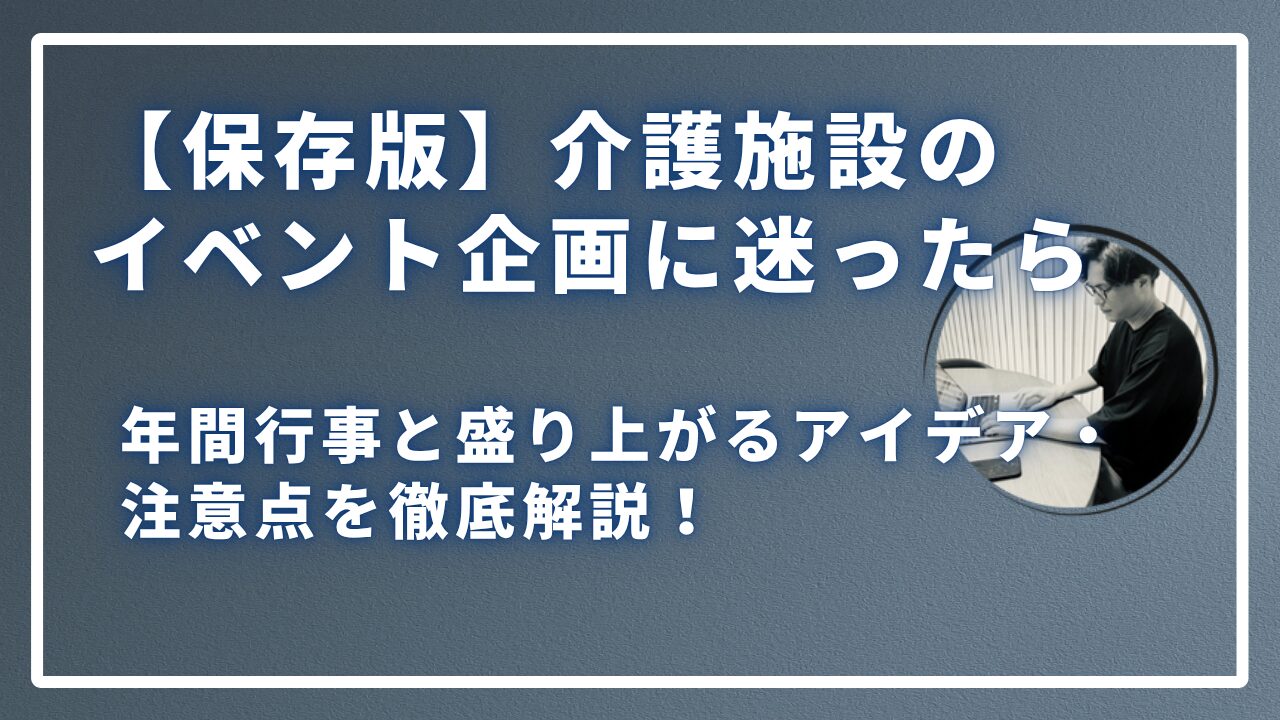
レクリエーションがうまくいく3つのコツ

「進行」より「雰囲気」づくりが大事
レクリエーションで一番大事なのは「うまく進行すること」ではなく、「その場の空気が楽しいこと」です。
完璧な進行や計画通りの進行は、必ずしも必要ではありません。
レクの現場では、予定していたルール通りに進まなくても、利用者さんが笑ってくれていれば“成功”です。アドリブが入ったり、順番がぐちゃぐちゃになったりしても、それもまた一興。
「進めなきゃ」と力まず、「楽しい空気」を意識すれば、自然と進行もスムーズになります。
何より“その場の温度”を大切にしてみてください。
笑顔で大きな声+利用者さんをとにかく褒める
レクを進めるときには、内容以上に「職員の表情と声」が雰囲気を左右します。笑顔で話し、聞き取りやすい声で進行するだけで、参加率や空気感がガラッと変わります。
さらに、「いいですね!」「すごい!」「ナイス!」など褒める言葉をたくさん使うと、利用者さんのやる気がぐんと高まります。たとえ間違っても、「惜しい!よく覚えてましたね」と前向きに返すのがコツ。
声かけと褒め言葉が自然に出るようになると、自分も周囲も楽になります。
とにかく笑顔と声、それが一番の武器です。
職員も一緒に楽しむことで“場が和む”
職員が楽しそうにレクをやっていると、それだけで場の空気は明るくなります。逆に、職員が緊張した顔で進めていると、それは利用者にも伝わってしまいます。
たとえば、ジャンケンやクイズでちょっと間違えて笑ってみせたり、利用者と一緒に拍手したり…。そういう「一緒に楽しんでる感」が、場を和ませ、信頼感にもつながります。
無理に盛り上げなくてもOKです。職員が“楽しんでいる姿”が、一番の空気づくりになります。
まずは自分から、「ゆるく楽しんでみよう」と意識してみましょう。
※ 利用者ファーストについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaisetu-stafffast/
【まとめ】苦手でも「シンプルに1つ」できれば大丈夫!

「何をやるか」ではなく「一歩踏み出す」ことが大切
レクリエーションで本当に大事なのは、「完璧な内容」でも「特別な道具」でもなく、「まずやってみる」という一歩です。
どんなにシンプルなレクでも、最初の声かけがあるかないかで、参加率や雰囲気は大きく変わります。
たとえば、「しりとりやりましょうか?」の一言でも、利用者さんは安心して参加できます。
その場の空気に合わせて柔軟に対応できるのは、専門的な技術よりも「やってみよう」という気持ちです。
苦手意識をなくすには、まず“始めてみること”。それが何よりの成長の第一歩です。
無理に盛り上げようとしなくてOK
「盛り上げないといけない」「笑わせないとダメ」なんて思わなくて大丈夫です。
レクに求められるのは、“派手な演出”よりも“心地よい時間”です。
利用者さんにとっては、「一緒に過ごす時間」「自分の話を聞いてもらえる場」が何よりの喜び。たとえゲームが静かでも、会話がはずめばそれで十分にレクの目的は果たせています。
無理して笑いを取らなくても、焦らなくてOK。
“そばにいてくれる安心感”が、最高のレクリエーションなのです。
今日紹介した7選から「1つだけでもやってみる」だけで十分です!
今回ご紹介した7つのシチュエーション別レクは、すべて「簡単」「準備不要」「一人でもできる」ものばかりです。
その中から、まずは「これならできそう」と思えるものを1つだけ選んで、実際にやってみてください。
最初の成功体験があれば、次は2つ、3つと自然にレパートリーが増えていきます。
「自分にもできた!」という感覚は、どんなマニュアルよりも大きな力になります。
レクは“数”より“気持ち”です。
1つだけでいい。まずは、そこから始めてみましょう。

コメント