介護の現場で働くうえで、リスクマネジメントは利用者と職員双方の安全と安心を守る重要な取り組みです。
本記事では、介護事故の予防から対処、チームでの情報共有、仕組みづくりまで、具体的かつ実践的な方法をわかりやすく解説します。
介護のリスクマネジメントとは?その目的と重要性を解説

利用者の安全確保
介護のリスクマネジメントの最も重要な目的のひとつは、利用者の安全を守ることです。
介護施設では、要介護者が日常的に身体的・認知的なリスクを抱えており、転倒、誤薬、誤嚥といった事故がいつ起きてもおかしくない環境にあります。こうした事故を未然に防ぐには、事前にリスクを予測し、適切な対策を講じることが不可欠です。
例えば、転倒リスクの高い利用者には、歩行器や滑り止めマットの使用、夜間の動線に照明を設置するなどの工夫を行うことで、安全性が格段に高まります。誤嚥の可能性がある方には、食事形態の調整や嚥下体操の導入など、個別性に応じた支援も大切です。
リスクマネジメントの取り組みは、ただの業務負担ではなく、利用者がその人らしい生活を安心して送るための基盤となります。職員全体で意識を高め、継続的に見直すことが、安全な介護の第一歩なのです。
訴訟・クレームリスクの軽減
介護の現場では、ちょっとした判断ミスや見落としが重大なトラブルに発展することがあります。その結果として、家族からのクレームや法的トラブルに発展するリスクも否めません。リスクマネジメントは、こうした事態を未然に防ぐための強力な盾となります。
クレームや訴訟の背景には、事故そのものの問題だけでなく、職員の説明不足や対応の不備、記録の不備といった「見えないリスク」が潜んでいることも少なくありません。事故が発生した際に、状況を正確に記録し、家族へ誠実な説明を行うだけでも、信頼関係の損失を防ぐことができます。
過去に、転倒事故の直後に速やかに対応し、家族に経過や今後の対応を丁寧に説明したことで、逆に「安心しました」と感謝されたという事例もあります。誠実な対応は、信頼の維持とトラブル回避の鍵となるのです。
リスクマネジメントは、「備え」としての役割を果たすだけでなく、施設運営全体の信頼性を高める力を持っています。
働きやすい職場環境づくり
リスクマネジメントの視点は、利用者だけでなく職員自身の安全と働きやすさにも直結します。明確な対応マニュアルや定期的な振り返りがあることで、職員は安心して業務に取り組めるようになります。
不安や緊張の多い介護現場では、「何かあったときにどうすればよいか」が共有されていないと、職員が萎縮したり、誤った判断をしてしまうリスクが高まります。しかし、リスクマネジメントが浸透している職場では、事故発生時にも冷静に行動できる環境が整っており、心理的安全性が高くなります。
たとえば、ある施設では「ヒヤリハット共有ノート」を設置し、職員が気軽に気づきを書き込める仕組みを導入したところ、業務ミスが減少し、職員間の信頼関係も向上したという成果が報告されています。
介護のリスクマネジメントは、「事故を防ぐための取り組み」という枠にとどまらず、職員の安心・やりがいにもつながる職場づくりの土台となります。
※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/
【事例付き】介護現場で頻発する事故とヒヤリハット

浴室での転倒/ベッドからの転落
介護現場で最も多い事故の一つが、浴室での転倒やベッドからの転落です。
水気のある場所や移乗時の不安定さは、事故を引き起こしやすい環境であり、細心の注意が求められます。
浴室では、床が滑りやすく、足元のふらつきや手すりの不使用が転倒の原因になります。また、ベッドからの転落は、深夜や早朝の移動時など、職員の目が届きにくい時間帯に発生しがちです。
具体的な事例として、ある利用者が浴槽をまたぐ際に足を滑らせ転倒。幸い軽傷で済みましたが、翌日からはシャワーキャリーを活用し、移動の際には必ず職員が付き添う体制に変更。以降、同様の事故は起きていません。
こうしたリスクに対しては、設備面の工夫(滑り止め、手すり、センサー付きベッド)と、介助時の声かけ・手順の確認が非常に重要です。
食事中の誤嚥・窒息/誤薬
食事や服薬は日常的な場面であるだけに、リスクが見落とされやすいのが現実です。しかし、誤嚥による窒息や誤薬は、命に関わる重大な事故に直結します。
高齢者は嚥下機能が低下していることが多く、普通の食事でも注意が必要です。また、薬の種類が多く、名前も似ていることから、配薬ミスが起こる可能性も高いのです。
実際に、ある利用者が「お茶と一緒にパンを食べた瞬間にむせて顔色が変わった」という事例がありました。すぐに職員が背部叩打法を実施し、事なきを得ましたが、以降は食事の前に嚥下体操を取り入れ、職員全員が誤嚥対応の研修を受けるようになりました。
事故を防ぐには、日々の食事や服薬場面を“危険が潜む瞬間”と認識し、マニュアルと教育を徹底することが必要です。
利用者の持ち物紛失や破損
利用者の所有物の紛失や破損は、一見小さなトラブルのように思われがちですが、信頼関係を損なう大きなリスクです。とりわけ思い出の品や高価な持ち物であれば、家族からのクレームや損害賠償に発展するケースもあります。
原因の多くは、共有スペースでの取り違いや、洗濯・清掃中の誤管理にあります。物品管理のルールがあいまいだったり、チェック体制が整っていない場合に発生しやすい問題です。
ある施設では、入所者が肌身離さず持っていた腕時計が洗濯時に紛失する事故が起きました。施設ではすぐに原因を調査し、洗濯物の個別タグを導入、チェックリストを作成する仕組みに改善。以降、紛失トラブルは激減しました。
利用者の物品は「大切な記憶の一部」であることを忘れず、丁寧な対応を心がけることが信頼と安心につながります。
実例から学ぶ「予防可能な事故」
介護事故の中には、未然に防げたものも少なくありません。こうした予防可能な事故に共通するのは、「リスクを想定していなかった」ことと、「情報共有が不十分だった」ことです。
転倒事故ひとつをとっても、直前にふらつきが見られていた、普段と違う行動パターンがあったなど、予兆はあったケースが多く報告されています。それらの情報を日報や申し送りで共有し、行動パターンの変化に早めに対応できていれば、防げた事故も多いのです。
ある現場では、「毎朝の歩行時のふらつき」が確認されていた利用者が、夕方に自室で転倒し骨折。職員の間では危険性が認識されていましたが、対策が講じられていませんでした。この事例を受け、フロア全体での危険予知トレーニング(KYT)を導入し、共有を強化。以降、同様の事故は大幅に減少しました。
介護事故を“防げるもの”として捉える視点と、職員間の密な連携が、事故予防の大きな力となります。
介護事故を防ぐ!リスクマネジメント実践5ステップ

リスク事例を把握する
介護事故を未然に防ぐためには、まずどのような事故が起こり得るかを正しく把握することが出発点になります。
現場で起きうる「リスク」の全体像を知っておくことで、職員は日々の業務の中で意識的に注意を払うことができるようになります。
たとえば、転倒・誤薬・誤嚥・転落・物品の紛失といった事例は、厚生労働省の資料や各施設の過去の記録などをもとに事前にピックアップすることができます。特に「ヒヤリハット報告書」などは、未遂に終わったリスクの宝庫です。
実際に、ある施設ではヒヤリハットを月次で収集・一覧化し、年度初めに「重点リスク」として掲示したことで、職員の意識が変わり、リスク感度の向上が見られました。
事故を防ぐには、まず“何が起きうるのか”を可視化することが第一歩です。
リスクを分析する(4Mなどを活用)
次のステップでは、把握したリスクをただ羅列するのではなく、原因や背景を分析することが重要です。
その際に有効なのが「4M(Man, Machine, Media, Management)」という分析手法です。
「Man=人」「Machine=設備・機器」「Media=環境」「Management=管理体制」という4つの観点から原因を探ることで、見落とされがちな根本要因まで掘り下げることができます。
たとえば、夜間の転倒事故があった場合、「Man=職員の配置」「Machine=センサーが故障していた」「Media=照明が暗かった」「Management=リスクの申し送り不足」といった複合的な原因が考えられます。
ある施設では4Mを使って分析を行い、「夜勤者が巡回中にセンサーの不具合に気づいていなかった」ことが判明。その後、センサーの点検体制が強化され、同様の事故が発生しなくなりました。
分析は、対策の質を高めるための土台となります。感覚的な反応ではなく、構造的に原因を探る姿勢が欠かせません。
防止策・対処策を立案する
リスクの分析結果を踏まえて、具体的な防止策や万が一の際の対処法を考えることがリスクマネジメントの中心です。このステップが曖昧だと、対策が場当たり的になり、再発のリスクが高まります。
重要なのは「誰が」「何を」「いつまでに」「どうするか」を明確にし、実現可能な内容に落とし込むことです。設備面の改善だけでなく、介助手順や声かけなど日常の行動も見直し対象に含めるべきです。
たとえば、転倒リスクが高い利用者には、毎日の移動時に職員が必ず付き添うルールを作成し、チェック表で確認する仕組みを取り入れた事例があります。
再発防止策は「実行可能」で「現場に馴染む」ものでなければなりません。職員の目線に立った設計が成功の鍵となります。
チーム内で共有・マニュアル化
立案した防止策や対応策は、必ずチーム全体で共有し、共通認識として定着させる必要があります。
一部の職員しか知らない対策では、現場全体として機能しないからです。
共有の方法としては、定例会議での報告、ヒヤリハット掲示板の活用、簡易マニュアルの配布などが有効です。また、OJTやミニ研修などを通じて、日々の業務に自然に浸透させる工夫も求められます。
ある施設では、事故後の対応フローチャートを作成し、事務室やナースステーションに掲示することで、緊急時の行動に迷いがなくなったという成功事例もあります。
「知っているだけ」では事故は防げません。「現場で実行される」ことにこそ意味があるのです。
実施後の振り返りと再評価
リスクマネジメントは一度やって終わりではありません。実施した対策が効果を上げたかを振り返り、必要に応じて再評価・改善することが不可欠です。
定期的な事故・ヒヤリハットの集計、職員へのアンケート、対応マニュアルの見直しなどを通じて、実態に即した運用が続けられているかを確認します。
たとえば、ある施設では毎月のリスクマネジメント会議で事故報告を分析し、改善点をチームで話し合う体制を構築。これにより「報告文化」が根づき、事故件数が年々減少しています。
振り返りは次の予防につながる貴重な財産です。リスクマネジメントを「回す仕組み」として捉え、継続することで効果が発揮されます。
事故やヒヤリハットが発生したときの適切な対応方法

応急処置
事故やヒヤリハットが発生したとき、まず優先すべきは利用者の安全確保と応急処置です。
この初動対応によって、被害の大きさが大きく左右されるため、迅速かつ冷静な判断が求められます。
出血・意識喪失・嘔吐などがある場合は、すぐに救急要請を行い、必要な処置を現場で行います。転倒の場合でも、安易に動かさず、専門職の指示を仰ぐなどの対応が必要です。
現場での対応力向上のために、救命講習や事故対応シミュレーションを定期的に行っている施設も増えてきています。こうした訓練が、いざというときの落ち着いた行動を支えます。
応急処置は、介護職員の責務であり、信頼に直結する重要なスキルです。
ご家族への報告
事故が発生した場合、ご家族への迅速かつ誠実な報告は信頼関係の維持に欠かせません。
事故内容を適切に伝え、施設側の対応と今後の再発防止策についても説明することが大切です。
報告は電話連絡に加え、必要に応じて面会の場を設けて丁寧に説明することが望まれます。その際、曖昧な表現は避け、事実と経過を簡潔に伝えることが求められます。
ある施設では、事故後24時間以内の家族連絡をルール化し、報告後にはフォロー電話を行う体制を整備したところ、家族からの信頼が向上しました。
家族への報告は、「報告=責任の明示」ではなく「誠実な対応」の一環であり、施設の姿勢を示す重要な場面です。
関係機関・上司への連絡
事故対応では、内部への報告体制も整備されている必要があります。
現場で起きた事故をすぐに上司や看護師、管理者へ伝えることが、適切な判断と支援を受けるための第一歩です。
さらに、重大な事故では、行政(市町村や監査担当)や保険会社、医師など外部の関係者への報告が求められる場合もあります。
ある施設では、「事故発生→上司→家族→医師・行政」の報告フローを掲示し、誰が何をするかを明確にして混乱を防いでいます。
適切な連絡体制が整っていれば、事故対応が速やかかつ正確に進み、事後処理のトラブルを防ぐことができます。
記録と原因分析
事故が発生した際には、必ず詳細な記録を残し、その後に原因を分析する必要があります。
これは事故防止策の改善にもつながり、職場全体のリスク感度を高める効果があります。
記録には「いつ、どこで、誰が、どのように」事故が起きたかを正確に記載し、主観を排して事実を客観的に残すことが求められます。その後、4Mなどのフレームワークを用いて原因分析を行うことで、再発防止策の方向性が明確になります。
実際に、分析結果をもとにトイレの構造を見直したことで転倒事故がゼロになった施設もあります。
記録と分析は、施設に蓄積される“知見”となり、次の事故を未然に防ぐ力になります。
適切な謝罪と再発防止策
事故後の対応で最も重要なのは、被害を受けた利用者とその家族に対する誠実な謝罪と、再発防止への姿勢を明確に示すことです。謝罪の際には、施設としての責任を明確にした上で、改善の取り組みについても丁寧に説明します。
単なる形式的な謝罪ではなく、「同じことを繰り返さない」という強い意志を示すことで、信頼関係の再構築につながります。
ある事例では、事故後すぐに謝罪・説明・対策を示し、半年後には家族から「対応が誠実だった」と感謝の言葉をもらったという報告もあります。
事故は“マイナス”な出来事ですが、その後の対応次第で“信頼”というプラスに変えることも可能です。
※ クレーム対応について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-claim-taisaku-7step/
介護事故におけるNG行動とそのリスク

記録の未記載、隠蔽
介護現場で絶対に避けなければならないNG行動のひとつが、事故に関する「記録の未記載」や「隠蔽」です。
これらの行為は、再発防止の妨げになるだけでなく、信頼関係の崩壊や法的トラブルに直結する重大なリスクを伴います。
記録が残っていなければ、後に振り返って原因を分析することができず、同じ事故が繰り返される可能性が高まります。また、事故の発覚後に記録がない、もしくは虚偽が明らかになると、施設全体の信用が失われ、訴訟や行政指導の対象にもなりかねません。
実際に、ある施設では転倒事故を記録せず、家族への報告も遅れたことで苦情が殺到。介護保険指定の一部停止処分を受けた例もあります。
事故発生時には、まず事実を正確に記録し、透明性のある対応を徹底することが基本です。記録の正確性と誠実さは、施設の信頼を守る防波堤となります。
利用者への誤った声かけ
事故が発生した際にありがちなミスが、「利用者への誤った声かけ」です。
焦りや緊張から不用意な言葉をかけてしまうと、利用者の不安を煽るだけでなく、心理的なダメージを与える可能性もあります。
「どうして動いたの?」「またですか?」といった言葉は、意図せずとも責めるように聞こえ、利用者の自尊心を傷つけてしまいます。特に高齢者や認知症の方は、言葉に敏感で、強く印象に残ることがあります。
ある現場では、転倒した利用者に対して「また倒れたんですね」と発言してしまい、それ以降、その方が歩行を拒否するようになったというケースがありました。本人の尊厳が傷つけられたことが原因でした。
事故時こそ、冷静に、思いやりを持った声かけが重要です。「大丈夫ですか?」「すぐにお手当しますね」など、安心感を与える言葉を意識的に使うことで、信頼関係を保つことができます。
チーム内の情報共有不足
事故対応において、チーム内の情報共有不足は致命的なミスを引き起こす原因となります。
誰が何を知っていて、どのような対応が行われたかが共有されていなければ、対策の統一も取れず、二次的な事故や混乱が生じる恐れがあります。
とくにシフト交代の場面や休日を挟んだ場合に、引き継ぎミスが生じやすく、「あの事故、知らなかった」という状態は非常に危険です。
たとえば、ある利用者が転倒したことを申し送りで伝え忘れたため、翌日も同じ場所で転倒を繰り返したという事例があります。このような場合、単純な連絡ミスが利用者の安全を脅かす重大事故につながるのです。
情報共有は、口頭の申し送りだけでなく、記録、チェックリスト、掲示物など複数の方法を併用し、確実に伝える仕組みづくりが重要です。チームで支えるという意識が、事故予防の強力な土台となります。
ヒヤリハットを組織で活かす!仕組み化のポイント

報告しやすい職場づくり
ヒヤリハットを組織の財産として活かすためには、まず「報告しやすい職場環境」を整えることが不可欠です。
報告がしづらい職場では、ミスやトラブルが隠されやすく、結果として同じ失敗が繰り返されるリスクが高まります。
「ミスを報告したら怒られる」「評価が下がる」といった空気があると、職員はリスク情報を共有しなくなります。その結果、施設として事故を未然に防ぐ機会を失うことになります。
ある施設では、「ヒヤリハットは“気づき”であり、責めない」を合言葉に掲げ、報告数が多い人を「安全意識が高い」と評価する制度にしたところ、報告件数が飛躍的に増加しました。
安心して報告できる文化は、事故予防の原動力となります。職員の声を受け止める柔軟な組織風土を育てることが、リスクマネジメントの第一歩です。
PDCAサイクルの導入
リスクマネジメントを継続的に機能させるためには、「PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)」の導入が効果的です。
単発的な対応ではなく、計画→実行→評価→改善を繰り返すことで、施設全体の安全体制をブラッシュアップしていけます。
例えば、転倒事故が続いていた施設では、毎月の事故分析会議(Check)を通じて、転倒の時間帯と場所の傾向を把握。対応策(Act)として夜間見守り体制を強化した結果、事故数が半減しました。
PDCAの導入は、属人的な対応を防ぎ、組織としての成長を促します。記録と評価を“回す仕組み”として整備することで、リスクマネジメントは確実に成果を上げていきます。
リスクマネジメント委員会の設置
リスク管理を組織的に推進するには、専任の「リスクマネジメント委員会」の設置が有効です。
委員会が中心となって、事故・ヒヤリハットの分析、再発防止策の検討、職員教育の実施を継続的に行うことで、安全意識が施設全体に浸透していきます。
ある施設では、委員会が月に1回集まり、直近のヒヤリハットをテーマに「事例検討会」を実施。新人からベテランまで意見を出し合う場となっており、結果としてチーム全体の事故感度が高まりました。
個人では限界のある事故防止も、チームで取り組めば成果が出やすくなります。組織的な体制を整えることで、リスクマネジメントは継続性を持つ「施設文化」へと発展します。
定期的な研修と事例共有
安全な施設運営を支えるのは、職員一人ひとりの知識と意識です。そのためには、定期的な研修と事例共有の機会を設けることが非常に重要です。
事故やヒヤリハットの背景には、「知らなかった」「気づかなかった」という知識不足があることが少なくありません。研修では、過去の事例や最新のガイドラインをもとに学びを深め、事例共有会では実際の現場体験をリアルに伝えることで、理解が格段に高まります。
ある法人では、毎月1回15分間の「ショート安全研修」を実施。内容をポスター形式で掲示することで、視覚的にもリマインド効果を生んでいます。
継続的な学びの場がある施設は、自然とリスクマネジメント力が高まり、事故の少ない安心な職場になります。
介護職におすすめのリスクマネジメントツール・製品

転倒予防マットや見守りカメラ
介護現場での事故を減らすには、転倒予防マットや見守りカメラなどのツールを積極的に活用することが有効です。
これらの製品は、利用者の安全を守るだけでなく、職員の負担軽減にもつながります。
転倒予防マットは、万が一転倒しても衝撃を緩和できるよう設計されており、ベッドサイドやトイレ前などに設置することで事故の重症化を防ぐことができます。一方、見守りカメラは夜間や死角のあるスペースでの動きに迅速に対応でき、職員が少ない時間帯の見守りにも最適です。
ある施設では、転倒の多かった利用者の部屋にセンサー連動型カメラを導入したことで、転倒事故が減少しました。異常時にはアラームが鳴るため、スタッフも即時に駆けつけることが可能です。
機器は「補助」であり「監視」ではありません。利用者の尊厳を守りながら、安全なケアを実現するためのパートナーとして上手に活用していきましょう。
スタッフ間共有アプリ
情報共有のミスが介護事故につながることは少なくありません。こうしたリスクを減らすために、介護現場ではスタッフ間で情報を共有できるアプリの活用が注目されています。
日々の申し送りや、ヒヤリハット・事故の記録、利用者の体調変化といった情報をリアルタイムで共有できることで、チーム全体の安全意識と対応力が向上します。
紙ベースや口頭での申し送りでは、「伝えたつもり」「聞き逃し」などのトラブルが発生しやすく、特に夜勤者や短時間勤務の職員との連携に課題が残ります。一方、アプリを使えば、時間や場所に縛られず、誰でも最新の情報にアクセスできる仕組みが作れます。
実際に、ある施設では、共有アプリを導入したことで申し送りミスが減少し、夜勤中の判断ミスも大きく改善したという報告があります。また、記録が時系列で残るため、あとから振り返って原因分析をする際にも非常に有効です。
スタッフ全員が同じ情報を持っている状態をつくることは、安全なケアの基本。ICTツールの力を上手に取り入れながら、チームでの連携強化を図っていくことが、これからの介護現場には求められます。
業務支援ソフト
介護のリスクマネジメントを円滑に進めるうえで、業務全体を支援するICTシステムの導入は非常に効果的です。
業務支援ソフトは、介護記録の作成や情報の一元管理、ケア計画の可視化、リスクアセスメントの記録などを効率化し、ヒューマンエラーの削減と業務負担の軽減に貢献します。
こうしたシステムを導入することで、職員間の記録ミスや伝達ミスが減少し、必要な情報を必要なタイミングで確認・活用できる環境が整います。特に利用者の状態変化やヒヤリハットなど、リスクに関する情報を速やかに共有・分析できる点が大きな強みです。
ICTを活用した業務支援は、「作業の効率化」だけでなく、「安全で質の高い介護を実現するための仕組み」でもあります。職員が本来のケア業務に集中できる環境をつくることは、リスクマネジメントの根幹を支える重要な要素と言えるでしょう。
業務支援ソフトは、単なる「効率化ツール」ではなく、「安全とケアの質を両立させる仕組み」として、リスクマネジメントの中核を担います。
参考資料 KONICA MINOLTA 【事例あり】介護現場におけるICT導入の活用事例・メリットを解説

よくある疑問Q&A:介護リスクマネジメントの資格・制度とは?

リスクマネジメントに関する資格
介護職員がリスクマネジメントを学ぶ上で、活用できる資格や研修は複数存在します。
資格取得は知識を体系的に学ぶだけでなく、現場での判断力やチームへの指導力を高めるうえでも大きなメリットがあります。
代表的なものとして「ケアリスクマネジャー」や「安全対策担当者」などがあり、事故防止・緊急対応・法的責任・記録の取り扱いなど、幅広い視点で学ぶことが可能です。
資格を取得したある中堅職員は、「根拠を持って対応できるようになり、自信を持って後輩に指導できるようになった」と話しています。現場経験に理論が加わることで、事故対応の質は確実に向上します。
現場で起きるリスクに対して「なんとなく」ではなく、「なぜ・どうすべきか」と言える力を身につけるためにも、資格の取得は非常に有効です。
法定研修との関連
介護職員が受ける法定研修の中には、リスクマネジメントに関連する内容が数多く含まれています。
とくに「介護職員初任者研修」「実務者研修」「認知症介護実践者研修」などでは、事故予防・緊急対応・記録の重要性といったテーマが扱われています。
これらの研修では、事故を未然に防ぐための視点や、発生時の対応、記録方法などが事例を交えて学べるため、実践的なリスクマネジメント能力を育む機会となります。
介護保険施設では、新人職員に対し、入職直後から法定研修として、「事故防止対策研修」の実施を義務付けられ、初期対応のスキルを高めることが求められています。
法定研修は単なる形式ではなく、施設の安全文化をつくる出発点。内容を「自分ごと」として捉え直すことで、実効性が格段に高まります。
認知症ケアや重度者支援のリスク対応
認知症のある方や重度の要介護者に対する支援では、特有のリスクが数多く存在し、一般的な対策だけでは対応しきれない場面もあります。そのため、認知症ケアや重度者支援に特化したリスクマネジメントの視点が重要です。
たとえば、認知症のある方は、見守りから離れて歩き出す「徘徊行動」や、不安・混乱による暴力的言動が発生することがあります。一方、重度者では移乗・体位変換・食事介助時の窒息や皮膚損傷など、介助そのものに高度な注意が求められます。
「認知症介護実践者研修」や「認知症介護リーダー研修」などでは、こうした特性に応じたリスク対応が学べ、日常ケアの中で起こりうるトラブルの予防と対応を強化することが可能です。
すべての利用者に対して「一律の対応」ではなく、状態や背景に合わせた「個別的リスクマネジメント」ができる職員が、これからますます求められる時代です。
※ 認知症ケアについて詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/ninntisyou-syoujou-kaisetu/
在宅介護や人材不足時代にこそ求められるリスクマネジメントの考え方

利用者の尊厳と安全のバランス
介護におけるリスクマネジメントでは、「安全を確保すること」と「利用者の尊厳を守ること」の両立が不可欠です。どちらか一方に偏った介護では、利用者のQOL(生活の質)は保障されません。
たとえば、転倒を恐れて過度に歩行を制限したり、誤薬防止のために服薬の自由を奪うといった対応は、一見安全に見えても、利用者の自立性や意思決定の機会を奪ってしまいます。
ある施設では、転倒リスクの高い利用者に「歩行禁止」ではなく「職員付き添いでの散歩」を提案した結果、本人の表情が明るくなり、家族からも「生活の質が上がった」と評価されました。
リスクを完全にゼロにすることよりも、利用者の想いや行動を尊重しながら、安全な環境を整える工夫が、これからの介護には求められます。
ハラスメント・防犯・防災への対応
近年、介護現場ではリスクの対象が「事故」だけにとどまらず、ハラスメント・防犯・防災といった社会的リスクへの対応も求められています。これらは一見“介護とは関係ない”と思われがちですが、職場や利用者を守るうえで極めて重要です。
たとえば、職員が利用者や家族から暴言・暴力を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、職員の離職要因のひとつとされ、厚生労働省も対策を強化しています。また、施設への不審者侵入や災害発生時の避難誘導など、非常時対応のマニュアル整備と訓練は必須です。
ある法人では、年に2回の防災訓練と、全職員向けの「ハラスメント対策研修」を義務化。結果として、職員の不安が軽減され、働きやすい職場風土が醸成されました。
リスクマネジメントは「事故防止」だけでなく、「職場と利用者の安全を包括的に守る仕組み」として進化させていく必要があります。
※ 介護現場でのハラスメント対策について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigo-kasuhara-taisaku/
限られた人材で実施する工夫
深刻な人材不足が続く中で、リスクマネジメントの取り組みを「省略せず、しかし効率的に」行う工夫が必要です。
人手が足りないからといって、事故対策や情報共有をおろそかにすれば、むしろ現場は混乱し、トラブルが増えて負担が重くなってしまいます。
鍵となるのは、ICTやDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用、そして「小さく始めて現場になじませる」視点です。記録の簡素化、アプリによる情報共有、見守り機器の導入などは、人の手を補完しながら安全性を保つ有効な方法です。
たとえば、夜間の見守りをAIカメラに任せることで、職員の負担が減り、その分利用者対応に時間を使えるようになった施設もあります。
少人数でも「やれることを、確実にやる」体制があれば、限られた人材でも安心・安全な介護が実現できます。
【まとめ】リスクマネジメントで利用者も職員も安心できる職場を

現場で明日から実践できること
リスクマネジメントは大がかりな取り組みから始める必要はありません。
大切なのは、日々の業務の中で「事故を未然に防ぐ意識」と「冷静に対応する習慣」を職員一人ひとりが持つことです。
たとえば、「ヒヤリとしたことは必ずメモする」「利用者の動きに少しでも変化があったら他の職員に伝える」「事故発生時は必ず記録と共有を徹底する」といった、基本的な行動が大きな効果を生みます。
ある施設では、申し送り時に「今日の気づき共有タイム(5分)」を設けたところ、小さな異変にも職員全体で対応できるようになり、重大事故の予防につながったという実績があります。
明日からできる一歩を積み重ねることが、リスクの少ない職場をつくる最大の力になります。
継続的な仕組みづくりの重要性
リスクマネジメントは、単なる「事故対応マニュアル」ではなく、職場全体で継続して取り組む“仕組み”であることが重要です。一度対策を立てても、時間が経てば風化し、新たなリスクに対応できなくなるからです。
継続のポイントは、(1)ルールの見直し、(2)定期的な研修、(3)事例の共有、(4)職員の声を反映する仕組み、の4つです。特に、職員が「改善に参加できる環境」をつくることで、リスクマネジメントは“やらされ仕事”ではなく“自分たちの安全を守る仕組み”へと変わっていきます。
実際、ある法人では月に一度「事故防止カンファレンス」を開催し、職員から出た改善案をすぐに実行に移す体制を整えた結果、職員の満足度が上がり、離職率が下がったというデータもあります。
リスクマネジメントは「守り」の活動ではありません。利用者も職員も安心して生活・仕事ができる、未来志向の“職場づくり”そのものです。
【関連記事】転倒転落リスクの看護計画の立案手順と現場で使える目標・評価例を徹底解説
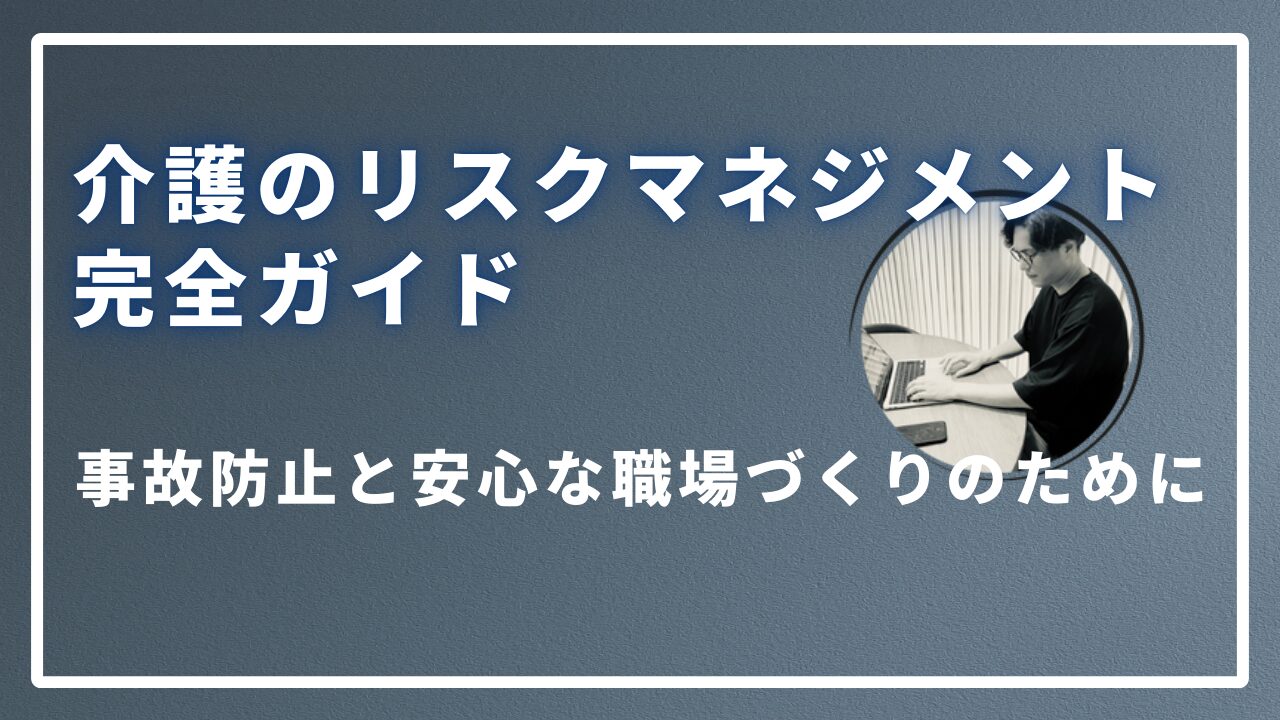
コメント