あなたが最後に食べたい料理は何ですか?――
もしその問いに、思い出の誰かの顔が浮かんだなら、あなたはきっとこのドラマに涙するでしょう。
2025年春、土曜の深夜に放送された特別企画『介護スナックベルサイユ』は、介護現場の「リアル」と、人と人との絆を、ファンタジックかつ温かい視点で描いた感動作。
「年寄り嫌いで他人を信じない若者」が、“思い出の料理”と出会いながら変わっていく…。
この物語を通じて、介護職の本当の魅力、そして“人を支える仕事”の尊さが、誰の心にも届くはずです。
この記事では、介護の世界を知らない人にも、現場で働く介護士さんにも届くように、ドラマの見どころとその意味を専門的視点から深掘りしていきます。
1. イントロダクション|「介護スナックベルサイユ」が今、話題の理由とは?

感動系×ファンタジー×介護という異色の組み合わせ
『介護スナックベルサイユ』が注目を集めているのは、「感動ドラマ」「ファンタジー要素」「介護現場のリアル」という一見ミスマッチな要素を見事に融合させた作品だからです。
これまでの介護を題材にしたドラマは、社会問題や高齢化の現実を正面から描く作品が多く、感動はあっても“夢”や“希望”を感じさせるものは限られていました。
しかし本作では、スナックという非日常的で懐かしい空間に“魔法のワイン”や“思い出の料理”が登場し、まるでおとぎ話のように展開しながらも、高齢者の人生と向き合うという深いテーマを描いています。
まさに、“介護×ファンタジー”という異色の切り口が、介護職だけでなく幅広い世代の視聴者に新しい驚きと感動を提供しているのです。
土ドラ特別企画での放送に注目が集まる
『介護スナックベルサイユ』は、東海テレビ×フジテレビ系の「土ドラ」特別企画として2025年春に放送され、その企画性とクオリティの高さに業界内外から注目が集まっています。
介護という専門的なテーマをゴールデンではなく、深夜帯で“あえて”放送することで、大人の視聴者層にじっくり届くよう設計された番組構成が特長です。
実際、初回放送後には「介護ドラマに涙したのは久しぶり」「久々に心が温かくなった」といった感想がSNSでトレンド入りし、再放送や配信希望の声も急増しました。
このように、“深夜ドラマ×感動ヒューマン×介護”という新たなスタイルが、今の時代にマッチし、多くの視聴者の心を動かしているのです。
若者と高齢者、そして“食”が織りなすヒューマンドラマの魅力
『介護スナックベルサイユ』が多くの人の心に残る理由は、若者と高齢者の世代を超えた交流を“食”という普遍的なテーマでつないでいる点にあります。
介護の現場では、食事が単なる栄養摂取ではなく、「思い出」「会話」「ケア」のすべてをつなぐ重要な場面であることが知られています。
ドラマ内で描かれる「最後に食べたい料理」は、高齢者の人生の記憶と深く結びついており、それを聞いた若者が心を動かされ、自身の価値観も変化していくというストーリー展開は、まさに“回想法(※1)”や“個別ケア”を連想させる構造です。
このように、介護職の魅力や介護の奥深さを、“思い出の料理”というドラマチックな演出を通じて描いたことで、専門職・一般視聴者問わず強く共感を呼んでいます。
※1 引用元 公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット 回想法 2019年11月 8日
「介護スナックベルサイユ」とは?あらすじと基本情報

物語の舞台は“介護スナック ベルサイユ”
『介護スナックベルサイユ』は、人生の終盤を迎える高齢者と、介護に関わる若者たちが出会う、特別なスナックを舞台にした感動ドラマです。
舞台となる“スナック ベルサイユ”は、一般的なスナックとは異なり、高齢者の“人生の物語”を料理とともに引き出す、まるで介護施設とカウンセリング空間を兼ね備えたような場所です。
主人公の若者・柊が初めてこのスナックに足を踏み入れた時、そこには懐かしさと温かさが満ちており、介護の現場で大切にされる“寄り添い”や“尊厳”が自然と描かれています。
このスナックは、ドラマの中で“理想の介護空間”を象徴する存在であり、視聴者に「こんな場所で最期を迎えられたら」と思わせるような深い感動を与えてくれます。
ワインと“思い出の料理”が心を癒す魔法のような空間
このドラマの大きな見どころは、“魔法のワイン”と“思い出の料理”が織りなす、幻想的で優しい空間の演出です。
ワインを一口飲むことで過去の記憶が蘇り、思い出の料理を口にすることで、人生の大切な場面が語られていくという展開は、まさに“回想法”そのもの。介護現場でも、認知症ケアや終末期ケアで用いられる重要なアプローチです。
たとえば第1話では、祖母との思い出の味噌汁がきっかけで、心を閉ざしていた主人公が涙を流すシーンが描かれ、多くの視聴者から共感の声が上がりました。
この“魔法のような空間”は、介護の本質である「心に寄り添うケア」を可視化したものとして、介護職にとっても深い学びとなるでしょう。
年寄り嫌いの若者が変わっていく成長物語
『介護スナックベルサイユ』のもう一つの魅力は、主人公・柊の変化を軸とした、ヒューマンストーリーの側面です。
柊は「年寄りはめんどくさい」「介護なんて絶対にやりたくない」と語る、典型的な無関心な若者。しかし、スナック・ベルサイユで出会った人々の語る人生や、料理に込められた想いに触れる中で、少しずつ価値観が変わっていきます。
特に、祖母の本音を知るエピソードでは、“介護される側の孤独”と“介護する側の戸惑い”の両面が描かれ、柊の心が揺れ動く様子がリアルに表現されています。
この若者の成長物語は、これから介護職を目指す人たちにとって、“仕事の意義”や“人と関わる力”の大切さを気づかせてくれる重要なメッセージとなっています。
放送日時、話数、ジャンルなどの基本データ
『介護スナックベルサイユ』は、東海テレビ制作・フジテレビ系列で放送される2025年春の土ドラ特別企画で、全2話構成の感動ファンタジードラマです。
第1話は3月22日(土)、第2話は3月29日(土)、いずれも夜23時40分から放送されました。深夜帯の放送でありながら、放送前からSNSや検索で「介護スナックベルサイユ」が話題となり、放送直後には「涙が止まらなかった」といった口コミが急増しました。
また、見逃し配信(TVer/FOD)や、今後の再放送の可能性もあり、介護施設や福祉関係者の間でも「職員教育や研修に使いたい」といった声も挙がっています。
介護を知らない人にも届くドラマでありながら、介護職の心にも深く残る。そんな“社会性”と“感動”を兼ね備えた作品です。
※ 介護職の転職を成功させる方法について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/careworker-jobchange/
豪華キャストが集結!登場人物とその魅力

主演・尾碕真花が演じる若者「柊」の成長ストーリー
『介護スナックベルサイユ』の主人公・柊を演じるのは、注目の若手女優・尾碕真花。彼女の繊細な演技が、若者の心の葛藤と成長をリアルに描き出しています。
柊は「介護なんて関係ない」「年寄りは苦手」と距離を取っていた若者でしたが、祖母の介護やスナック・ベルサイユでの出会いを通じて、他人と向き合う勇気を手にしていきます。
たとえば、第1話では、祖母との関係に葛藤を抱えつつも、思い出の料理を通して心を開いていく過程が丁寧に描かれ、介護現場でよく見られる“関係性の変化”が自然に表現されていました。
尾碕真花の演技は、介護職にとっても「若い世代がどう介護と向き合うのか」を考えさせられるきっかけとなるでしょう。
ベルサイユのママ:宮崎美子が醸す“包容力”
宮崎美子が演じる“ベルサイユのママ”は、このドラマの心臓部とも言える存在であり、包容力に満ちたキャラクターです。
ママは、訪れる客にそっと寄り添い、思い出の料理を注文させることで、その人の“人生の物語”を引き出す役割を担っています。その姿は、まさに“介護職の理想像”と重なる部分があります。
例えば、柊が戸惑いながらも高齢者の話を聞く場面で、ママがそっと背中を押すような助言をする描写は、介護現場における“支援者同士の連携”や“育成”の大切さを象徴しています。
宮崎美子の自然体で深みのある演技が、ドラマ全体に安心感と温かさをもたらしています。
チーママやバーテンダー、接客係たちが彩る“多職種連携感”
『介護スナックベルサイユ』には、チーママ(笛木優子)、マネージャー(木村了)、接客係(杏花)、バーテンダー(高山広)など、多彩なキャラクターが登場します。
彼らはそれぞれが異なる役割を担いながら、高齢者を支える“チーム”として機能しており、まさに“多職種連携”の象徴です。
ドラマの中では、スタッフが連携して一人の客を見守り、記憶を引き出す流れが描かれており、現場での“介護チーム”の動きと通じるものがあります。
登場人物がそれぞれの得意分野で支え合う姿は、介護職や福祉関係者にとって非常にリアルで、理想的なチームケアの一例として映るでしょう。
第1話・第2話のゲスト陣とエピソード紹介
本作では、毎回ゲストが登場し、それぞれの“人生の1ページ”を描く構成が採られています。第1話には草村礼子、小野武彦、萬田久子、石倉三郎ら、名バイプレイヤーが登場。
彼らが演じるのは、恋や家族の記憶に苦しみながらも、スナックでの語らいと料理によって癒されていく高齢者たち。その演技には、年齢を重ねたからこその深みがあり、自然と涙を誘います。
第2話では、夏樹陽子や片岡信和などが登場し、“母の味”や“祖母の願い”といったテーマを通じて、家族の絆と別れの描写が際立ちます。
ゲスト陣の存在感がストーリーを一層引き立て、回を追うごとにドラマ全体の完成度が高まっていることも、視聴者からの高評価につながっています。
介護現場を知る人ほど泣ける!感動ポイントの専門的視点

「最後に食べたい料理」という設定が語る“生きる意味”
『介護スナックベルサイユ』の象徴的な設定である「最後に食べたい料理」は、高齢者の人生そのものを映し出す重要な要素です。
介護現場でも、食は「生きる意欲」「思い出」「つながり」を支える存在であり、回想法や個別ケアにも頻繁に用いられます。
ドラマでは、亡き人との思い出が詰まった料理を通して、高齢者が過去を語り始め、そこに若者が耳を傾けることで世代を超えた対話が生まれます。
この設定は、ただの演出ではなく、“食を通じた尊厳あるケア”のあり方(※2)を提示しており、現場で働く介護士にとって深い共感を呼ぶ要素となっています。
※2 引用元 かいごgarden 「介護の三原則」とは?高齢者の尊厳を守るために欠かせない考え方 2023.03.29
スナック=小さなコミュニティとしての終末ケア
スナック・ベルサイユは、単なる飲食店ではなく、“終末期ケアの場”としての機能を持った小さなコミュニティです。
介護施設やグループホームなどでも、入居者が最期の時間をどこで、誰と、どんなふうに過ごすかは極めて重要なテーマであり、近年は“暮らしの継続”が重視されています。
ドラマでは、ママやスタッフが高齢者の話をゆっくりと聴き、思い出に耳を傾けるという流れが描かれており、それはまさに“看取りのケア”に通じる姿勢です。
スナックという場の持つ温かさと人との距離感が、理想的な終末期ケアを象徴しており、「最期はこういう場所で過ごしたい」と思わせてくれます。
若者×高齢者の関係性に見る「世代間交流」のリアリティ
ドラマの大きなテーマの一つは、若者と高齢者の“心の距離”をどう縮めるかという点です。
実際の介護現場でも、世代間の価値観の違いや接し方に悩む場面は少なくありません。しかし、心を開くきっかけがあれば、思わぬ交流が生まれることもあるのです。
『介護スナックベルサイユ』では、柊が高齢者の話を聞きながら変化していく様子が丁寧に描かれており、ケアの現場でも応用できる“信頼構築のヒント”が随所に見られます。
このリアリティは、現役介護職にとっても「自分たちの仕事が持つ可能性」を再確認させてくれる重要な気づきとなるでしょう。
現役介護職員が共感する“ケアの本質”が詰まっている
『介護スナックベルサイユ』は、派手な演出に頼ることなく、人の心に寄り添う“ケアの本質”を物語として描いています。
介護現場では、マニュアル通りにはいかないことばかり。それでも、相手の声に耳を傾け、小さな喜びを共有することでしか得られない信頼関係があります。
本作では、スタッフが客の人生に真剣に向き合い、「その人らしさ」を尊重する姿勢が一貫して描かれており、現場で働く介護職の理想像と重なります。
だからこそ、このドラマは介護職にとって“泣ける作品”であり、「この仕事をしていて良かった」と改めて感じられる、特別な一作なのです。
「食」が持つ力|介護×料理の奥深い関係

回想とともに出てくる料理=認知症ケアにも応用できる手法
『介護スナックベルサイユ』に登場する「思い出の料理」は、まさに認知症ケアにおける“回想法”と重なる演出です。
回想法とは、過去の体験や記憶を引き出すことで、認知機能や情緒の安定に働きかけるケアの方法であり、現在多くの介護施設でも実践されています。
たとえば、ドラマの中で高齢者が昔恋人と食べたカレーを注文し、当時の記憶を語り出す場面は、実際の介護現場における「食を通じた回想法」と同じ効果を持っています。
このように、“料理”というツールが高齢者の記憶にアクセスする手段として描かれていることは、介護の専門的観点から見ても非常に意義深いものです。
「思い出の味」で心をほぐす回想法の実践例
介護現場では、「懐かしい味」「母の味」といった“思い出の料理”が、高齢者の心を開く鍵になることが多くあります。
食事は五感すべてを刺激し、特に嗅覚や味覚は記憶と直結しているため、認知症の方が昔のことを急に思い出すことも少なくありません。
『介護スナックベルサイユ』では、登場人物たちが“あの頃の味”を口にした瞬間に、表情が和らぎ、心を開く描写が繰り返されます。これは、回想法が実際に効果を発揮する瞬間を再現したものであり、介護職員にとっては学びにもなるシーンです。
「食べること」には単なる栄養摂取以上の意味がある――そのことを、ドラマは繊細に伝えてくれています。
食事の場がもたらす心理的効果とコミュニケーション支援
介護の現場において、食事の時間は単なる生活の一部ではなく、人との関わりを深める“コミュニケーションの場”でもあります。
特に、高齢者が集う場所では、食卓を囲むことで笑顔が生まれ、自然と会話が始まり、孤独感が和らぐ効果が期待されます。
ドラマ『介護スナックベルサイユ』でも、スナックのカウンターで料理を囲みながら語り合う場面が多く登場し、視聴者に「食卓の力」を改めて実感させます。
こうした描写は、施設職員が日常的に提供している「共食支援」や「食事介助の在り方」に通じており、改めて“食のもつケア的な価値”を認識させてくれる内容です。
引用元:厚生労働省 高齢者にとっての「食べること」の意義 資料4−1
ファンタジーだからこそ描ける“理想の介護”のかたち

実際の現場では難しい“時間と心の余裕”をドラマで体現
介護の理想は、「一人ひとりの想いに寄り添い、丁寧に関わること」ですが、現場では人手不足や時間的制約により、それが難しいのが現実です。
『介護スナックベルサイユ』では、1人の高齢者に対して、スタッフがゆったりと時間をかけて話を聞き、想いをくみ取りながら料理を提供します。
たとえば、ある高齢者が「この味は父と最後に食べた料理だった」と語る場面では、職員が静かにその話を聴き、何も急かさずに寄り添う姿勢が描かれていました。
現場では叶いにくい“時間と心の余裕”を映像として見せることで、「理想の介護」の輪郭がより鮮明になるのです。
ベルサイユ=理想の介護空間?温かさと尊厳の共存
“スナック・ベルサイユ”は、非日常的な空間でありながら、「温かさ」「尊厳」「個別性」が共存する理想的なケアの場として描かれています。
介護施設においても、利用者が「自分らしくいられる」空間づくりが求められており、その理想がスナックという舞台に重なる点がユニークです。
ドラマでは、高齢者が昔の名前で呼ばれたり、普段の自分とは違う一面を引き出されたりする場面も多く登場し、“尊厳の保持”の重要性が印象的に描かれています。
ベルサイユは、「その人らしさを引き出す空間」として、介護の現場における“理想的な環境づくり”を示唆してくれる存在です。
介護職員が持つ「人を支える力」の再発見
『介護スナックベルサイユ』を観ると、介護職員が日々どれだけ“人の人生”に寄り添っているかを改めて感じさせられます。
料理をつくる、話を聴く、思い出を引き出す、涙に寄り添う――これらはすべて、介護職が普段行っている「ケアの本質」です。
たとえば、ドラマ内でスタッフが“その人にとって大切な瞬間”を理解しようとする姿は、実際の現場で私たちが取り組む「個別ケア」とまったく同じ視点です。
このドラマは、介護という仕事が「日常の中に奇跡を生み出す仕事」であることを可視化し、介護職員自身が“自分の仕事の価値”を再確認できるような、力強いメッセージを発しています。
「介護スナック」という新しい文化の可能性

介護×スナックという斬新なコンセプトの社会的意義
『介護スナックベルサイユ』が提示した「介護×スナック」という斬新な発想は、今後の介護業界にとっても新しい方向性を示すヒントになり得ます。
高齢化が進む日本では、“介護される場”と“交流する場”をどう組み合わせていくかが大きな課題となっており、スナックという親しみやすい空間はその有力な選択肢です。
実際に、認知症カフェや介護予防を目的とした「地域拠点」としてのスナック形式の集まりが、各地で広がりを見せています。
こうした試みは、高齢者と地域をつなぐ“交流のハブ”としての役割を果たすことができ、「介護スナック」という概念の社会的意義を裏付けるものです。
介護職に“華”と“語り場”を与える場所としての意味
介護の現場は常に忙しく、感情の整理や振り返りをする時間がなかなか取れないのが実情です。そんな中、ドラマで描かれた“スナックのような語り場”は、介護職員にとっての心の逃げ場としても非常に魅力的に映ります。
スナックには、ただ飲んで騒ぐのではなく、「語る・共感する・笑う」という側面があり、それは“ケアの本質”と非常に近い構造を持っています。
たとえば、劇中でスタッフ同士が1日の出来事を語り合う場面や、思い出を共有する姿は、介護現場で起こる“振り返り”や“共有”と同じ役割を果たしています。
このような“ケアする人のための場”として、介護スナックの可能性が見直されている今、福祉業界全体で“語りの文化”を大切にする動きが求められているのです。
現場で働く介護職員へのメッセージ|このドラマが教えてくれること

「誰かの人生に寄り添う」ことの重みと美しさ
『介護スナックベルサイユ』の中核にあるのは、「その人の人生をまるごと受け止める」という姿勢です。
介護職は、単に“お世話”をするのではなく、人生の最終章に寄り添う“人生の伴走者”ともいえる存在です。
ドラマでは、誰かの記憶に寄り添い、料理を通じて過去を共有しながら、少しずつ相手の心を理解していく姿が描かれています。
その過程は、私たち介護職員が日々取り組んでいる“傾聴”や“共感”そのものであり、「介護の仕事って、こんなにも美しい」と再確認できる内容になっています。
モチベーションが上がる、仕事の励みになるセリフの数々
『介護スナックベルサイユ』には、介護職にとって心に響くセリフが数多く登場します。それらは、厳しい現場で働く私たちにとって、“心の栄養”となるような力を持っています。
「誰かに必要とされるって、嬉しいことなんだな」「人の人生には、こんなにドラマがあるんだ」――そんな言葉に出会うたび、疲れた心がそっと癒されていくのです。
実際に、SNSでも「このセリフに救われた」「仕事に戻る勇気が出た」といった声が寄せられており、現場にいるからこそ響くメッセージが多く詰まっています。
こうしたセリフを通じて、介護職の誇りや意義を再確認できる点も、このドラマが“職業ドラマ”として優れている理由の一つです。
ケアの中にある“演出力”や“人間ドラマ”の再認識
介護職員の仕事には、常に「人間ドラマ」があります。そしてその背後には、実は“演出力”や“場づくり”の力が必要とされています。
利用者に安心してもらう空気感をつくる、信頼関係を築くタイミングを見極める、場を和ませる一言を添える――これらはすべて“感情のマネジメント”という意味で、立派な専門技術です。
『介護スナックベルサイユ』は、まさにその“見えないケアの技術”を映像化しており、視聴者に「介護職ってすごい」と思わせるだけでなく、職員自身にも「自分のやっていることに意味がある」と再認識させてくれます。
ケアとは、人の心を動かす“舞台演出”のようなもの――そんな視点をもたらしてくれるこのドラマは、現場に立つすべての人の心に灯をともす存在です。
一般視聴者へ|このドラマで介護に触れてみてほしい理由

介護=暗い・大変 という先入観が変わるチャンス
『介護スナックベルサイユ』は、これまで介護に対して「大変そう」「重そう」というネガティブなイメージを持っていた人々にとって、イメージを変える絶好の機会です。
多くの人が「介護=しんどい」「自分には無縁」と思い込んでいますが、本作では“温かい人間関係”や“人生の美しさ”が繊細に描かれており、まったく違う側面の介護を体感できます。
たとえば、人生の終盤にふさわしい「最後の晩餐」を通して描かれる家族の愛や、世代を超えた心のつながりが、視聴者の心に自然に響いてきます。
このドラマを見ることで、「介護ってこんなに温かくて希望があるんだ」と感じる人が増え、介護への先入観が変わるきっかけとなるでしょう。
世代を超えた“心の交流”は、誰にとっても身近なテーマ
『介護スナックベルサイユ』の魅力のひとつは、世代を超えた人間関係が丁寧に描かれている点です。
年齢や立場が異なっていても、人と人とが心を通わせる瞬間は、誰にとっても共感できるテーマです。
たとえば、主人公の若者・柊が、高齢者の話に耳を傾けることで自分自身の過去や家族と向き合っていく姿は、多くの視聴者に「自分もこうだったかもしれない」と感じさせるはずです。
このドラマは、親や祖父母との関係、自分の人生をどう歩むかといった普遍的なテーマをやさしく描いており、年代問わず誰の心にも届く作品です。
「親の介護」や「自分の将来」に役立つ視点が得られる
日本社会が超高齢化に向かう中で、「親の介護」や「自分の老後」は誰にとっても避けられない現実です。
『介護スナックベルサイユ』は、感動的な物語の中に、実際の介護のあり方や人生の終え方に関するヒントがちりばめられています。
たとえば、「最後に食べたい料理」というテーマは、親の好物や過去の思い出をあらためて考えるきっかけになり、「どんなふうに見送ってあげたいか」「どう生きたいか」と自分に問いかけるきっかけとなります。
この作品を通して、“介護は他人ごとではない”と実感できるはずです。ドラマが届ける“小さな気づき”が、これからの人生設計にも大きな影響を与えてくれるでしょう。
『介護スナックベルサイユ』放送情報と視聴方法

放送日・時間:2025年3月22日・29日(土)23時40分~
『介護スナックベルサイユ』は、2025年3月22日(土)と3月29日(土)の2週連続、フジテレビ・東海テレビ系列の「土ドラ特別企画」として放送されました。
時間は深夜23時40分からですが、「遅い時間でも観る価値あり!」と口コミで話題になっており、介護職の方が夜勤の合間に録画で楽しんでいるという声も多く聞かれます。
2話完結のため非常に見やすく、1話からしっかり物語が進んでいく構成になっており、見逃せない内容がギュッと詰まっています。
“限られた放送回数でここまで泣けるとは”という声もあるほど、濃密なストーリー展開となっています。
見逃し配信、再放送の有無、動画配信サービス情報
『介護スナックベルサイユ』は、地上波放送後に見逃し配信として【TVer】【FOD】で視聴可能となっています。
忙しくてリアルタイム視聴できない方や、もう一度感動を味わいたい方にとって、配信サービスは非常にありがたい手段です。
また、反響次第ではBSやCSでの再放送も予定される可能性がありますので、公式情報の更新を見逃さないようにしましょう。
介護職やご家族での視聴にもピッタリな構成なので、複数人での視聴や職場での共有にもオススメです。
SNSや公式サイトでの情報チェック方法
最新情報を確認するには、東海テレビの公式サイトや『介護スナックベルサイユ』の番組ページ、各種SNS(X/Instagramなど)の公式アカウントをチェックしましょう。
特にX(旧Twitter)では、放送中にリアルタイムで感想を投稿するユーザーも多く、共感の輪が広がっています。
また、出演者のSNSでも裏話や撮影風景が公開されており、ドラマへの親しみがさらに増します。
ドラマの感想を投稿する際には「#介護スナックベルサイユ」で検索・投稿するのがオススメです。
エンディング|「介護は、もっと希望に満ちている」
ドラマを観て、「介護って、こんなにドラマチックなんだ」「介護職って、実はカッコいいかも」と思ってもらえることが、この作品最大の魅力です。そして現場で働く私たちにとっても、このドラマは“自分たちの仕事の価値”を再確認させてくれるはずです。
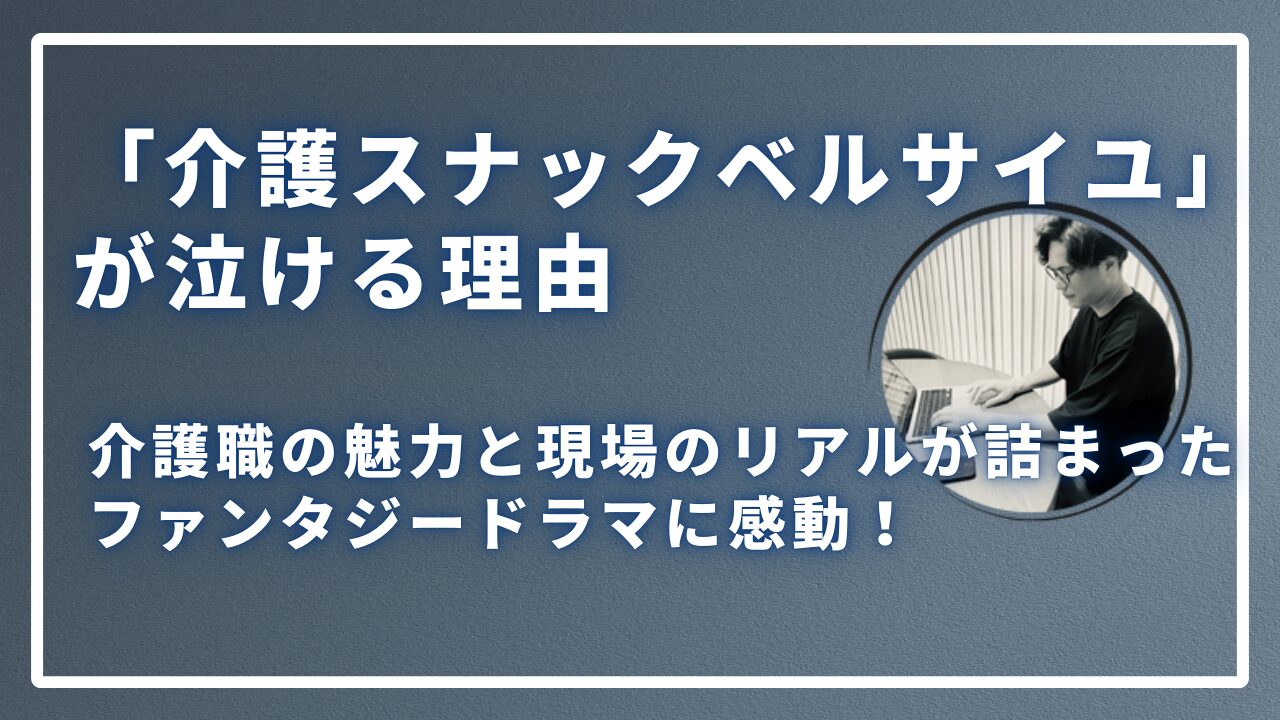
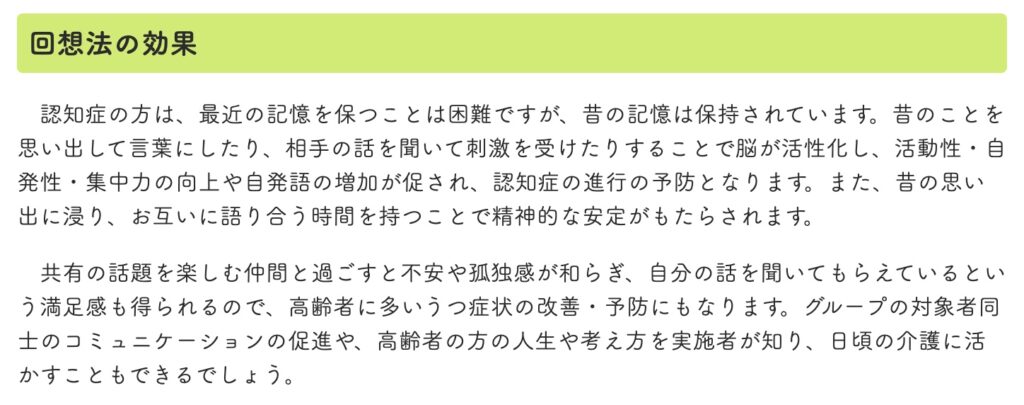
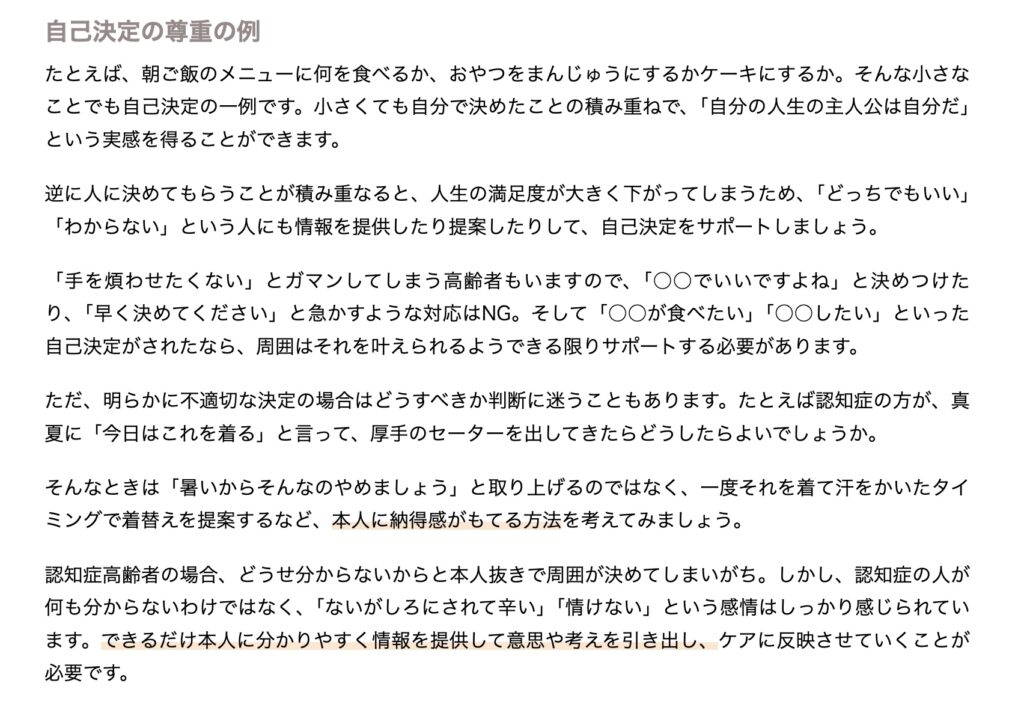
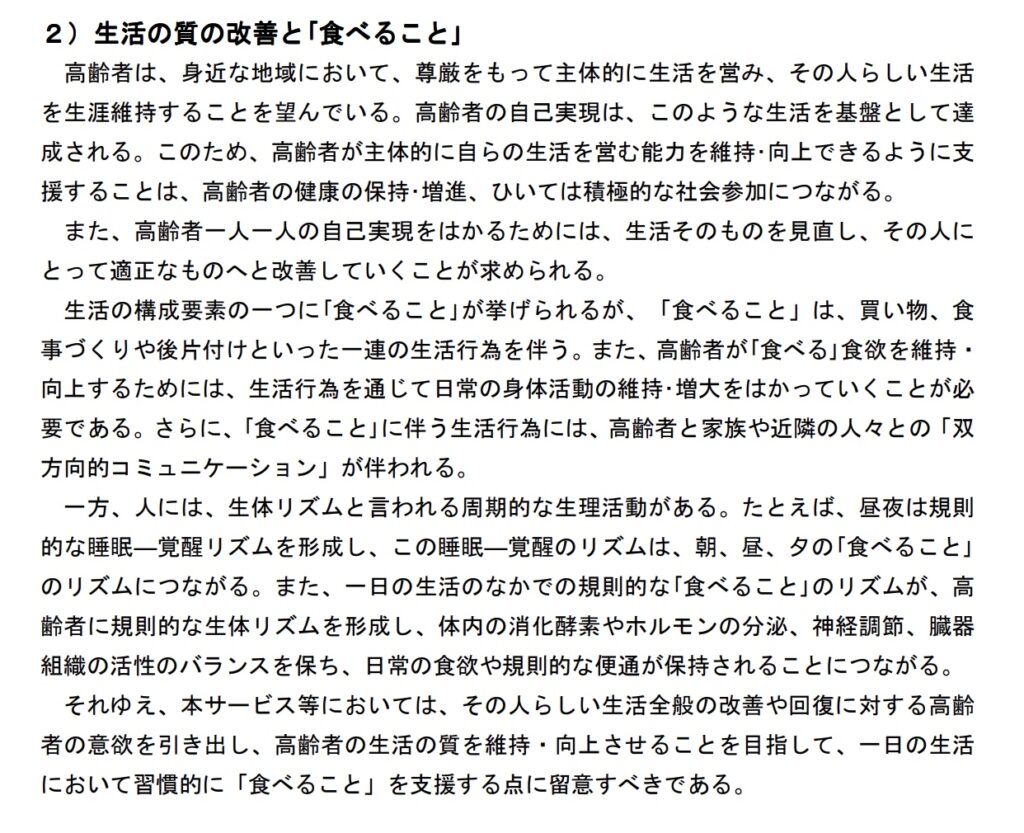
コメント