特別養護老人ホームとは?

特養の目的、介護保険制度の位置付け
特別養護老人ホーム(特養)は、介護が必要となり、在宅での生活が難しくなられた方が、長期的に安心して暮らせるようにするための施設です。
日本の高齢化社会において、特養は、重度の介護が必要な方々に対して、24時間体制で生活支援や介護サービスを提供します。介護保険制度の一環として運営されており、要介護3以上の高齢者を中心に受け入れています。
特養は、医療機関と連携しながら、施設で出来る範囲での医療的ケアも含めた総合的なサポートを行いますが、病院とは違いあくまで生活の場としての役割が強い施設です。
ポイント
入居要件は要介護3以上の認定を受けていること
病院ではないので治療は目的としておらず、あくまでも生活の場である
入居に関する基本事項
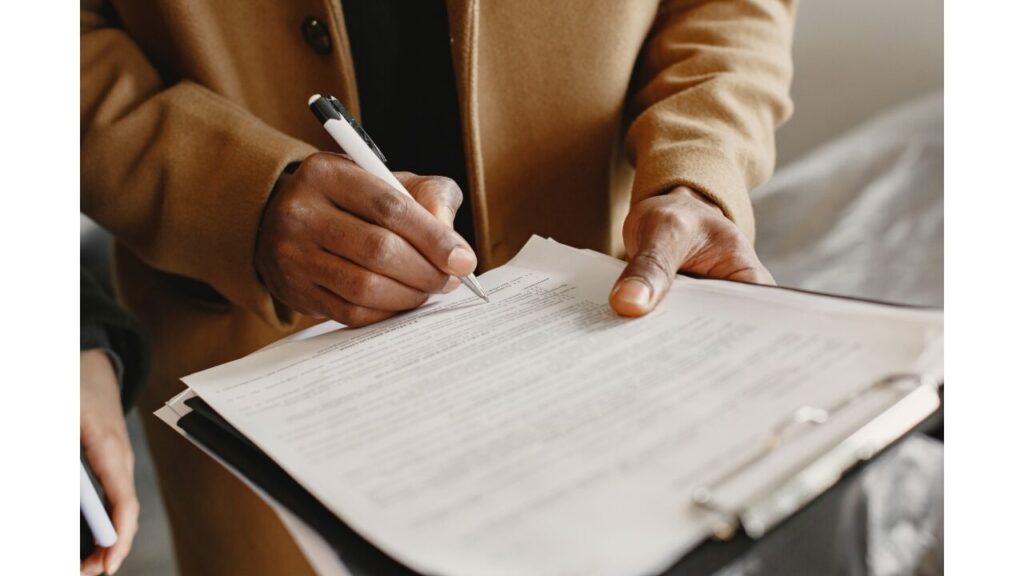
入居要件
入居には要介護3以上の認定が基本要件となっていますが、家庭状況や他の施設、サービスでの生活が困難な場合など、特例として要介護1・2でも入居が認められることがあります。
特養は、常に満床に近い状態であるため、入居までの待機期間が長くなることが一般的ですが、対象者の介護度、在宅生活が困難な理由によっては優先的に検討する場合もあります。入居希望者は早めに相談することをおすすめします。
ポイント
要介護3に満たなくても、特例で入居できる場合もある
待機者が多く申し込みしてもすぐ入居できない
料金体系
特養の料金は、介護保険の給付を受けつつ、自己負担額を支払う形となります。自己負担額は、施設利用料、食費、居住費、日用品費などから構成され、月額の支払額は個々の収入や資産に応じて異なります。低所得者には負担軽減制度があり、収入に応じた補助が受けられるため、負担が大きくなることを心配せずに利用できます。
食費や居住費は施設ごとに設定されているため、ホームページや、情報公表など事前にチェックすることをおすすめします。また、介護サービス以外にも、電気料金、レンタル品など利用する場合は追加費用が発生する場合があります。
ポイント
非課税世帯には介護保険負担限度額認定申請制度という減免制度がある
食費、居住費は施設ごとに設定されている
施設の種類と選び方

従来型とユニット型の違い
特養には「従来型」と「ユニット型」の2つのタイプがあります。従来型は大部屋での共同生活が基本となり、他の入居者と共に生活することが求められます。
一方、ユニット型は少人数のグループで生活するスタイルで、各入居者に個室が提供され、プライバシーが保たれやすい環境です。ユニット型は、より家庭的な環境で生活を送りたい方に適していますが、費用がやや高めになる傾向があります。
ポイント
従来型は多床室が中心で居住費が安価
ユニット型は個室でご自宅に近い環境であるが居住費が従来型に比べて高い
施設でのケアと医療対応

特養での医療(できること、できないこと)
特養では、基本的な健康管理や薬の管理、軽度の医療処置が行えます。例えば、血圧測定やインスリン注射、胃瘻経管栄養などは施設内で対応可能な場合が多いですが、施設の体制によっては在宅酸素、喀痰吸引(頻度や状況による)、鼻腔、腸瘻などは受け入れが難しい場合もあります。
特養は病院ではないため、高度な医療や緊急手術、集中治療などはできません。入居者の状態が悪化した場合や、病状が急変した場合には、すみやかに提携病院への転院が必要となります。
ポイント
医療依存度の高い方は入居が難しい場合がある
特養は薬の管理、軽微な処置、点滴管理などできることが限られる
病院との違い(医師の常駐、非常勤)
特養の殆どには常勤の医師はいませんが、非常勤の医師(嘱託医)が定期的に訪問し、入居者の健康チェックや簡単な治療を行います。
医療対応が必要な際には、施設内の看護師と協力して対応します。病院と比べると、医療体制は限定的ですが、生活の場としての環境を重視しているため、入居者は家庭に近い環境で暮らすことができます。
ポイント
医師は非常勤であることが多く、定期的な往診がある
看護師が医師の指示を受けて対応する
リハビリの有無、どの程度のリハビリ
リハビリは、入居者の身体機能の維持や改善を目指して行われます。
特養には機能訓練指導員という専門職が配置されています。個々の入居者に応じたリハビリプランが提供されます。
リハビリの内容は、主に日常生活動作の維持・向上を目指したものが中心で、歩行訓練や関節の柔軟性を保つための運動などを現場の介護職員と共に提供しています。病院で行われるような専門的で集中的なリハビリは提供されません。
ポイント
特養のリハビリは生活の中でのリハビリが中心
積極的なリハビリを望む方には適さない
生活の質を高めるための支援

外出、外泊の状況
特養では、入居者が定期的に外出や外泊をすることができるようにサポートしています。
外出は施設内での生活から一時的に離れて、家族との時間を過ごすためや気分転換を図るために行われることが多いです。
外泊については、事前に施設に申請を行い、家族と一緒に過ごすための外泊も認められます。ただし、コロナ禍により外出や外泊の機会が奪われてしまいました。
施設は入居者の体調や安全が最優先に考えていくため、施設によって判断は様々です。入居前に問い合わせ外出、外泊制限について確認することが必要です。
ポイント
積極的に外出、外泊支援をしている
コロナ禍により施設の判断で対応は異なる
入院した場合どうなるの
入居者が病院に入院した場合、特養のベッドは一定期間(最長3カ月)確保されますが、長期にわたる入院が必要となった場合には、一旦契約解除となることがあります。
この場合でも退院後には再度特養への入居を希望する場合には、再入居できるよう便宜が図られます。ただし、ベッドの空き状況によるので、家族や本人と施設が緊密に連携することが求められます。
ポイント
入院しても在籍扱いのまま(3ヶ月以内)
入院中も居住費は必要
いつまで入居できるの
特養は基本的に最期まで入居できます。ただし、前章に記載したように特養で管理できない医療依存が発生した場合には、状態に応じた医療施設への転居が求められます。
また、要介護度が軽減した場合にも在宅復帰か、引き続き特例入居を申請し、特養での生活を送るのか、本人、家族、施設職員で検討することになります。
ポイント
医療依存度が高くなると入居継続が困難
要介護1、2になれば、在宅復帰、転居、特例申請を検討する
家族との協力体制

看取りもしてもらえる
特養では、入居者が最期の時を迎える際に、看取りケアを提供しています。
看取りケアでは、入居者ができるだけ苦痛を感じずに、安らかな最期を迎えられるように、医療的な支援や心のケアが行われます。
家族にとっても、最期の時間を共に過ごすことができるようなサポートが提供されます。
ポイント
希望があれば看取りケアも可能
終末期をどのように迎えたいか親族間で考えておく(本人の意思がしっかりしているうちに検討しておく)
家族の役割
家族は、定期的な面会や施設との連絡調整、入居者の心身の状態を共有する役割を果たします。
家族の支えがあることで、入居者の生活の質が向上し、安心して過ごせる環境が整います。
特に看取りの際には、家族と施設の協力が不可欠です。入居者の最期の瞬間を共に迎えるため、家族ができるだけ寄り添うことが求められます。
ポイント
入居者にとって家族との時間は重要
施設職員、家族とが協力して入居者を支える
ケアの計画とトラブルへの対応

ケアプランとカンファレンス
特養では、入居者ごとに個別のケアプランが作成されます。ケアプランは、入居者の健康状態や生活習慣を考慮し、家族や介護スタッフ、医師、看護師などの専門職が協力して策定します。
定期的なカンファレンスを通じて、ケアプランの見直しや改善が行われ、入居者のニーズに合わせたケアが提供されます。
ポイント
カンファレンスは入居者の状況を共有できる場
必ず参加し施設への要望を伝えよう
トラブルの事例
特養で発生するトラブルの事例として、入居者間のトラブル、介護方法に対する家族の意見の違い、スタッフとのコミュニケーション不足などがあります。これらのトラブルに対しては、施設が迅速に対応し、家族と協力して問題解決を図ります。トラブルが発生した際には、カンファレンスでの話し合いや、専門家の助言を求めることが重要です。
ポイント
トラブルがゼロの施設は無い
トラブルに対して真摯に対応する施設かどうか見極める
入居者の生活環境とプライバシー

受診の対応
入居者が定期的な受診を必要とする場合、施設が受診の手配やサポートを行います。
家族が同行する場合もありますが、施設スタッフがサポートすることが一般的です。緊急時には、すぐに医療機関と連携し、適切な対応が取られます。
ポイント
定期的な受診対応は家族が対応する場合が殆ど
対応できない場合には、ヘルパー付きタクシーの利用も検討
携帯持ち込み可能?Wi-Fi環境ある?
特養では、入居者が携帯電話を持ち込むことが可能です。施設内にWi-Fi環境が整備されている場合も増えており、インターネットを利用したコミュニケーションや情報収集が容易に行えます。ただし、Wi-Fi環境の整備状況は施設によって異なるため、事前に確認が必要です。
ポイント
携帯は持ち込み可能だが、管理の責任までは施設に求められない
ポケットWi-Fiが持ち込みも可能な場合もある
カメラつけても良い?
入居者のプライバシーや他の入居者の権利を尊重するため、部屋にカメラを設置することは制限される場合が多いです。
特に、共用スペースや他の入居者が使用する部屋には、カメラの設置が禁止されることが一般的です。家族が入居者の安全を確認したい場合は、施設との相談が必要です。
ただし、近年ではICT化が進み、居室に見守りカメラを設置する施設も増えています。その場合にはプライバシー保護の観点から入居者、家族の同意のもと取り付けを行います。
ポイント
従来型とユニット型でプライバシーの観点は異なる
施設の体制として、見守りカメラが整備されているところもある
まとめ
特別養護老人ホーム(特養)は、高齢者が安心して生活を続けられるよう、生活のサポートを中心にサービスを提供する場所です。
しかし、施設ごとでサービス内容、入居にかかる費用など、事前に理解しておくべきポイントが多くあります。本人や家族の希望を尊重しながら、最適な施設を選びためには、十分な情報収集と施設見学が不可欠です。
また、家族との協力やトラブル対応も、入居後の生活の質を左右する大きな要素となります。このブログが特養選びにおいて皆様の一助となれば幸いです。

コメント