優秀な職員の退職は「突然」のようで、実は前兆が積み重なって起きることがほとんどです。結論から言うと、離職は「前兆の早期発見 → 24時間以内の初動 → 1on1で本音の原因特定 → 小さな改善の合意 → 30日フォロー」の流れで、防げる確率が上がります。
この記事では、介護現場で起きがちな「辞める前兆10選」をチェックリスト化し、管理者・リーダーがそのまま使える声かけ例/1on1質問テンプレ/改善提案の型まで、コピペで使える形でまとめました。
離職は「前兆→初動1on1→改善提案→30日フォロー」で止められる

離職対策で一番効くのは、制度やスローガンではなく「最初の24時間の動き」です。前兆に気づいたら、まずは詰めずに・急がずに・放置しない。その上で1on1で原因を言語化し、本人が「ここなら続けられる」と思える最小の改善を合意して、30日フォローまでセットで回す。これが王道です。
退職を考える職員の多くは、頭の中で「辞める理由の整理」と「辞めた後の見通し」を同時に進めています。ここに入ってしまうと、現場側が動いても手遅れになりがちです。だからこそ、“辞める”と決める前のサイン段階で介入する必要があります。
「最近元気がない」「報連相が減った」程度の段階で、短い声かけ→翌日までに1on1→小さな調整(夜勤回数・担当・ペア変更など)を1つだけ決める。これだけでも、気持ちが折れたまま退職へ進む流れを止められます。
ここから先は、前兆を見抜くためのチェックリストと、初動・面談・改善提案の具体策です。まずは、次のチェックリストで状況を可視化してください。
退職前兆チェックリスト(Yes/No)
当てはまるものにチェックを入れてください。3つ以上で要注意、5つ以上で“今週中に1on1推奨”です。
- □ 以前より笑顔や雑談が減った
- □ 挨拶や返事が短くなった/目が合いにくい
- □ 報連相が減った、情報共有に参加しない
- □ ミスが増えた、記録が雑になった
- □ 仕事のスピードが落ちた/動きが遅い
- □ 苦手業務・夜勤・委員会を避ける発言が増えた
- □ 有休を固めて取りたがる/急に休み希望が増えた
- □ 申し送りや会議で発言しなくなった
- □ 「どうせ変わらない」「もういいです」など諦め言葉が出る
- □ スキルの高い人ほど、周囲の負担を背負って疲弊している
介護職が辞める前兆(退職サイン)10選

退職サインは、派手な言動よりも「小さな変化」に出ます。特に優秀な職員ほど、揉めずに静かに準備を進めるため、周囲が気づきにくいのが特徴です。
優秀な職員は、業務を回しながら周囲にも配慮します。限界まで我慢し、ある日「決めました」となる。つまり、辞める直前よりも、その前の“静かなサイン”を拾えるかが勝負です。
1)雑談・笑顔が減る
表情の変化は最初のサインになりやすいです。
疲労・不満・孤立感が強まると、まずコミュニケーションに出ます。
休憩中に席を外す、談笑に入らない、目線が下がる。
「最近どう?」ではなく「最近忙しそうだけど負担増えてない?」と具体に声をかけましょう。
2)挨拶・返事が短くなる(目が合いにくい)
関係性の糸が細くなるサインです。
気持ちのエネルギーが切れてくると、最低限の反応だけになります。
返事が「はい」だけ、表情が固い、声が小さい。
評価や叱責ではなく、「いつもありがとう。最近大変そうで心配」とケアから入るのが効果的です。
3)報連相が減る/情報共有の場に乗らない
職員が現場から“心が離れている”兆候です。
辞める気持ちが出ると、「改善や共有に時間を使う意味が薄い」と感じ始めます。
申し送りで最低限しか話さない、会議で意見を言わない。
「共有して」と指示する前に、「共有しづらい理由」を1on1で探る必要があります。
4)ミスが増える/記録が雑になる
能力不足ではなく、心身の余裕不足の可能性が高いです。
疲労が溜まると注意力が落ち、丁寧さが維持できません。
記録の抜け、ダブルチェック漏れ、ヒヤリハットが増える。
責めるより「今どこが一番きつい?」を聞き、負担の“原因業務”を特定しましょう。
5)仕事のスピードが落ちる/動きが鈍くなる
限界が近いサインです。
睡眠不足・疲労・ストレスで身体が動かなくなります。
休憩後も戻りが遅い、移動がゆっくり、表情が硬い。
勤務の見直し(夜勤回数・連勤・役割)を“本人と合意して”微調整するのが先です。
6)苦手業務・夜勤・委員会を避ける発言が増える
「これ以上は抱えられない」というSOSの可能性があります。
優秀な人ほど背負い込み、限界で「もう無理」が出ます。
「夜勤がきつい」「委員会は難しい」「他の人に任せたい」など。
逃げと決めつけず、“何が負担か”を言語化して手当てしましょう。
7)有休を固めて取りたがる/急に休み希望が増える
転職活動や心身回復の準備に入っている場合があります。
面接・見学・研修参加など、外部に動く時間が必要になるからです。
月後半に連続休み希望、平日休みの希望が増える。
詮索ではなく「休み方を工夫したい?体調面?」と目的を確認するのが先です。
8)申し送りや会議で発言しなくなる(提案が消える)
現場に期待していない状態かもしれません。
提案しても変わらない経験が続くと、意見を言うエネルギーがなくなります。
「特にありません」が増える、目線が下がる。
まずは「以前の提案、ちゃんと拾えてなくてごめん。今一番困ってることを教えて」と修復から入ります。
9)諦め言葉が出る(「どうせ変わらない」「もういいです」)
退職の最終段階に近い危険サインです。
改善の期待が切れると、決断が固まります。
相談しなくなる、反応が薄い、淡々としている。
ここまで来たら、次章の「24時間以内の初動」を最優先してください。
10)優秀な人ほど“周囲の負担”を背負い、静かに疲弊している
優秀な人の離職は、「本人の弱さ」ではなく「構造の偏り」で起きます。
頼られる人に仕事が集まり続けると、限界が来ます。
新人フォロー、難ケース対応、急変対応、記録の尻拭いが集中する。
個人の気合いで解決しようとせず、仕事の配分と仕組みを見直すのが正解です。
前兆に気づいたときの初動|24時間以内にやる声かけと1on1

初動はシンプルでOKです。①短い声かけ(詰めない)→②翌日までに1on1確保→③原因の言語化→④最小の改善を1つ合意。これだけでも「放置されていない」という安心感が戻ります。
退職が進む一番の加速要因は、本人の中で「ここにいても変わらない」が確信になることです。初動で“話を聞く姿勢”を示すだけでも、流れを止められます。
まずは30秒の声かけ(例文そのまま使えます)
最初の一言は「評価」ではなく「気づき+心配」です。
「辞めるの?」と聞くと、防衛反応が出て本音が引っ込みます。
目的は退職確認ではなく、“話せる空気を作る”ことです。
1on1の進め方(20〜30分でOK)
1on1は「原因探し」より先に、「安心」を作ることが大事です。
安心がないと本音が出ず、表面的な話で終わります。
以下の順番で進めると、現場でも回しやすいです。
- 感謝(まず先に):「いつも助かってる。ありがとう」
- 観察事実:「最近、会議で発言が減った気がして心配」
- 確認:「今の負担、10段階でいうとどれくらい?」
- 原因の棚卸し:「一番しんどいのは“業務量・人間関係・成長不安・家庭事情”のどれ?」
- 最小改善の合意:「今週できる小さな改善、1つだけ決めよう」
- 次回設定:「来週同じ時間で10分フォローさせて」
“改善提案”を盛り込みすぎず、まずは1つに絞るのがポイントです。
1on1質問テンプレ(原因特定用10問)
やってはいけないNG初動(関係を壊します)
- 「辞めるの?」「いつ辞めるの?」と詰める
- 「みんな大変」「甘えるな」と一般論で片付ける
- 原因の前に“引き留め条件”を提示して取引にする
- その場しのぎの約束をして、フォローしない
初動で“聞く姿勢”と“1つの改善合意”ができれば、離職確定の流れを止めやすくなります。次は、そもそも優秀な職員が辞める理由を整理します。
優秀な介護職員が辞める主な理由(データ+現場の実感)

優秀な職員が辞める理由は、給与だけではありません。多くは「人間関係」「負担の偏り」「評価・成長の見通し」「勤務の無理」「改善が進まない諦め」が複合して起きます。
優秀な人ほど仕事を回せてしまうため、課題が“その人の頑張り”で隠れてしまいます。結果として負担が集中し、本人が静かに燃え尽きます。
理由1:負担が集中する(頼られすぎる)
優秀な人ほど、仕事が集まりやすい構造があります。
「早い・丁寧・安心」だから任せたくなる。しかし、それが続くと限界が来ます。
難ケース、急変、家族対応、新人指導、委員会運営が集中。
配分の偏りを見える化し、役割を分散しない限り、同じ離職が繰り返されます。
理由2:人間関係の消耗(言えない・頼れない)
介護現場の離職理由で、根が深いのは人間関係です。
毎日チームで動く仕事だから、関係性の摩耗が続くと回復しにくい。
小さな不満が溜まり、相談しない→孤立→転職で解決しようとする。
対策は「仲良く」ではなく、「言える仕組み(1on1・相談窓口・ルール)」です。
理由3:評価・成長の見通しがない(頑張り損)
優秀な人ほど、成長の天井が見えると離れます。
努力が評価や役割に反映されないと、外に可能性を求めます。
「任されるだけで報われない」「役割が増えるほど損」と感じる。
評価の透明化、役割と手当の整合、キャリアの見える化が必要です。
理由4:勤務の無理(夜勤・連勤・休めない)
体力の限界は、気持ちでカバーできません。
睡眠不足や連勤が続くと、判断力も対人余裕も落ちます。
夜勤回数、急な残業、休憩が取れない、希望休が通らない。
まずは「一時的な調整」で回復の余地を作り、次に構造を整えます。
理由5:「変わらない」と諦める(改善が進まない)
最後に決断を固めるのは“諦め”です。
提案しても変わらない経験が続くと、心が離れます。
「言っても無駄」「どうせ変わらない」→退職準備。
小さな改善を確実に実行し、“変わる実感”を積むことが最大の離職対策です。
理由が分かったら、次は具体策です。今週・今月・3か月で何をするか、現場で回せる形に落とし込みます。
引用元:公益社団法人介護労働安定センター 令和5年度 介護労働実態調査結果 2024年7月
離職を防ぐ具体策|短期(今週)・中期(今月)・構造(3か月)

離職対策は「大改革」ではなく、小さな改善を確実に実行して信頼を回復することが近道です。まずは今週できることから始め、次に今月、最後に3か月で構造を整えます。
退職を考える人は、早く状況を変えたい。長期計画だけ示されても「今が苦しい」が解決しません。
短期(今週):まず1つ、負担を減らす(小さな改善合意)
今週は“1つだけ”でOKです。
改善の実行が見えると、「ここで続けられるかも」が戻ります。
1on1で決めた改善は、必ず期限(例:2週間)と次回確認日をセットにします。
中期(今月):改善提案の型で“現実的に”前に進める
改善は「不満」ではなく「提案」に落とすと進みます。
改善提案の型(そのまま使えます):
- 現状:今困っていること(いつ・どこで・何が)
- 影響:誰にどんな影響が出ているか(ミス・残業・不満)
- 原因仮説:なぜ起きているか(人・手順・役割・情報)
- 提案:現実的な案を1〜2個(まず小さく)
- 条件:必要な支援(時間・人・物)
- 期限:いつまでに何をやるか
「夜勤明けの記録が雑になりミスが増える → 明けの15分を“記録専用”にし、相方が見守りをカバー → 2週間試す」
全員が納得する完璧案より、“小さく試して改善する”方が離職対策としては強いです。
構造(3か月):負担の偏りを見える化して“仕組み”で守る
優秀な人を守るには、属人化を減らす仕組みが必要です。
- 役割の棚卸し:誰が何を背負っているか一覧化
- 難ケース対応のルール:特定の人に集中しない
- 新人指導の分担:主担当+副担当で抱えない
- 相談ルートの明確化:困ったら誰に何を言うか
- 月1の短い1on1運用:5〜10分でも“継続”が効く
仕組みがない現場では、結局「頑張れる人」が損をして辞めます。
3か月で“偏りを減らす仕組み”を作ると、離職は長期的に下がりやすくなります。
突然退職を申し出られた時の対処法
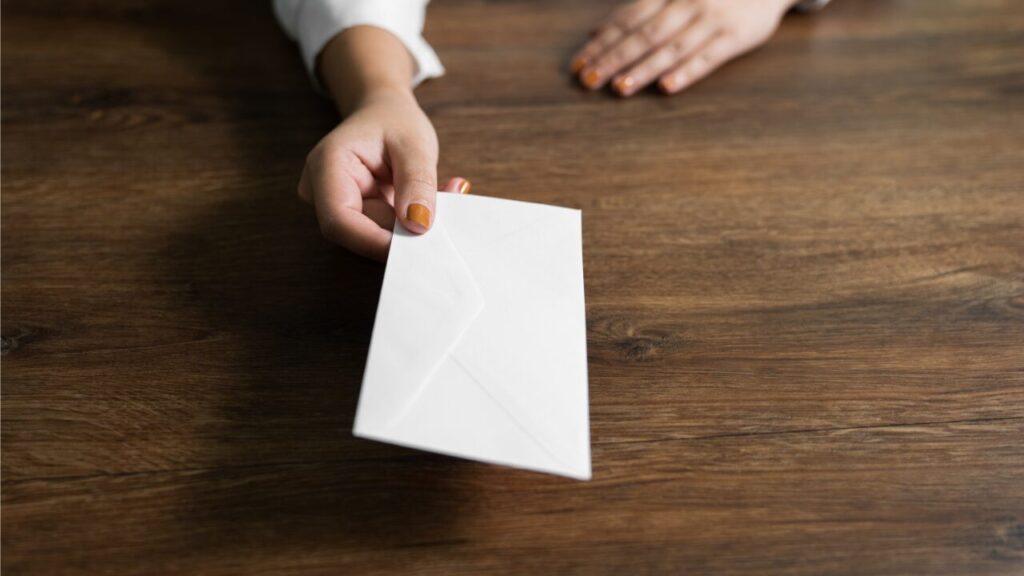
突然の退職申し出が来たら、まずは感情的に引き留めず、「受け止める→理由を整理する→選択肢を提示する→本人の決定を尊重する」の順で対応します。強引な引き留めは、信頼を壊して悪い口コミにもつながりやすいので注意が必要です。
退職を口にする時点で、本人の中では相当悩んだ末の決断であることが多いからです。ここで否定されると、「もう話しても無駄」と関係が切れます。
退職面談で聞く順番(コピペ用)
引き留めの提案は“取引”ではなく“改善”として提示する
提案は「あなたのため」だけにせず、現場全体の改善として伝えるのがポイントです。
「夜勤回数を減らす」だけでなく「偏りを是正する仕組みを作る」とセットで提示する。
本人が残らなかったとしても、改善が残れば次の離職を防げます。
引き継ぎ・リスク管理(最低限ここは守る)
- 個別ケースの注意点(転倒リスク・服薬・食事形態・家族対応)を一覧化
- 担当業務(委員会・研修・物品)を棚卸し
- 残職員の負担が急増しないよう、シフトと役割を前倒しで再設計
突然の退職は痛いですが、対応次第で「次の離職」を防ぐチャンスにもなります。
※ 人手不足の原因と背景について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigostaff-gensyou-haikei/
※ 介護職の退職理由について詳しく知りたい方はこちら>>>https://asu-asu.blog/kaigosyoku-taisyokuriyuu7sen-saishinban/
介護職の離職率と事業所への影響

介護業界の離職率は年度により変動しますが、概ね1割強(約13%前後)と言われることが多く、決して低くありません。離職は「一人減る」だけで終わらず、現場全体に連鎖します。
介護はチームで回す仕事です。欠員が出ると残業・夜勤負担が増え、ミスや不満が増え、さらに離職が続く“負のスパイラル”に入りやすいからです。
採用コスト・教育コスト、業務の属人化、家族対応の不安、稼働率への影響、事故リスクの増加などが同時に起きます。
だからこそ、辞める直前の対応よりも、前兆段階での初動と仕組みづくりが、最も費用対効果が高い対策になります。
引用元:公益財団法人介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について 2025年7月28日
FAQ(よくある質問)

Q1:介護職が辞める前兆で一番多いのは?
一番多いのは「コミュニケーションの減少(雑談・報連相・発言が減る)」です。
心が現場から離れると、まず“関わり”が減るからです。
申し送りで最低限しか話さない、会議で意見が消える。
変化に気づいたら、詰めずに早めに1on1を入れるのが効果的です。
Q2:退職を引き留めるのは違法になりますか?
丁寧な対話や条件提示は問題になりにくい一方、強要や圧力は避けるべきです。
本人の意思決定を尊重しない対応は、トラブルにつながりやすいからです。
脅し、人格否定、退職届を出させない、過度な引き止め。
「受け止め→理由整理→改善案提示→本人の決定尊重」の順で対応しましょう。
Q3:優秀な職員ほど辞めるのはなぜ?
優秀な人ほど仕事が集中し、静かに燃え尽きるからです。
“頑張れる人”に依存する構造があると、負担が偏ります。
難ケース対応や新人指導が集まり、回復の余地がなくなる。
個人の問題にせず、配分と仕組みを整えることが根本対策です。
Q4:1on1はどれくらいの頻度が現実的?
月1回5〜10分でも継続できれば効果があります。
“定期的に話せる場”があるだけで、抱え込みが減るからです。
夜勤前後の5分、勤務交代の10分を固定枠にする。
完璧な制度より、続く運用が勝ちです。
Q5:前兆が出ている職員に、周囲はどう接すればいい?
周囲は「励ます」より「孤立させない」が正解です。
励ましがプレッシャーになることもあるからです。
声かけ、短い雑談、ペアの調整、負担の見える化。
本人が“助けて”と言いやすい空気を作りましょう。
まとめ|優秀な人ほど「辞める前に」見ている

優秀な職員の離職は、突然ではありません。小さな前兆が必ず出ます。だからこそ、やるべきことは明確です。
- 前兆10選で早期に気づく
- 24時間以内の初動で放置しない
- 1on1で原因を言語化する
- 最小の改善を1つ合意して実行する
- 30日フォローで“変わる実感”を積む
離職対策は、特別な制度より「最初の動き」と「小さな改善の積み重ね」が効きます。まずは、チェックリストで状況を見える化し、気になる職員がいるなら今日中に30秒の声かけから始めてみてください。
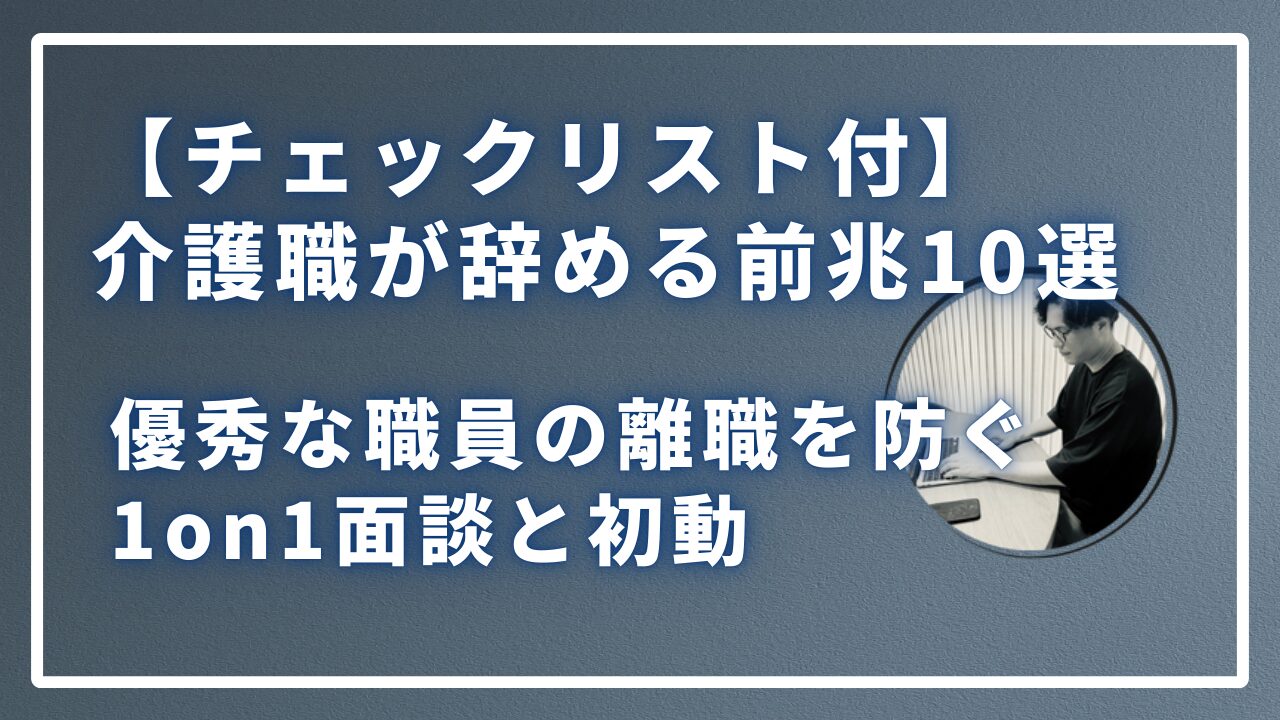
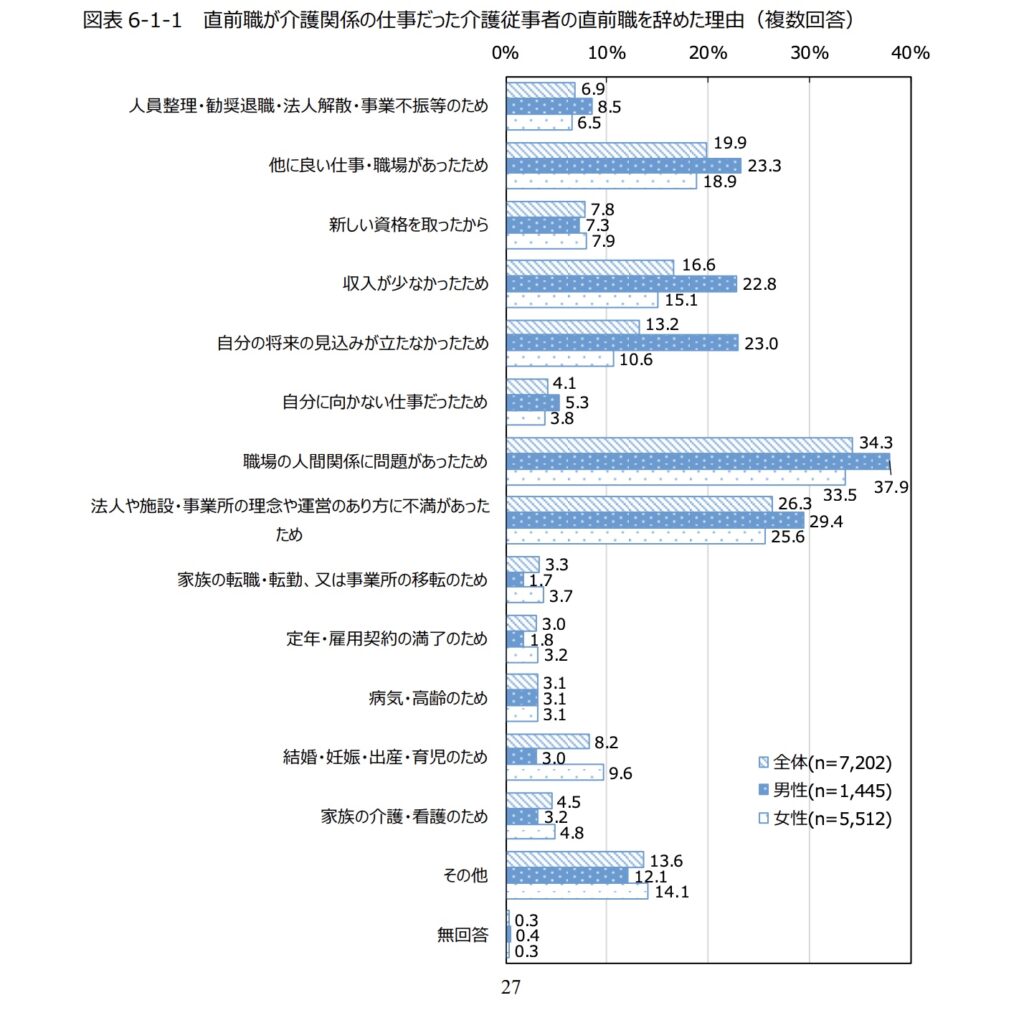
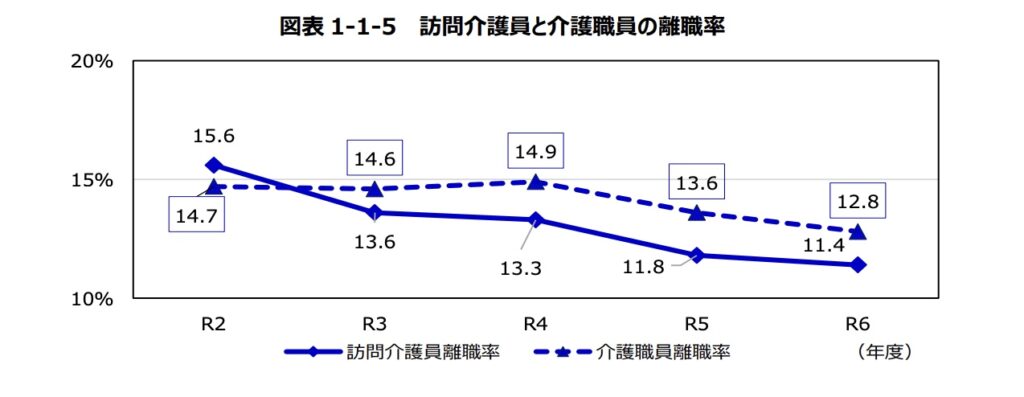
コメント